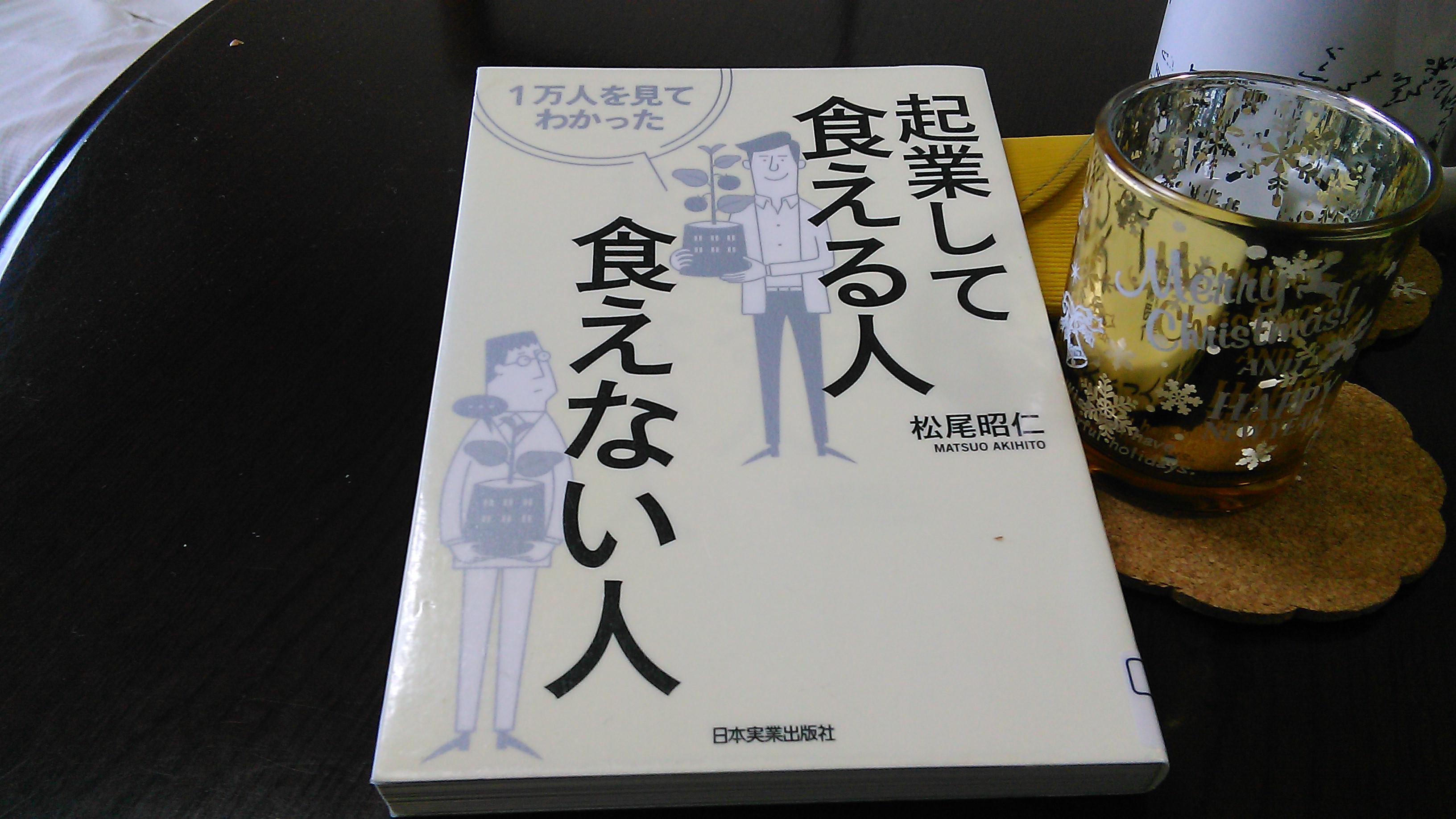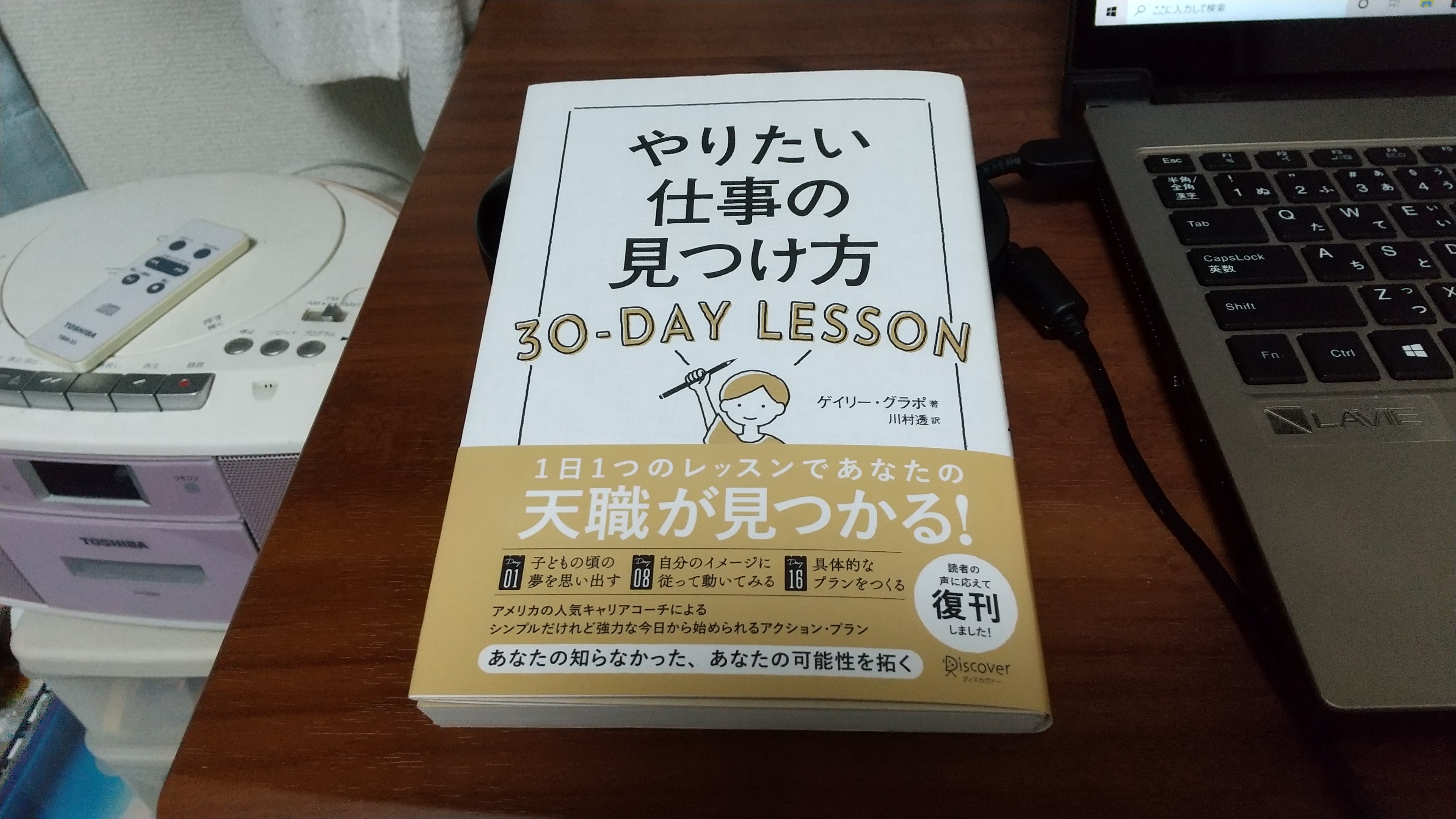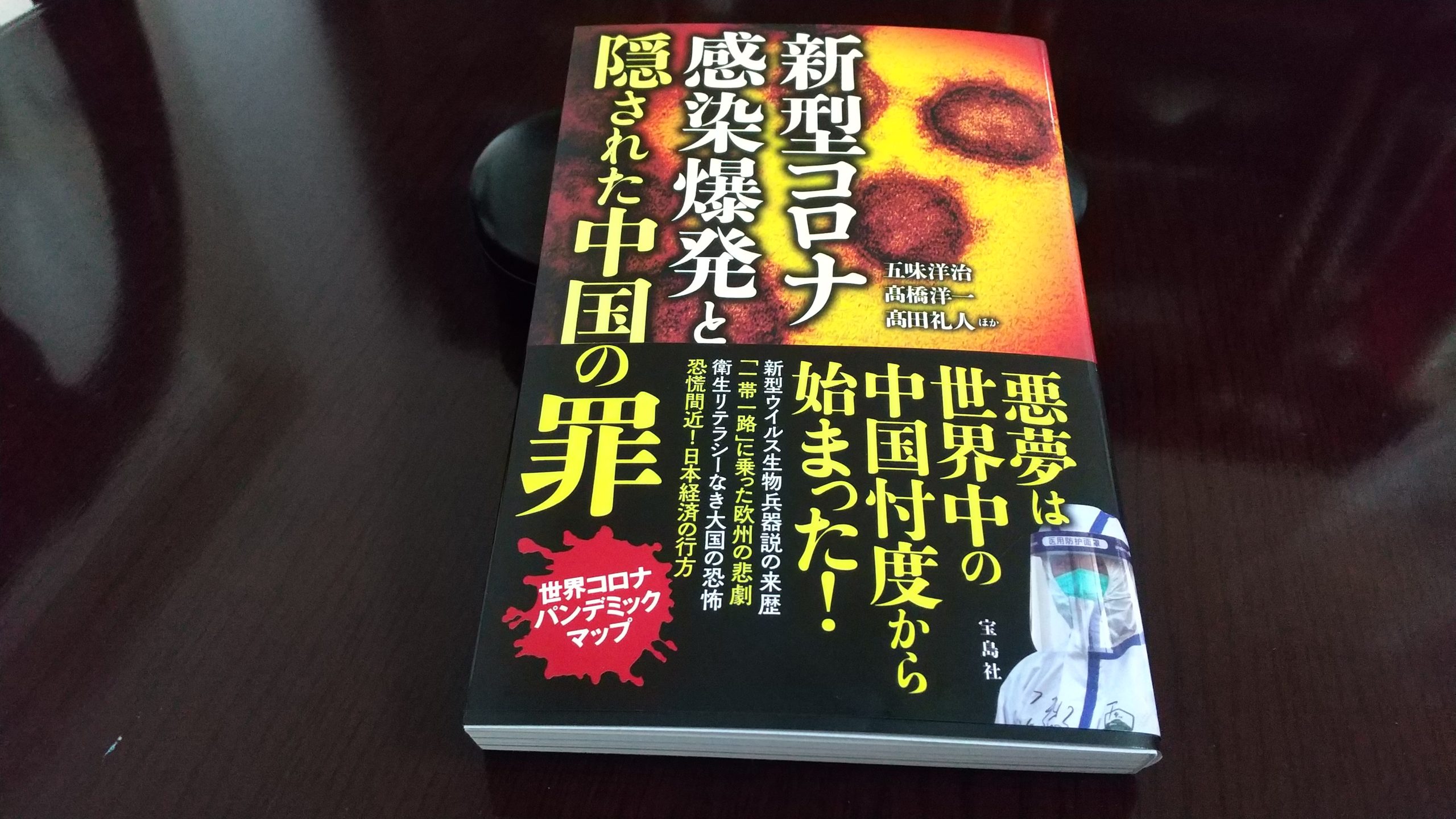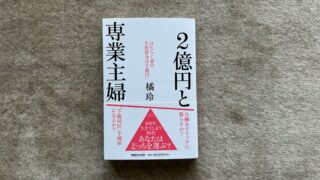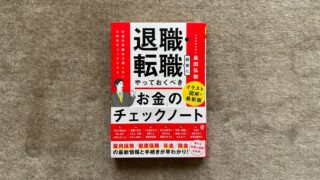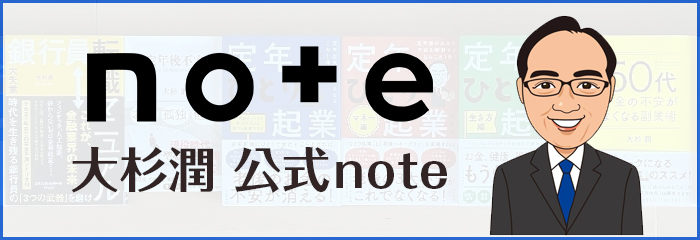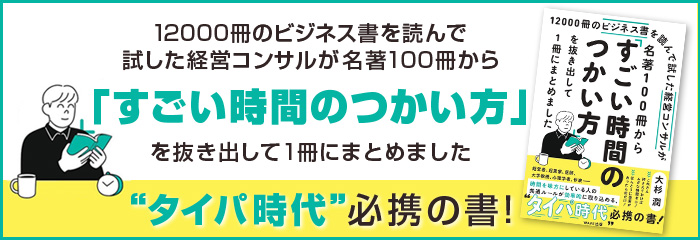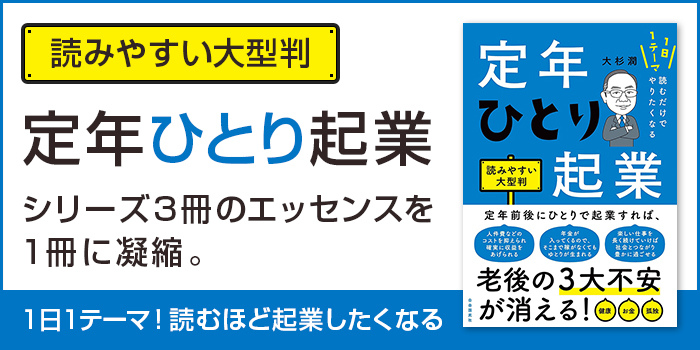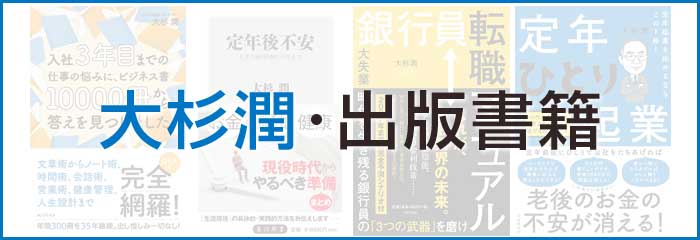『絶対に死ぬ私たちがこれだけは知っておきたい健康の話 「寝る・食う・動く」を整える』
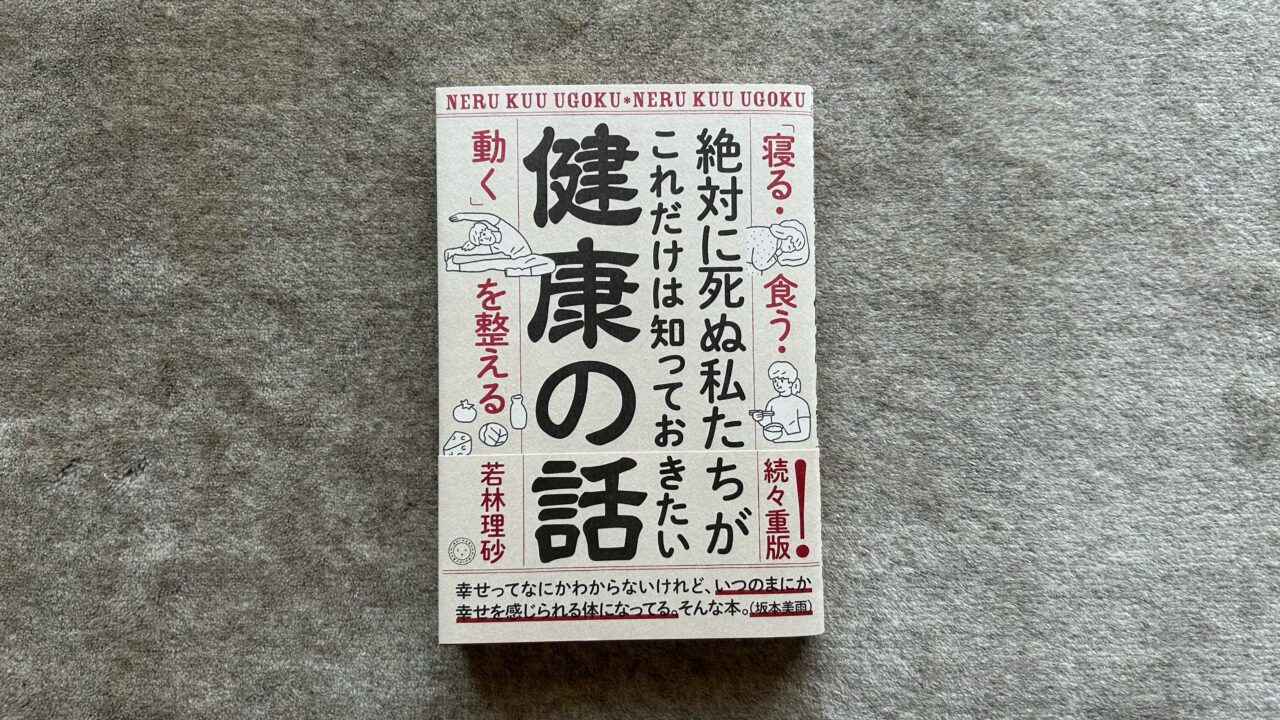
「現代人よ、もっと、もっと、もっと寝よう!」――そんなメッセージとともに、健康との向き合い方を見直すための “現代版・養生のすすめ” を教えてくれる一冊があります。
本日紹介するのは、1976年生まれ、高校卒業後に鍼灸免許を取得、早稲田大学第二文学部卒(思想宗教系専修)で、鍼灸師・臨床家として長年にわたり不調に悩む人々に寄り添い、東洋医学の叡智と現代人の生活スタイルを融合させた独自の健康法を実践・提唱している若林理砂さんが書いた、こちらの書籍です。
若林理砂『絶対に死ぬ私たちがこれだけは知っておきたい健康の話 「寝る・食う・動く」を整える』(ミシマ社)
この本は、「寝る」「食う」「動く」という3つの基本動作を、毎日の生活の中でどう整えていくかを実践的に指南する、“暮らしに根ざした東洋医学的ライフスタイル本” です。
この本の冒頭では、「あなたの健康法は、ほんとうに効果がありましたか?」と問いかけ、「健康法の棚卸し」からスタートし、体と心の無理を少しずつ手放していく養生生活を提案しています。
本書は以下の6部構成から成っています。
1.健康法の棚卸し
2.「ハレ」と「ラク」が招く不健康
3.「寝る・食う・動く」の時間を決める
4.「寝る・食う・動く」の質を高める
5.風邪は引き初めに東洋医学で治す
6.生活そのものが養生になる
本書の前半では、「健康神話をリセットし、生活習慣を再構築する」ための以下のポイントが強調されています。
◆ “健康にいい”とされる習慣でも、自分に合っていなければ逆効果になる
◆ 体調不良の原因は、過労や無理なスケジュールに起因していることが多い
◆ 「ハレ」と「ラク」を求めすぎると、結果的に自律神経を乱す
◆ 健康は「意志の力」で保つのではなく、「仕組み」で整える
◆ 食事・睡眠・運動の“時間”を決めて、自分の身体に合ったリズムを作ることが重要
この本の中盤では、「生活の質を高める技術」として、以下のような具体的なノウハウが紹介されています。
◆ 睡眠の質は、寝室・布団内の温湿度管理で大きく変わる
◆ 野菜中心の食事が、花粉症や慢性症状の緩和に効果あり
◆ 運動は「ラジオ体操」で十分──時間より“毎日”がカギ
◆ スマホやSNSの使用時間を制限し、神経を鎮める時間を意識的につくる
◆ 自分の体調を日々観察し、微調整していく感覚が「養生力」になる
本書の後半では、「風邪・不調の初期対応」と「生活そのものを養生に変える視点」が示されています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 葛根湯は風邪の初期に飲めば高い効果を発揮する
◆ 医療に頼り切るのではなく、自分の感覚を信じてセルフケアする
◆ 養生とは“特別なこと”ではなく、“暮らしの中の小さな選択”の積み重ね
◆ 健康は目的ではなく、楽しく生きるための土台である
◆ 続けていけばいくほど、気力・体力・財力が自然と増えていく
この本の締めくくりとして著者は、「養生と生きる楽しみを繰り返していくことができれば、“ああ楽しかった”と息をひきとるその日まで、健やかに生きられる」と語っています。
私たちは誰しも “絶対に死ぬ” 存在ですが、だからこそ、その日まで「自分の体を大切に扱うこと」が、生きる楽しみへとつながっていくのです。
あなたも本書を手に取り、今日からできる“養生の一歩”を始めてみませんか?
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3775日目】