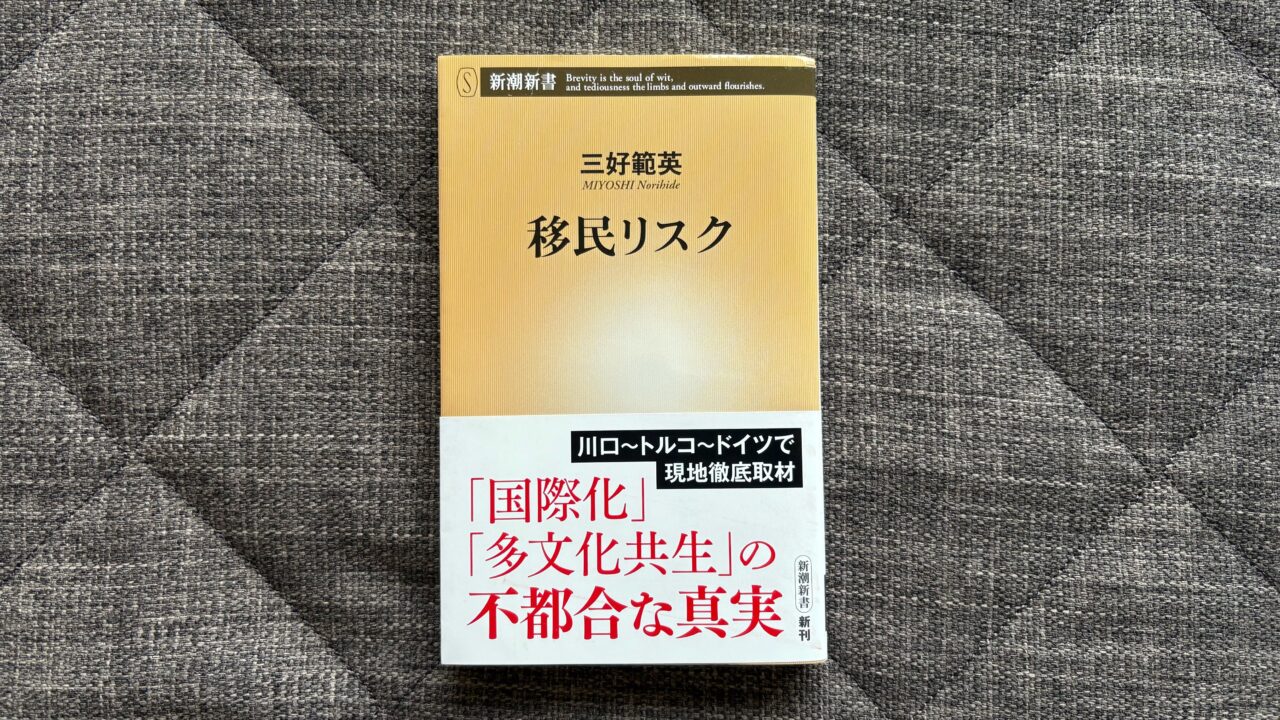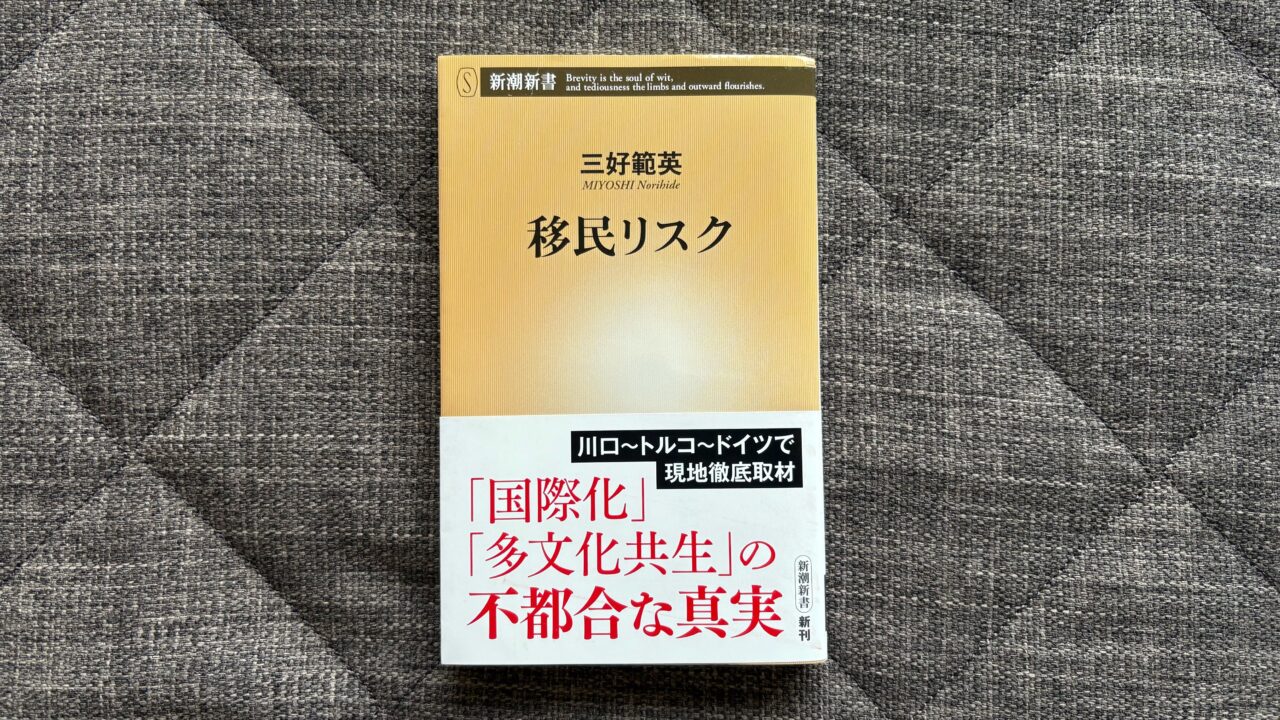「“外国人は日本人ではない”――この当然の原則を見失うと、国家の基盤が揺らぐ。」――そんな警鐘の言葉で、いま日本が直面する「移民問題」の現実を鋭く描き出す一冊があります。
本日紹介するのは、1959年東京都生まれ、東京大学教養学部卒業後、読売新聞社に入社。バンコク、プノンペン、ベルリンの特派員として国際報道に携わり、欧州の移民・難民問題を長年取材してきた国際派ジャーナリスト・三好範英(みよし・のりひで)さんが書いたこちらの書籍です。
三好範英『移民リスク』(新潮新書)
この本は、埼玉・川口市で現実化した「クルド人問題」を起点に、日本の入管行政・難民政策・地域社会のひずみを徹底的に取材したルポルタージュです。
著者は、欧州の “移民先進国” ドイツを取材してきた経験から、「理想論だけでは社会は守れない」という現実を日本に突きつけます。
人口減少、労働力不足、人道的支援――移民受け入れの理由は多々あれど、そこに “リスク ”が潜むことを冷静に描く問題作です。
本書は以下の4部構成から成っています。
1.川口・蕨「クルド人問題」の真相
2.「入管の闇」という偏向
3.移民規制に舵を切ったドイツ
4.理想論が揺るがす「国家の基盤」
本書の前半では、「川口・蕨のクルド人問題」および「入管行政への批判」を中心に、日本の現場が抱える矛盾を明らかにしています。主なポイントは以下の通りです。
◆ トルコ語のゴミ出しルール、住民との摩擦など地域の “共生の限界” が露呈
◆ 難民申請を5回繰り返し、20年間在留できる “制度の抜け道”
◆ 不法就労、生活保護、出産ラッシュ――社会保障への影響が拡大
◆ 「クルド人=政治難民」というイメージが現実を見えにくくしている
◆ メディアの “入管批判一辺倒” が、現場の混乱を深めている
この本の中盤では、「ドイツの移民政策の変遷」を通して、日本が今後直面しうるリスクを描きます。主なポイントは次の通りです。
◆ 「移民先進国」ドイツでも、理想と現実のギャップが拡大
◆ メルケル政権の “難民受け入れ” が引き起こした社会分断と治安悪化
◆ 不法残留者の送還が困難化し、犯罪・テロ事件が増加
◆ メディアが“人道”を優先し、問題を報じない “沈黙の構造”
◆ 左派政権でさえ“送還促進・流入制限”に舵を切らざるを得なかった
本書の後半では、「理想論が国家を揺るがす」という視点から、移民政策の本質的課題を掘り下げます。主なポイントは以下の通りです。
◆ 「子供在特」など特例措置が、法の平等性を崩す危険
◆ 送還実務の難航――現場の入国警備官は疲弊
◆ 査証免除の見直しこそ、リスク抑止の最優先策
◆ 事前審査の強化やAIによる監視システムの必要性
◆ 多数派(国民)が多数派であり続けることの意味――国家の存続の根幹
本書の魅力は、イデオロギーや感情論に流されることなく、“現場取材” に基づいて移民問題を客観的に分析している点にあります。
川口の街頭からトルコのクルド地域、ドイツの移民コミュニティまで足で取材を重ねた筆致には、記者としての冷静な視点と使命感が宿ります。
著者はこう警告します。
「理想だけでは社会は持たない。寛容の名のもとに“秩序”が崩れれば、守るべき国民が苦しむ。」
日本がいま選ぼうとしている “移民国家への道” の先に何が待つのか――。
本書は、その問いに正面から向き合うための、貴重な現実レポートです。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3904日目】