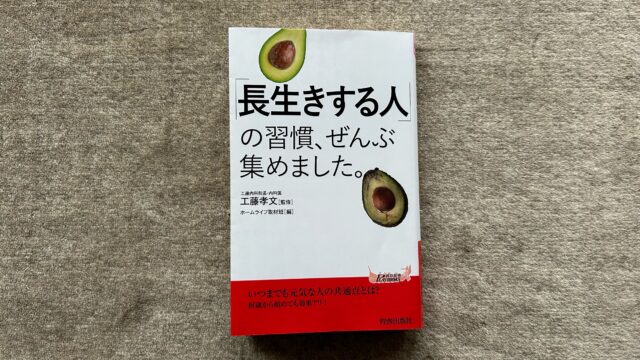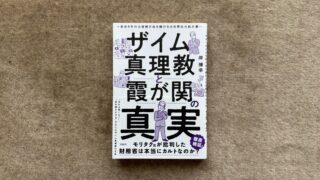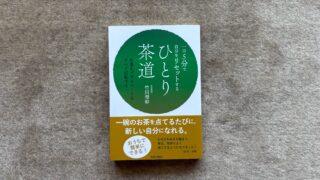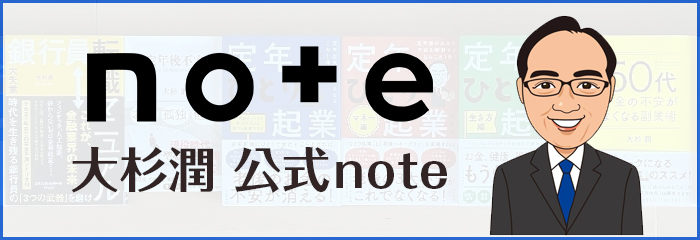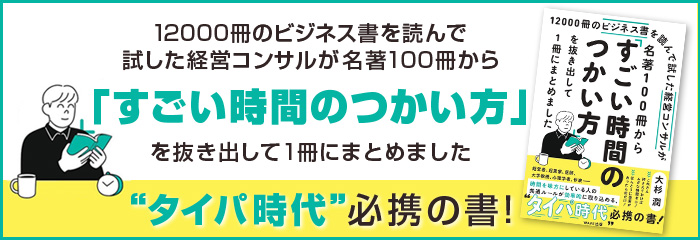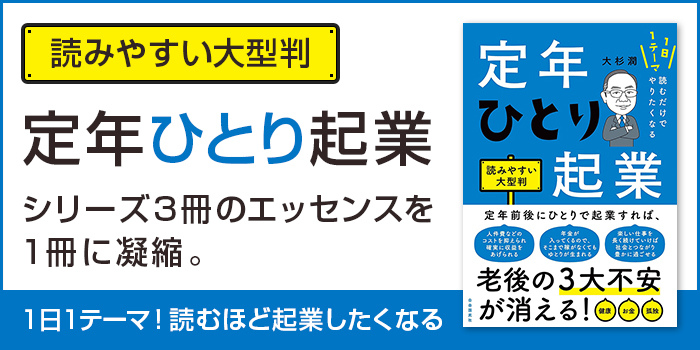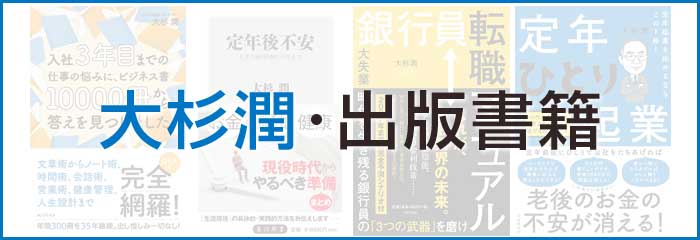『おひとりさま時代の死に方』
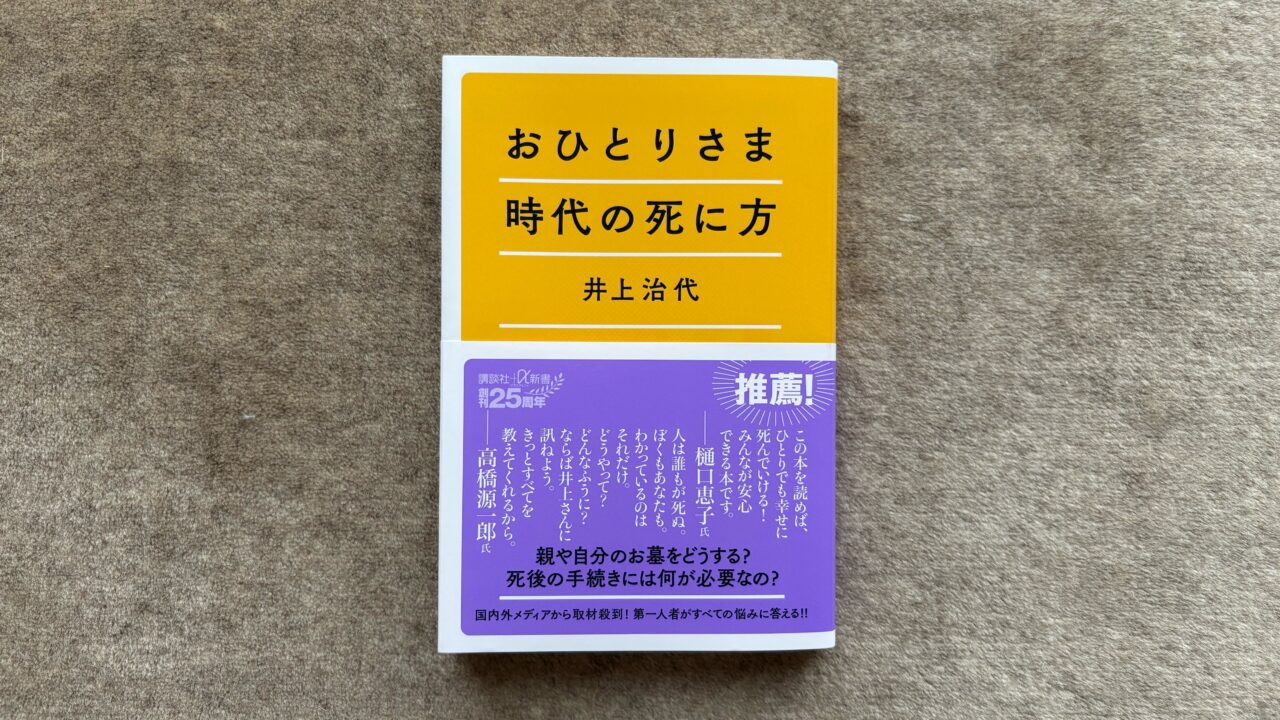
「親や自分のお墓をどうする? 死後の手続きには何が必要なのか?」――誰もが避けて通れないテーマに正面から取り組んだ一冊があります。
本日紹介するのは、尊厳ある死と葬送の実現をめざした認定NPO法人エンディングセンターを立ち上げ、「桜葬」墓地や「墓友」活動を展開、東洋大学教授を経て、同大・現代社会総合研究所客員研究員、エンディングデザイン研究所代表を務める社会学博士の井上治代(いのうえ・はるよ)さんが書いたこちらの書籍です。
井上治代『おひとりさま時代の死に方』(講談社+α新書)
この本は、死に方というタブーを解きほぐし、「おひとりさま」の時代に誰もが直面する現実的課題を、研究と実践に基づいて提示する、まさに安心と希望を与える一冊です。
本書は以下の4部構成から成っています。
1.家と墓はどう変化してきたか?
2.おひとりさま時代の「桜葬」と「墓友」
3.日本と海外の「自然葬墓」
4.ひとりで死んだらどうなるか?
この本の冒頭で著者は、本書執筆の原点が「墓の継承問題」と「身寄りのない人の死後の担い手問題」にあると述べています。そして、市民団体の活動も踏まえつつ、人口減少やひとり世帯の増加という大きな社会変化の中で、「死後福祉」の必要性を説いています。
本書の前半では、「家と墓はどう変化してきたか?」および「おひとりさま時代の『桜葬』と『墓友』」を扱い、日本の家族や墓制がどう変容してきたのかを解き明かしています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 家制度に支えられてきた従来型の墓の仕組みが維持できなくなっている
◆ 家族の変容とともに墓のあり方が揺らいでいる
◆ 「桜葬」という新しい形の墓が生まれている
◆ 墓を核に「墓友」という新しい人間関係が生まれている
◆ 墓の変化が社会の孤立や絆の再編と結びついている
この本の中盤では、「日本と海外の『自然葬墓』」を取り上げ、日本・イギリス・韓国の比較を通して新しい葬送文化を論じています。主なポイントは次の通り。
◆ 樹木葬など自然志向の墓が各国で広がっている
◆ 日本の「自然葬」における「自然とは何か」という独自の問い
◆ 西欧や東アジアにおける自然葬の背景
◆ 自然志向の墓が宗教観や価値観の変化を反映している
◆ 墓制の国際比較から日本社会の特徴が浮かび上がる
本書の後半では、「ひとりで死んだらどうなるか?」に焦点を当て、死後の手続きや担い手不在の問題を掘り下げています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 死亡届の「届出人」は誰が担うのかという具体的な課題
◆ 任意後見契約や第三者依頼の必要性
◆ 「友人に頼んである」では法的に不十分
◆ 身寄りのない人の死後を支える仕組みである「死後福祉」
◆ 個人が安心して最期を迎えるための具体的手段
この本の締めくくりとして著者は、「ひとりであっても尊厳ある死を迎えるために、誰に何を託すかを早めに考え、準備することが大切だ」と述べています。
あなたもこの本を読んで、最期を迎えるための準備を考えるきっかけにしてみませんか。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3840日目】