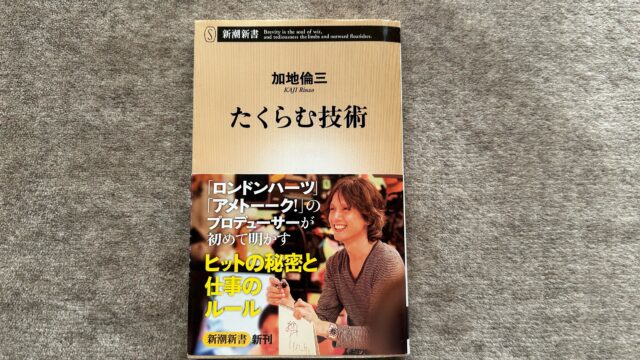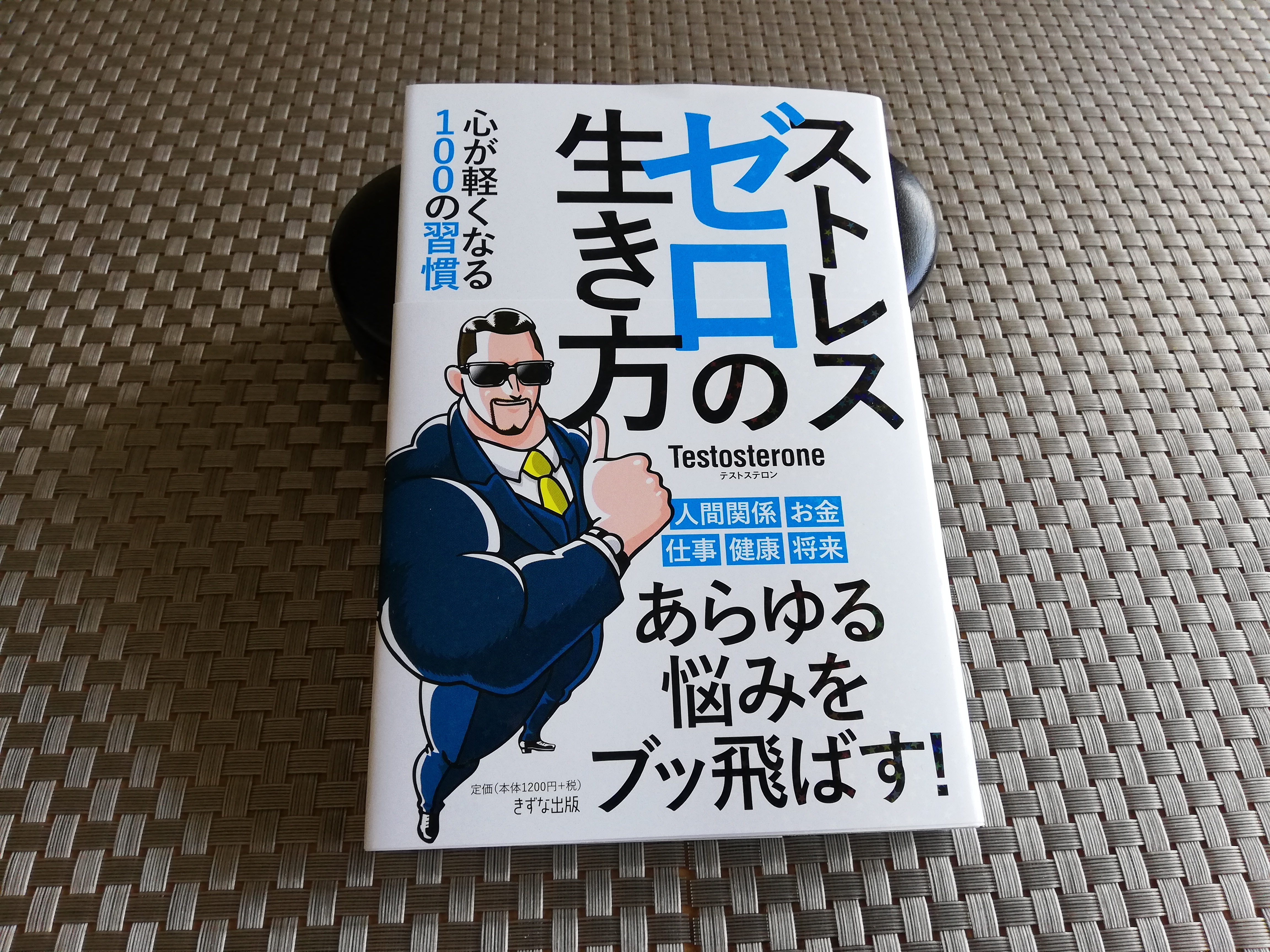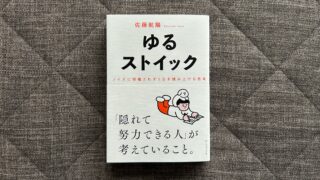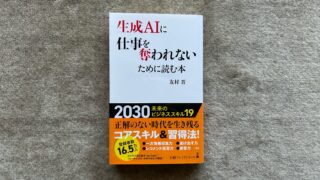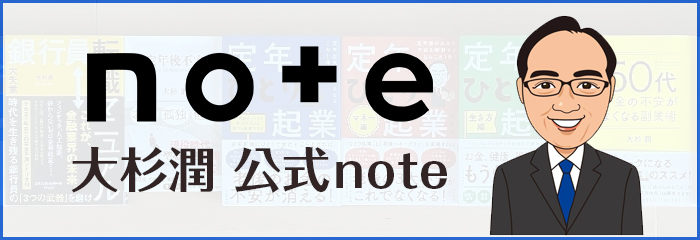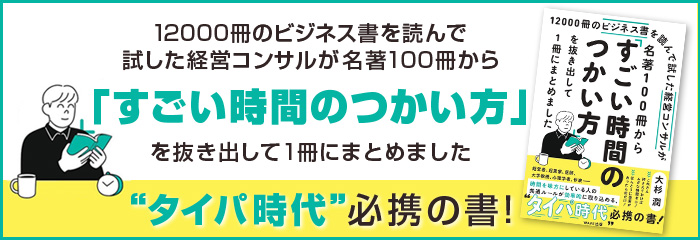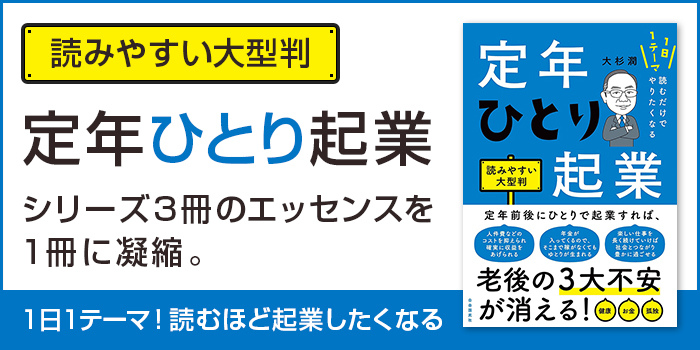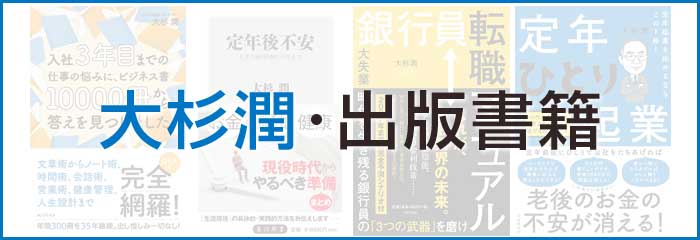『シン読解力:学力と人生を決めるもうひとつの読み方』
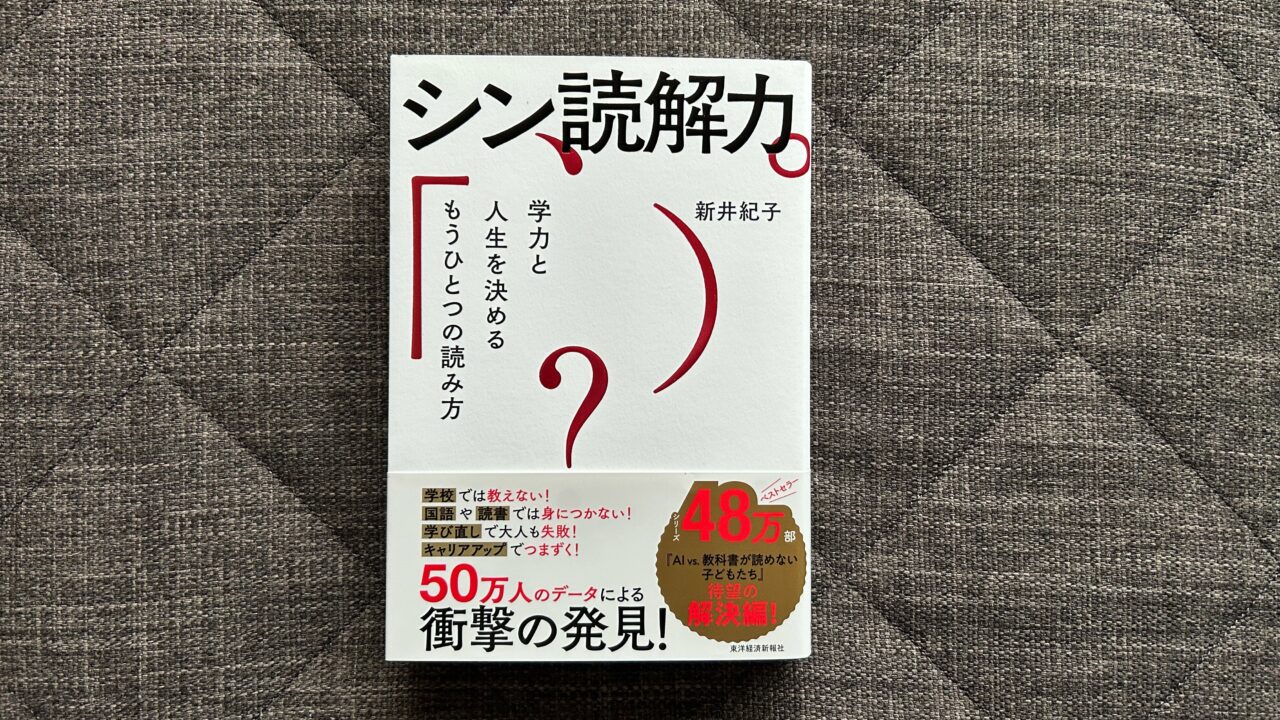
「読解力は、国語の成績や読書量では測れない。」「教科書を正確に読み解く力こそが、学力と人生を左右する。」と述べている本があります。
本日紹介するのは、一橋大学法学部およびイリノイ大学数学科卒業、イリノイ大学5年一貫制大学院を経て、東京工業大学より博士(理学)を取得、専門は数理論理学、2011年より人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトディレクターを務める。2016年より読解力を診断する「リーディングスキルテスト」の研究開発を主導『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』で日本の教育界に衝撃を与えた、国立情報学研究所 社会共有知研究センター長・教授、一般社団法人 教育のための科学研究所 代表理事・所長の新井紀子さんが書いた、こちらの書籍です。
新井紀子『シン読解力:学力と人生を決めるもうひとつの読み方』(東洋経済新報社)
この本は、50万人以上が受検したリーディングスキルテスト(RST)のデータをもとに、「教科書を正確に読み解く力=シン読解力」の重要性と、その習得法を解説した書です。
本書は以下の7部構成から成っています。
1.チャットGPTの衝撃
2.「シン読解力」の発見
3.学校教育で「シン読解力」は伸びるのか?
4.「学習言語」を解剖する
5.「シン読解力」の土台を作る
6.「シン読解力」トレーニング法
7.新聞が読めない大人たち
この本の冒頭で著者は、「AI時代において、正確に読み解く力がますます重要になる」と述べています。
本書の前半では、「読解力とは何か?」「なぜ教科書が読めないのか?」について、以下のポイントで説明しています。
◆ RSTの結果、教科書を正確に読めていない子どもが多数存在
◆ 大人も新聞記事を正確に読み解けていない現実
◆ 読解力は才能ではなく、トレーニングで身につくスキル
◆ 読解力と学力には強い相関がある
◆ 読解力が低いと、ビジネスにも支障をきたす
この本の中盤では、「学習言語の特性」「読解力を支える土台」について詳しく解説しています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 教科ごとに異なる「学習言語」の存在
◆ 語彙力と経験が読解力の土台となる
◆ ワーキングメモリの限界と認知負荷の関係
◆ 科学的なトレーニングで認知負荷を下げる方法
◆ 国語や英語の教育方法から学ぶ読解力の育成
本書の後半では、「読解力を伸ばすための具体的なトレーニング法」「社会人における読解力の重要性」など、実践的な内容が紹介されています。主なポイントは以下の通りです。
◆ RSTノートを活用したトレーニング法
◆ 福島県相馬市での読解力向上の成功事例
◆ 読解力は年齢を問わず伸ばすことができる
◆ ビジネスの現場でも読解力が求められる
◆ 採用戦略におけるRSTの活用
この本の締めくくりとして著者は、「読解力は一生もののスキルであり、誰もが身につけることができる」と述べています。
あなたも本書を読んで、「シン読解力」を身につけ、学力やビジネススキルを向上させてみませんか?
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3720日目】