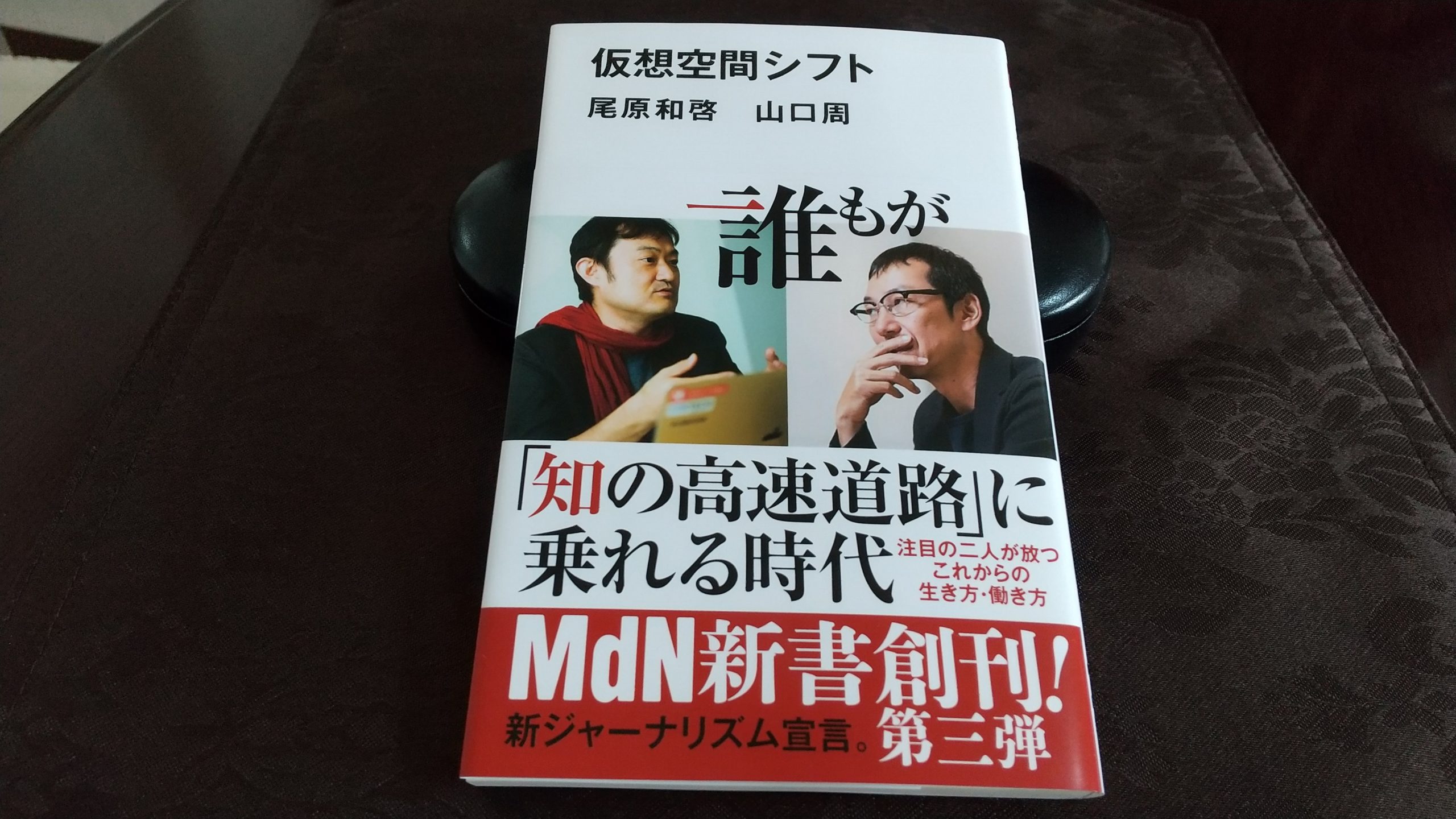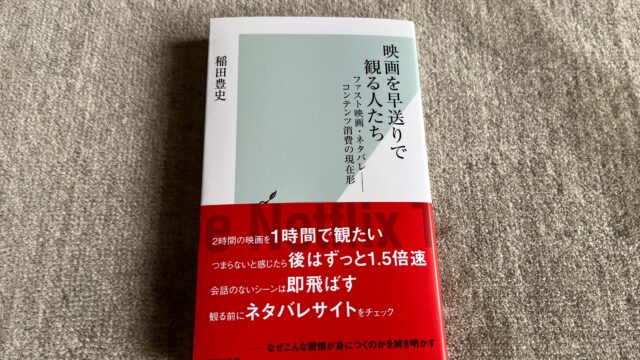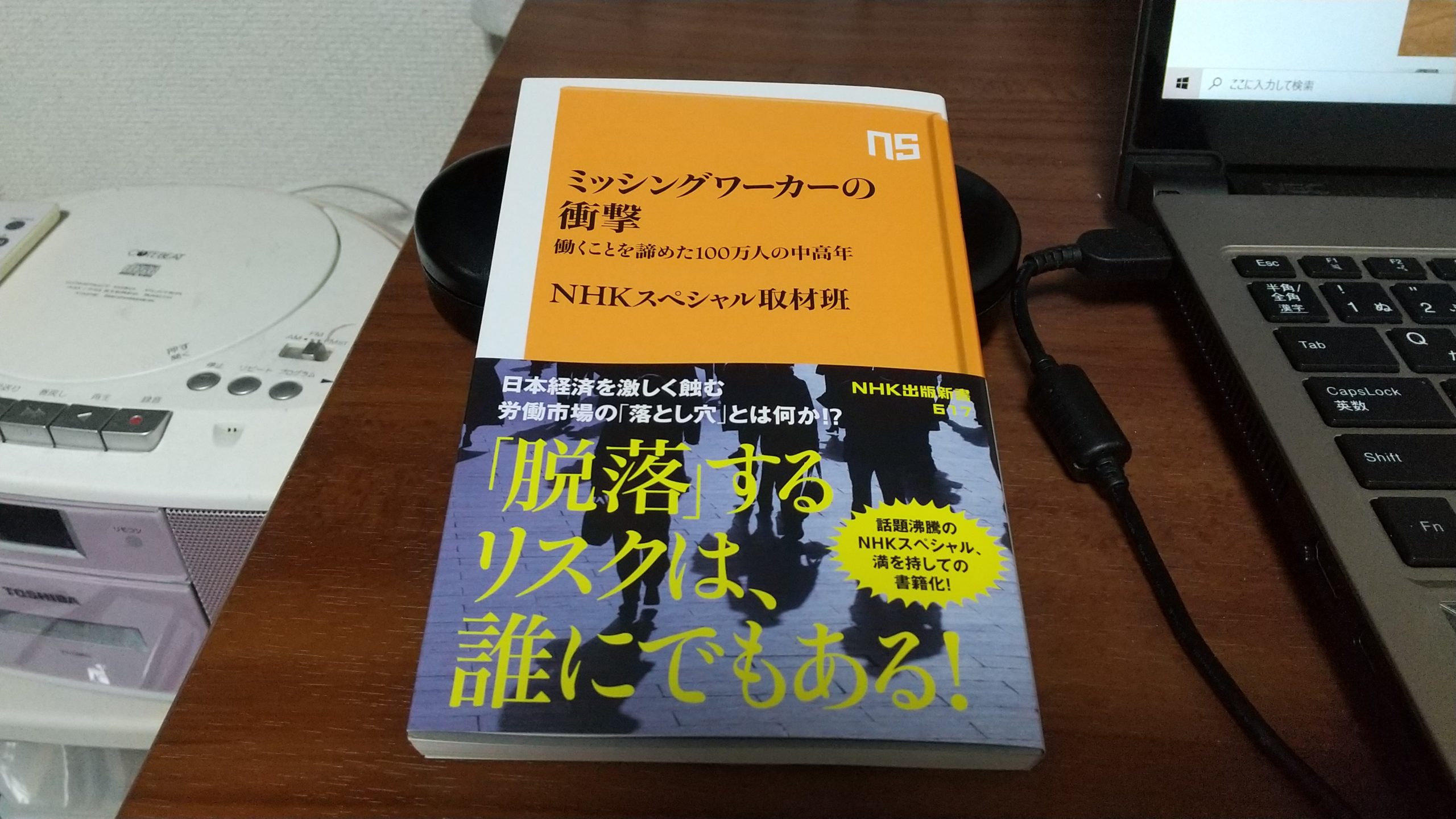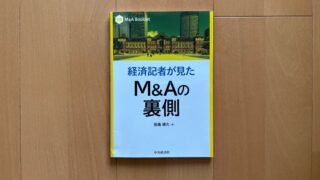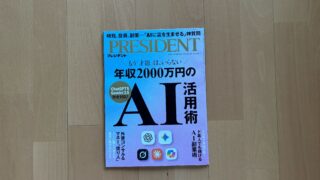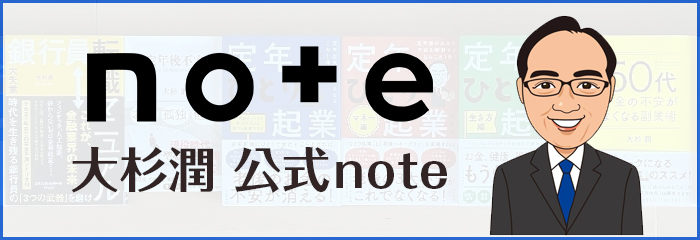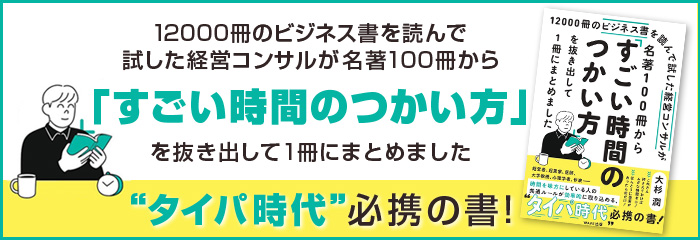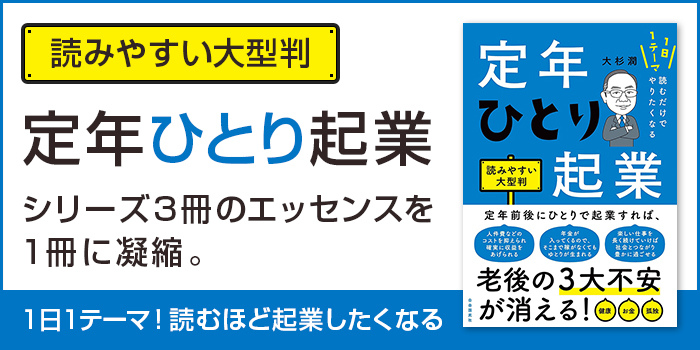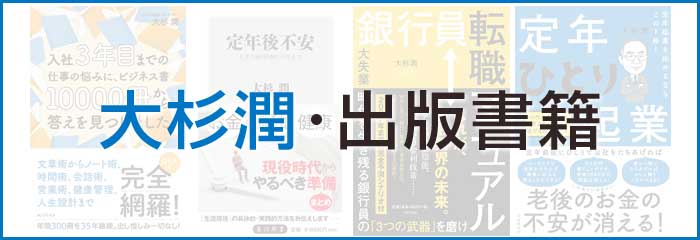『日本の構造 50の統計データで読む国のかたち』
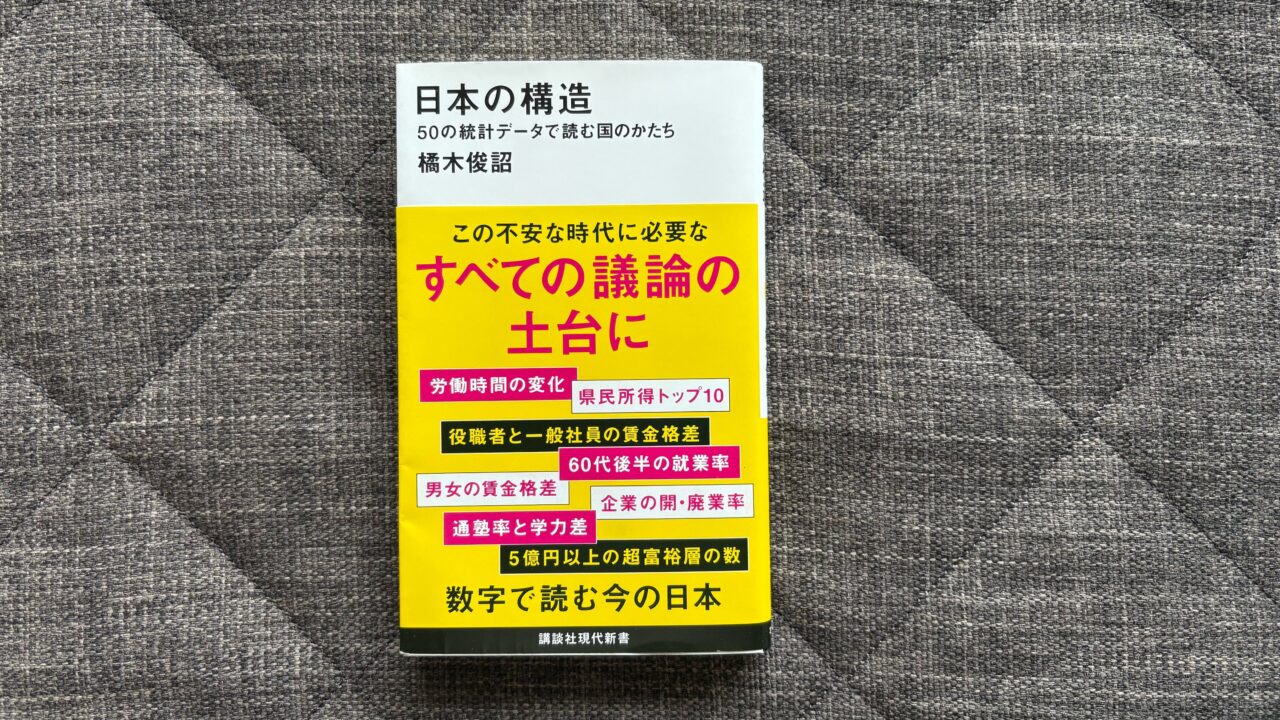
「“50の統計データから、日本の国のかたちが浮かび上がる”」――そんなメッセージを突きつけてくれる一冊があります。
本日紹介するのは、1943年兵庫県生まれ、小樽商科大学、大阪大学大学院を経て、ジョンズ・ホプキンス大学院博士課程修了(Ph.D.)。その後、京都大学教授、同志社大学教授、京都女子大学客員教授を歴任し、現在は京都大学名誉教授を務める橘木俊詔(たちばなき・としあき)さんが書いたこちらの書籍です。
橘木俊詔『日本の構造 50の統計データで読む国のかたち』(講談社現代新書)
この本は、日本社会の実像を50のデータから総点検し、不安な時代に必要な “議論の土台” を提示する一冊です。
本書は以下の10部構成から成っています。
1.日本の今とコロナ禍
2.日本経済の健康診断
3.教育格差
4.日本人の労働と賃金
5.日本人の生活
6.老後と社会保障
7.富裕層と貧困層
8.地域格差
9.財政
10.今後の日本の針路
この本の冒頭で著者は、日本の現状を統計という“確かな物差し”で捉えることが、議論を誤らないための出発点になると強調しています。
本書の前半では、「日本の今とコロナ禍」「日本経済の健康診断」「教育格差」「日本人の労働と賃金」を取り上げ、経済と教育、働き方の構造をデータから浮かび上がらせています。主なポイントは以下の通りです。
◆ コロナ禍で顕在化した社会の脆弱性
◆ 長時間労働の実態と国際比較
◆ 学歴や性別による賃金格差の根強さ
◆ 開廃業率が他国の3分の1にとどまる日本経済の硬直性
◆ 大学進学率や教育投資額に見る家庭環境の影響
この本の中盤では、「日本人の生活」「老後と社会保障」「富裕層と貧困層」に焦点を当て、格差や老後の実態、そして富裕層の姿までを具体的に示しています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 高年収世帯は低年収世帯の3倍の学校外教育費を支出
◆ 60代後半の就業率、男性は50%超・女性は30%超
◆ 社会保障給付の過半が高齢者と遺族向け
◆ 生活保護申請率が必要世帯の1〜2割にとどまる現実
◆ 資産5億円以上を持つ8.7万世帯の存在
本書の後半では、「地域格差」「財政」「今後の日本の針路」において、人口減少社会での構造的な歪みと持続可能性への課題を提示しています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 東京の地方税収は長崎県の2.3倍という地域格差
◆ 学力調査で突出する秋田県と北陸3県の存在
◆ 財政赤字と社会保障費の膨張という二重苦
◆ 地域間の人材・資源配分の偏在
◆ 50のデータから見えてくる「日本の針路」の必然
この本の締めくくりとして著者は、「不安な時代だからこそ、数字に基づいて冷静に議論し、国の未来を見据える必要がある」と述べています。
統計という“鏡”を通じて、日本の構造を客観的に見つめ直すことができる一冊です。ぜひ手に取ってみてください。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3854日目】