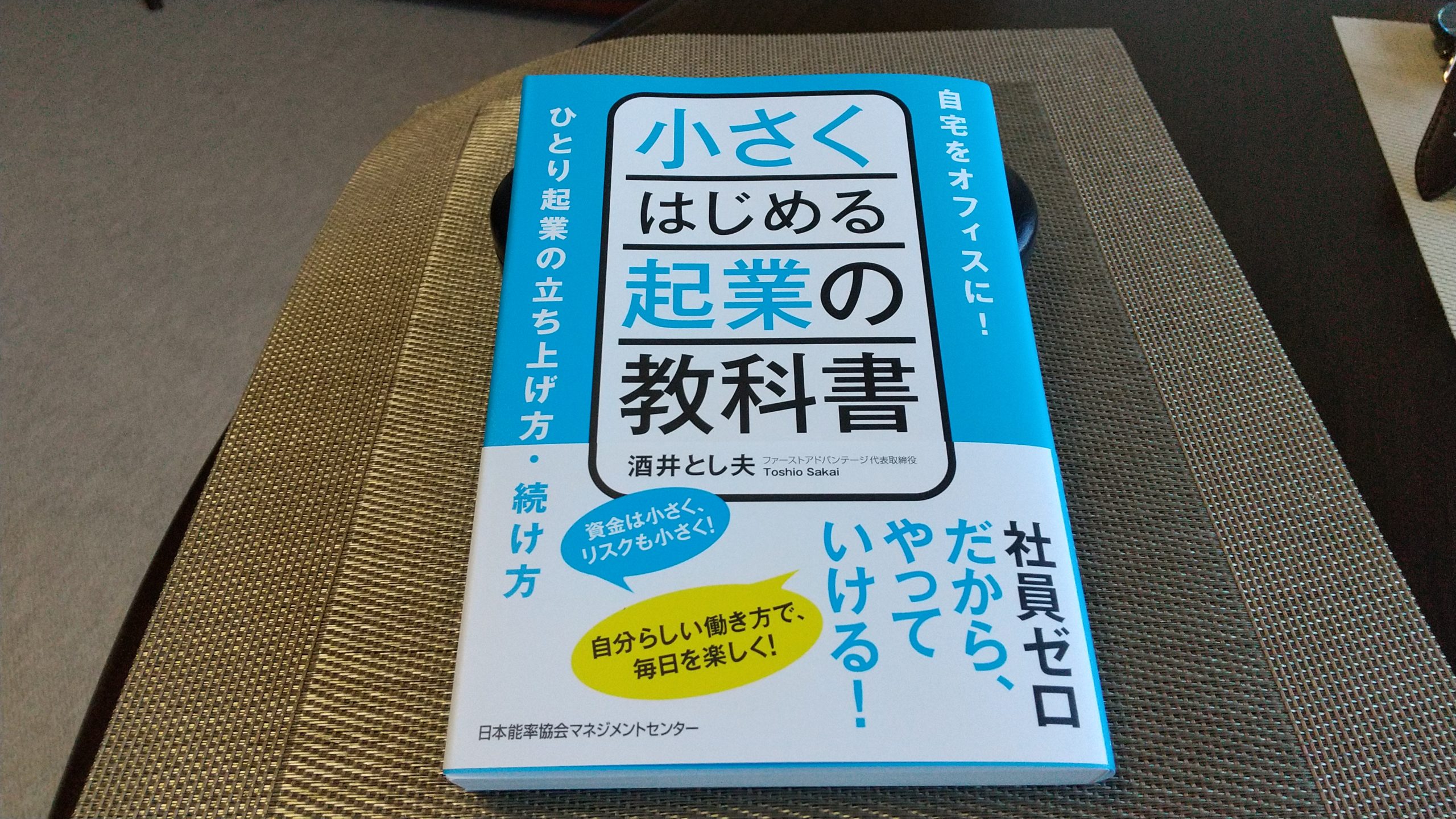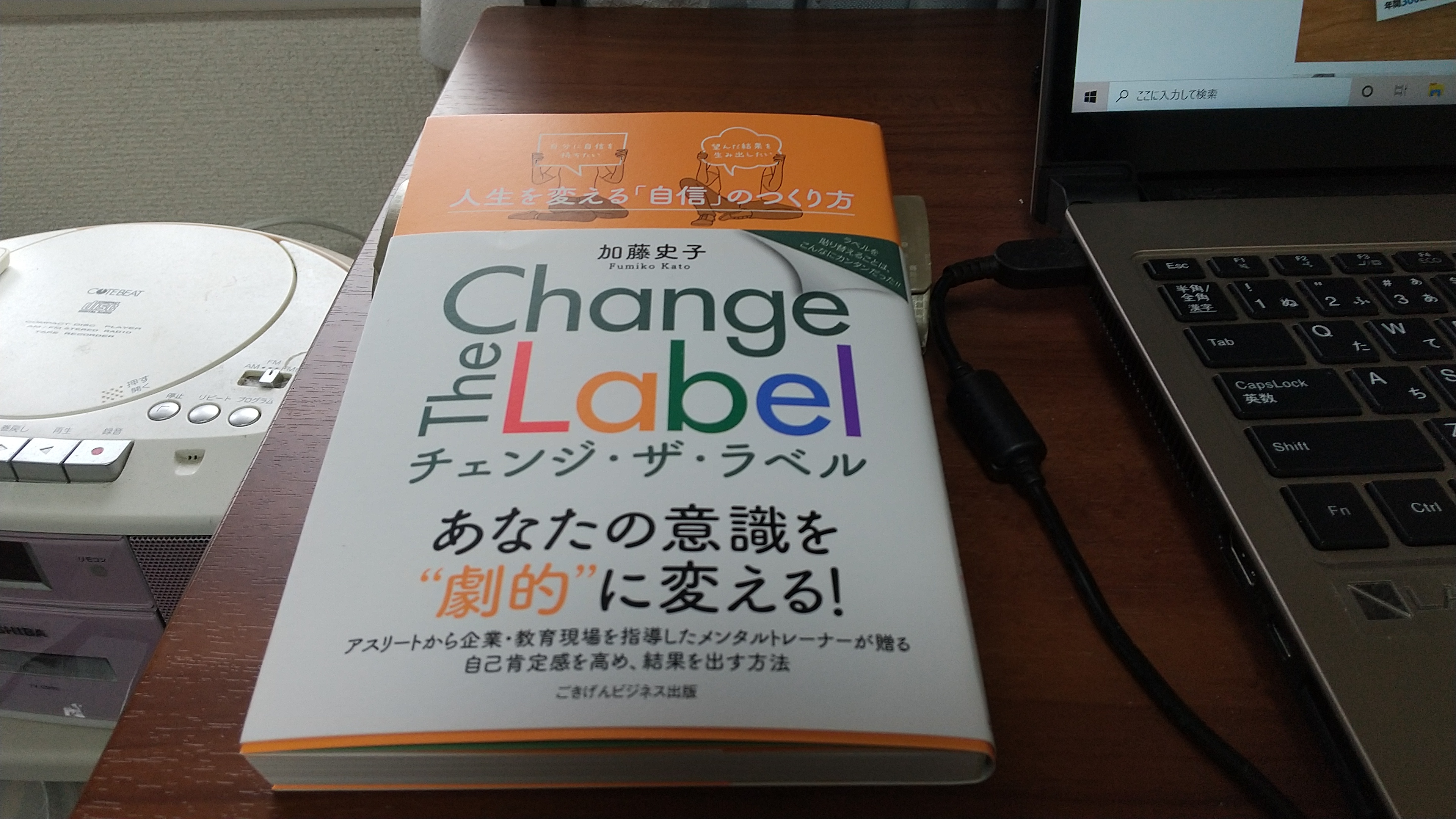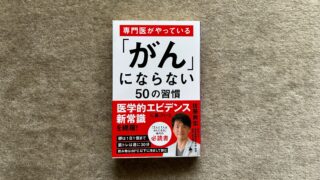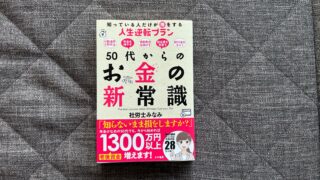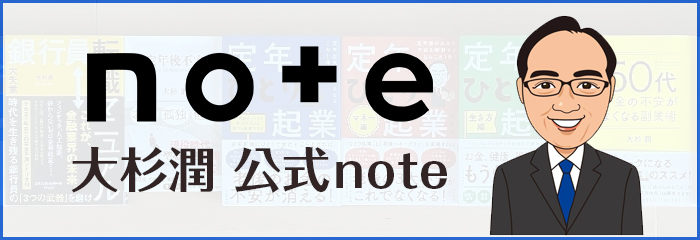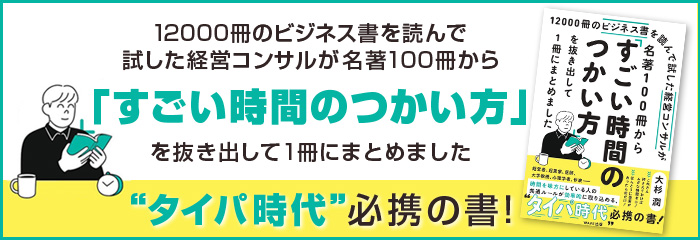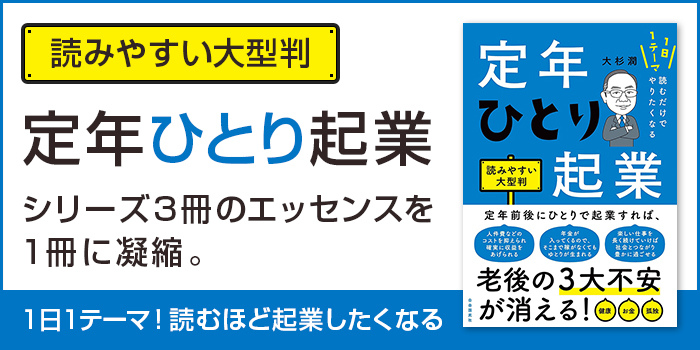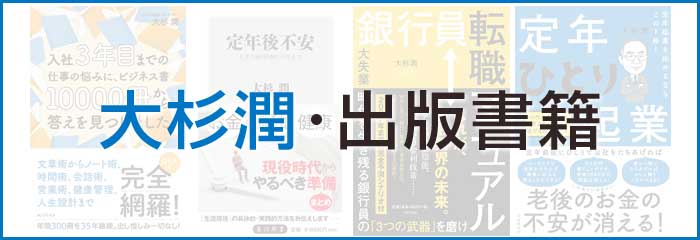『日本経済の死角ー収奪的システムを解き明かす』
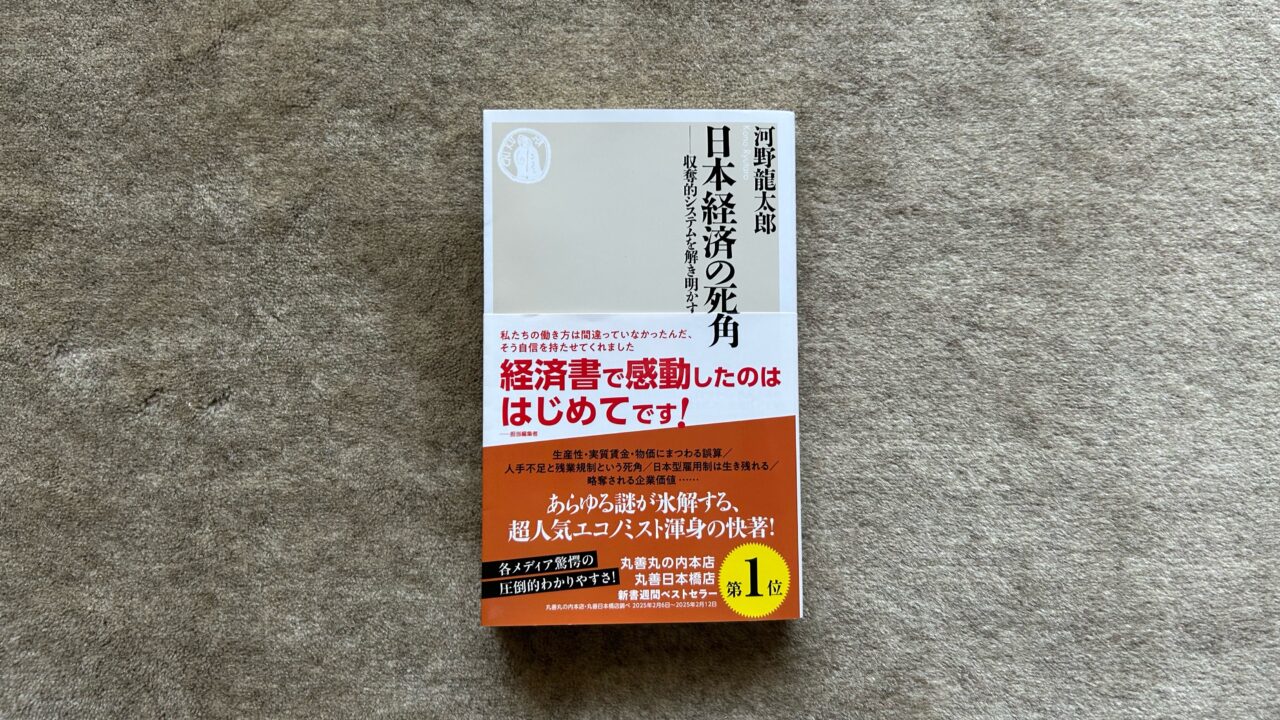
「なぜ日本経済はここまで“分配のない成長”に陥ったのか?」――その本質を、制度の構造から解き明かす渾身の経済書があります。
本日紹介するのは、1964年生まれ、横浜国立大学経済学部卒業後、住友銀行を経て第一生命経済研究所、そしてBNPパリバ証券のチーフエコノミストを務め、現在は東京大学先端科学技術研究センター客員教授としても活躍する経済学者の河野龍太郎さんのこちらの書籍です。
河野龍太郎『日本経済の死角ー収奪的システムを解き明かす』(ちくま新書)
この本は、長期にわたる日本経済の停滞と実質賃金の伸び悩みの根底にある「制度の歪み」を、雇用慣行・労働法制・企業統治・金融政策・イノベーションなどの視点から総合的に分析し、日本が無自覚に陥った “収奪的システム” の全貌を明らかにする意欲作です。
本書の冒頭では、「実質賃金が上がらないのは、生産性の低さではなく、制度的な分配構造の問題だ」という視点が提示され、アベノミクスや新しい資本主義の限界を踏まえつつ、日本が “分け前のない成長” に至った背景を制度論的に解明していきます。
本書は以下の7部構成から成っています。
1.生産性が上がっても実質賃金が上がらない理由
2.定期昇給の下での実質ゼロベアの罠
3.対外直接投資の落とし穴
4.労働市場の構造変化と日銀の二つの誤算
5.労働法制変更のマクロ経済への衝撃
6.コーポレートガバナンス改革の陥穽と長期雇用制の行方
7.イノベーションを社会はどう飼いならすか
本書の前半では、「賃金と成長の不均衡の根本原因」について、以下の視点が整理されています。
◆ 日本は既に“収奪的システム”に入っていると考えるべき段階にある
◆ 労働者への分配が軽視された成長政策が“実質ゼロベア”を固定化している
◆ 定期昇給制度が“実質賃金のフラット化”を促進している
◆ 日本型コーポレートガバナンス改革は、かえって非正規雇用の増加と格差を生んだ
◆ 「異次元緩和」は家計を犠牲にし、企業だけを潤した政策となった
この本の中盤では、「日本企業の投資行動・グローバル戦略の誤算」や、「働き方改革による成長率の鈍化」が精緻に検討されます。主なポイントは以下の通りです。
◆ 海外直接投資は利益を上げているが、国内には波及しない
◆ 労働法制変更や残業規制は、実質的な労働供給制約を生んだ
◆ 女性・高齢者の労働参加は限界に達しつつある
◆ ユニットレーバーコストの上昇が中小企業を直撃している
◆ “消費者余剰”の減少が、社会の不満と分断を深めている
本書の後半では、「成長と分配を両立させるにはどうすべきか」について、長期雇用制度・ジョブ型導入・イノベーション政策の見直しを軸にした議論が展開されます。主なポイントは以下の通りです。
◆ 雇用制度は“漸進的改革”が必要であり、欧米型の一括導入は機能しない
◆ ガバナンス改革は“企業価値を高める”どころか、“価値の収奪”を招いている
◆ 野生化したイノベーションは、格差と分断を拡大する危険がある
◆ 包摂的なイノベーションを実現するには“対抗力の再構築”が必要
◆ AI時代の到来に備え、制度の根本的見直しが不可欠である
この本の締めくくりとして著者は、「今こそ日本は“制度の死角”に目を向け、分配構造を再設計しなければ、持続可能な経済成長も民主主義も危うくなる」と警鐘を鳴らしています。
成長の果実が行き渡らず、働いても報われないという“閉塞感”に満ちた現代の日本社会、その本質的原因を構造的に掘り下げ、私たちの“気づき”を促してくれる本書は、まさに “現代日本を読み解く羅針盤” といえるでしょう。
あなたも本書を手に取り、“収奪から共創へ”という経済のビジョンを、今一度自らの目で確かめてみませんか?
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3778日目】