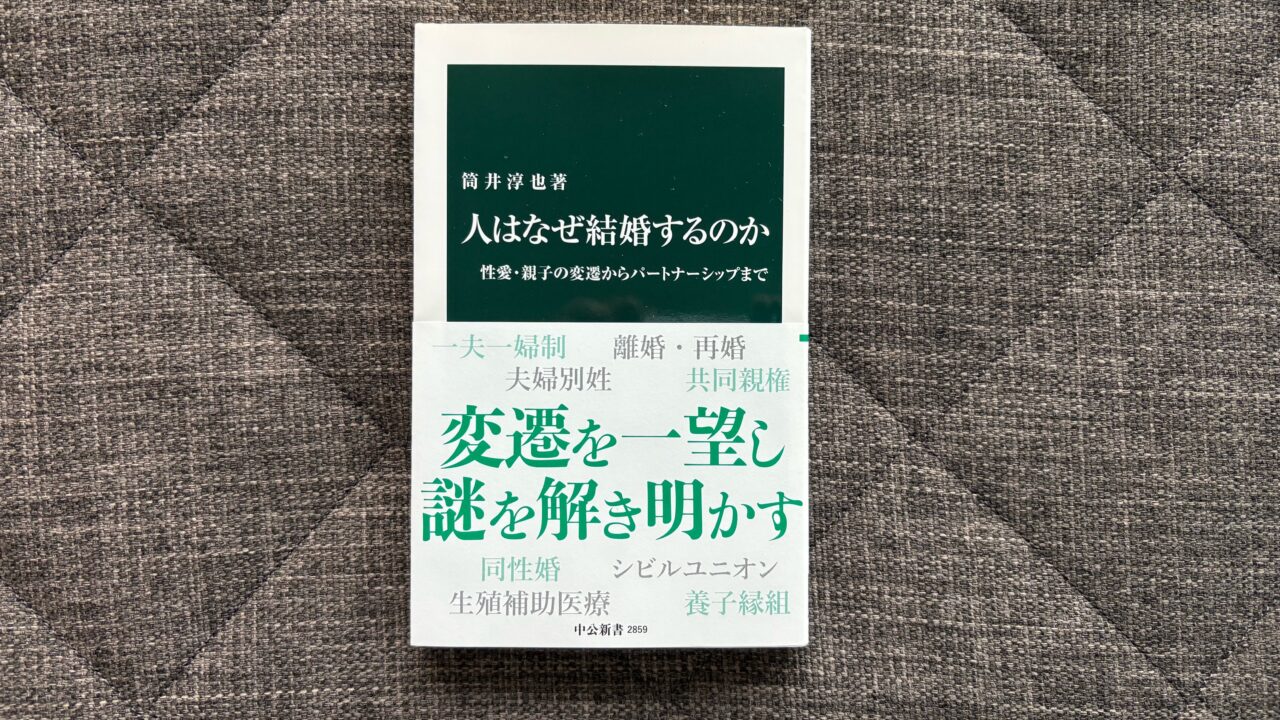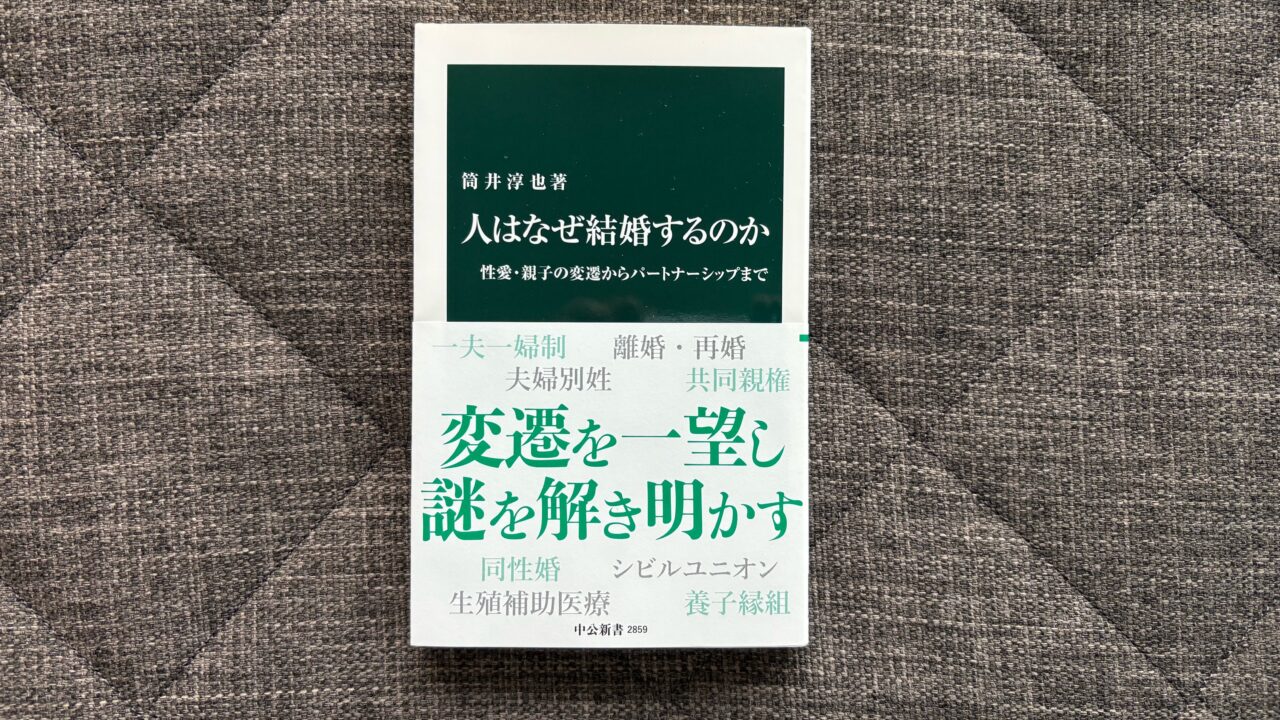本書の前半では、「結婚のない社会?」および「結婚はどう変わってきたのか」とについて、大胆な問いからスタートし、結婚の歴史的・文化的な意味と変遷をたどります。主なポイントは以下の通り。
◆ 結婚は「生殖・財産・共同生活」を結ぶ社会制度として誕生した
◆ 母系社会では父親の位置づけが曖昧で、結婚観も流動的だった
◆ 家族制度は「家」や「仕事」の枠組みと密接に結びついていた
◆ 近代化により“愛”が結婚の主軸となり、経済的結びつきが弱まった
◆ 結婚の自由化が進むほど、個人の“しんどさ”も増している
この本の中盤では、「結婚の法からみえる結婚の遷り変わり」「同性婚、パートナーシップ、事実婚」および「結婚と親子関係」について、法的側面から現代の結婚を検証しています。主なポイントは次の通りです。
◆ 国や支配者が結婚制度に介入してきたのは、秩序維持と人口管理のため
◆ 自由婚は「自由」なようで、社会制度や慣習に縛られている
◆ 同性婚・シビルユニオンは“結婚の定義”そのものを問い直す契機
◆ 結婚による法的メリット(相続・税制・扶養)は依然として大きい
◆ 制度と現実のギャップを埋める議論が、今後の日本社会に不可欠
本書の後半では、「乗りこえられるべき課題としての結婚」および「残された論点」について、結婚と家族をめぐる最前線の課題を掘り下げます。主なポイントは以下の通りです。
◆ 結婚制度の根幹には「親子関係の安定化」がある
◆ DNA鑑定や代理出産が“父性と母性”の定義を揺るがしている
◆ 養子縁組や同性カップルの育児など、多様な家族形態が出現
◆ 結婚を「義務」ではなく「選択肢」として捉える時代へ
◆ 自由と平等が進むほど、“倫理”と“責任”の問いが重くなる
この本は、単に “結婚するかしないか” の選択を超え、「人と人がどう関わり合い、支え合う社会を築くか」という本質的なテーマに迫っています。
結婚をめぐる議論に息苦しさを感じている人や、リベラルと保守の対立を超えて本質を考えたい人にとって、まさに “現代を生きるための社会学的羅針盤” といえるでしょう。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3880日目】