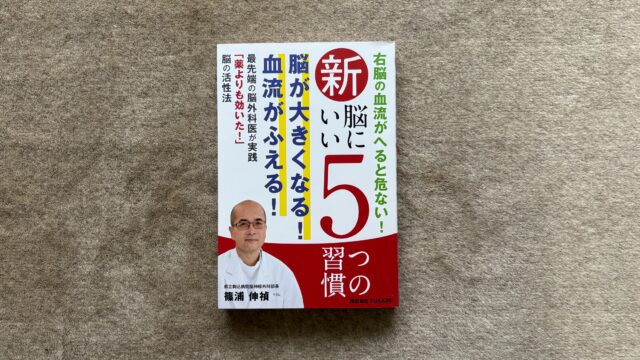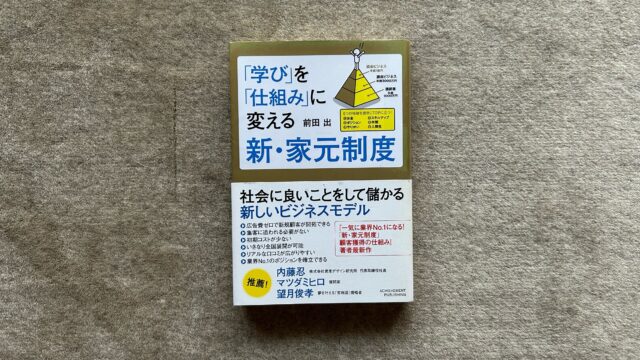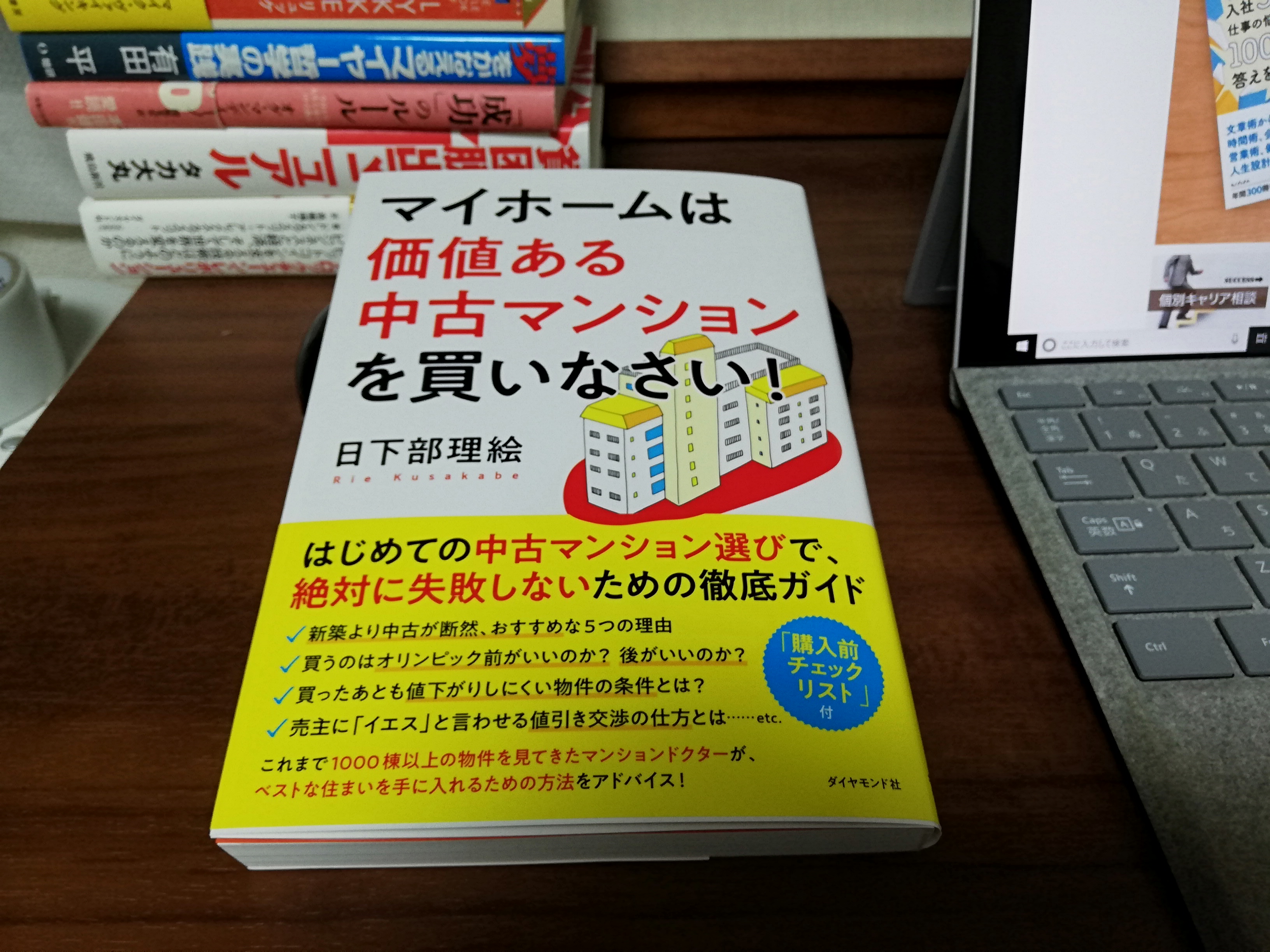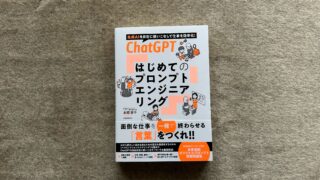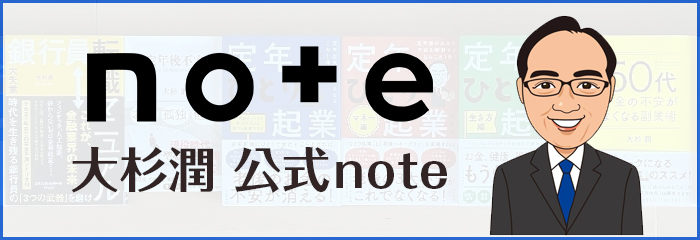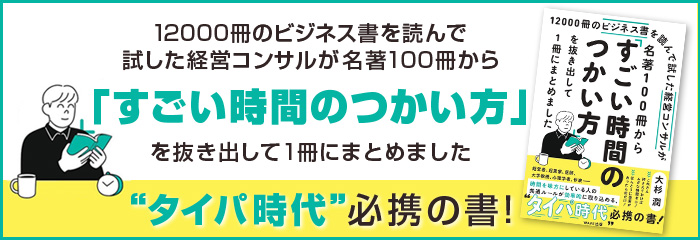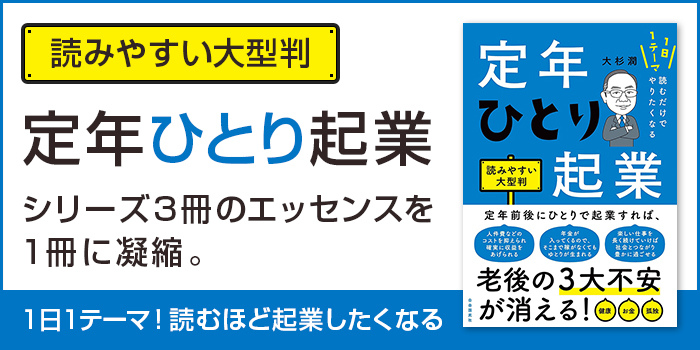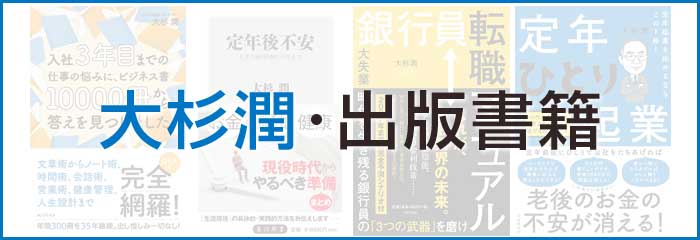『難病の子のために親ができること』
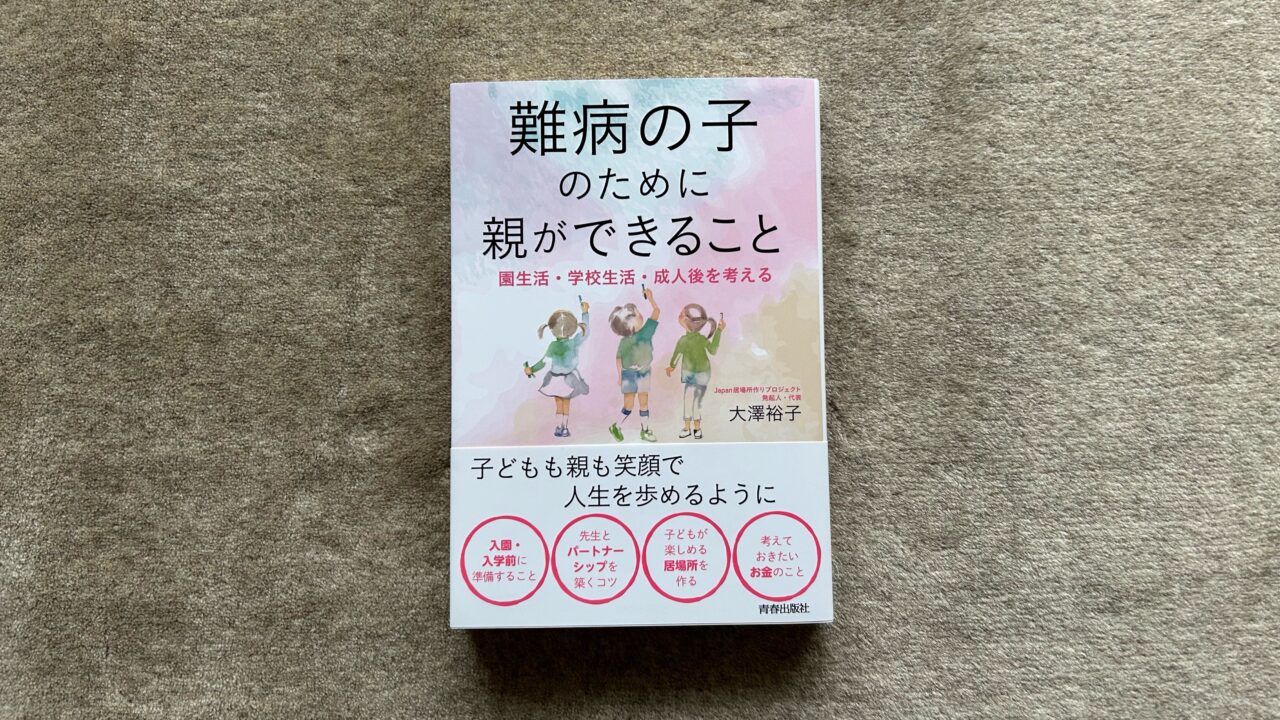
「子どもが難病と診断されたとき、親はどう向き合えばよいのか。」「医療的ケアが必要な子どもとの日常を、どう乗り越えていくのか。」そんな問いに対し、15年間の実体験をもとに答えてくれる本があります。
本日紹介するのは、東北福祉大学総合福祉学部社会教育学科卒業、社会福祉主事と児童福祉司の任用資格を保有、Japan居場所作りプロジェクト発起人・代表で2児の母である大澤裕子さんが、難病の子どもを育てる中で得た知見やノウハウをまとめた、こちらの書籍です。
大澤裕子『難病の子のために親ができること』(青春出版社)
この本は、妊娠中に子どもの重度の心疾患が判明し、15年間にわたって医療的ケアが必要な子どもを育ててきた著者が、その経験から得た知識や心構えをQ&A形式でわかりやすく解説した一冊です。
本書は以下の7部構成から成っています。
1.赤ちゃんが病気とわかったら
2.闘病中でも、子どもが子どもらしく過ごすために
3.園生活、学校選び、先生と・・・どう向き合っていく?
4.親も子も安心できる、勉強環境の整え方
5.子どもが自分らしくいられる、ホッとできるつながりとは
6.「学校に行きたくない」に、親がしてあげられること
7.高校生活から成人後をどうサポートしていくか
この本の冒頭で著者は、「経験してきたことが、今悩んでいる誰かの力になれたら──」という想いで本書を執筆したと述べています。
本書の前半では、「赤ちゃんが病気とわかったときの受け止め方」や「子どもが子どもらしく生きるための環境づくり」について、以下のポイントで丁寧に語られています。
◆ 病名を聞いたときに親が抱える葛藤とその整理の仕方
◆ 医師との信頼関係の築き方と情報収集の姿勢
◆ 子どもに“特別感”を持たせすぎない育て方
◆ 「できること」を見つけて伸ばしていく視点
◆ 病院でも“遊び”の時間を大切にする工夫
この本の中盤では、「園や学校との関わり方」「学びの支援環境の整え方」「社会とのつながり」について、現場での経験を交えながら以下のような実践的なヒントが紹介されています。
◆ 入園・入学前に学校側と話し合うべきポイント
◆ 学校の先生とのコミュニケーション法
◆ 体調に波がある子のための勉強環境とスケジューリング
◆ 家庭学習を無理なく続けるためのツール
◆ 他の親や支援者との“ゆるいつながり”を持つことの安心感
本書の後半では、「不登校への対応」「進学や成人後の支援」について、将来を見据えた準備の仕方が綴られています。
◆ 子どもが「学校に行きたくない」と言ったときの親の心構え
◆ 出席日数・評価への影響と制度の活用法
◆ 高校・大学・専門学校への進学に必要な準備
◆ 親亡き後の自立をどう描くか
◆「支援してもらう」から「選んでいく」への転換
この本の締めくくりで著者は、「親も迷いながらでいい。完璧じゃなくても、少しずつ一緒に前に進めばいい」と伝えています。
あなたも本書を読んで、難病の子とその家族がより穏やかで希望ある毎日を過ごすための道しるべを手にしてみませんか?
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3724日目】