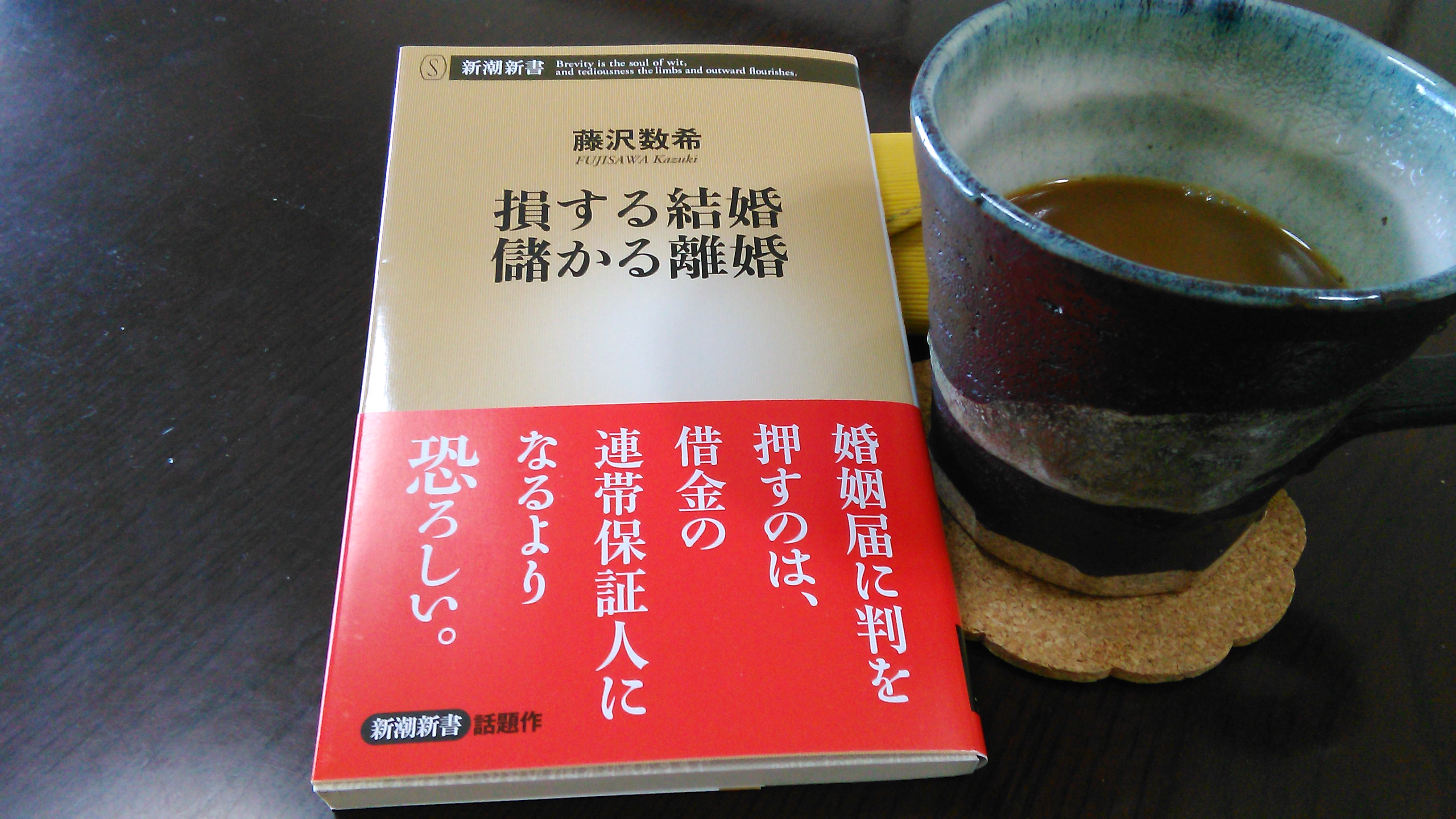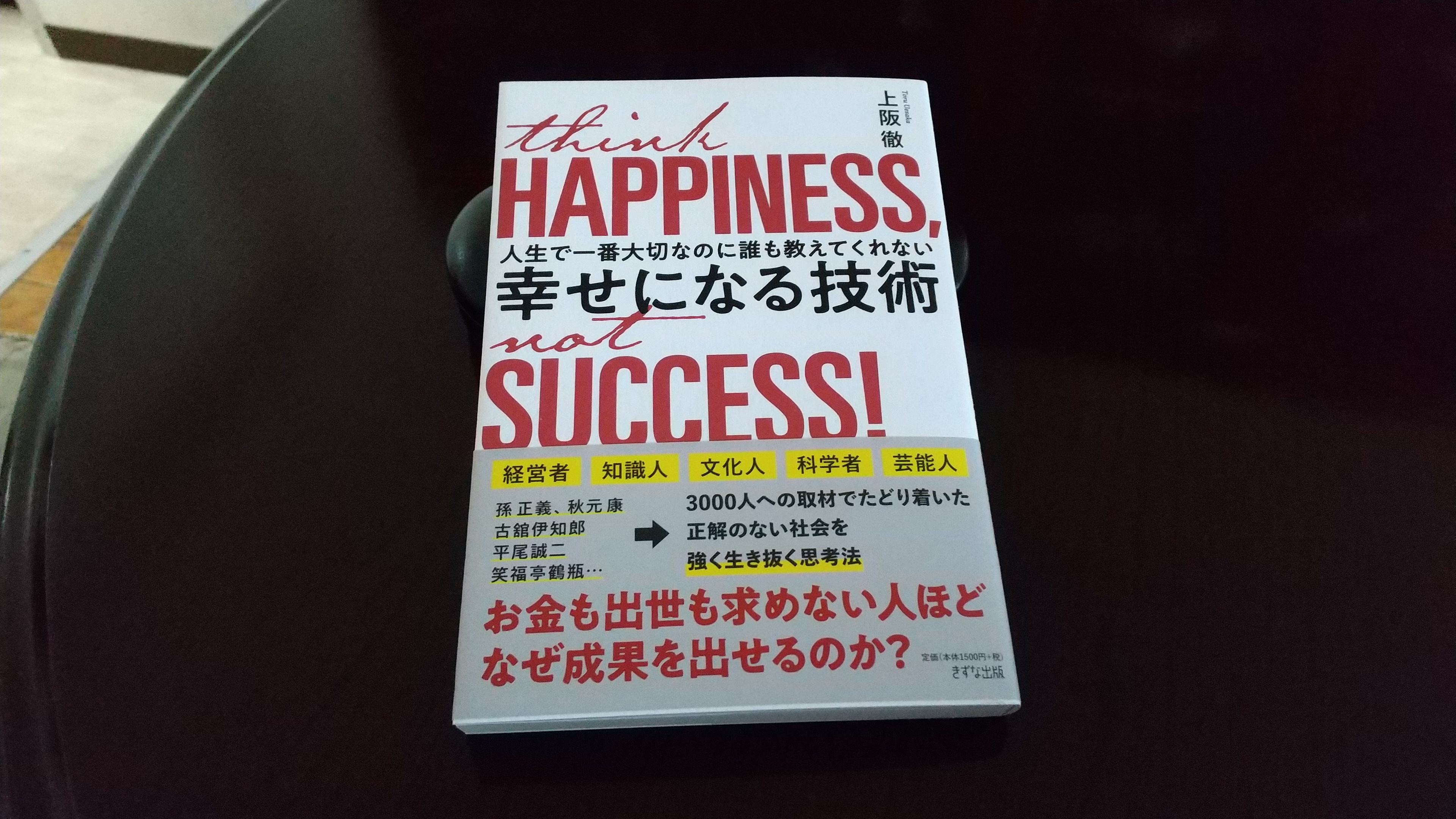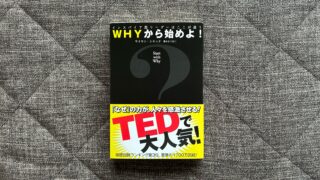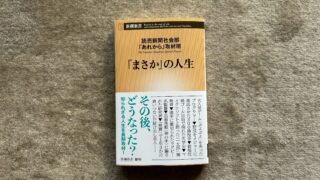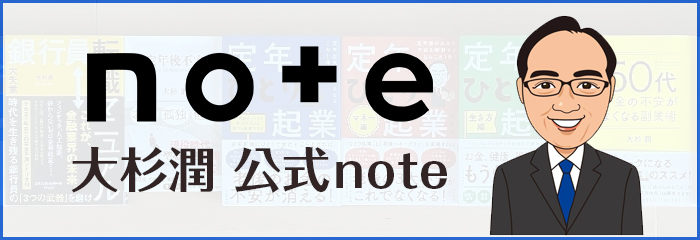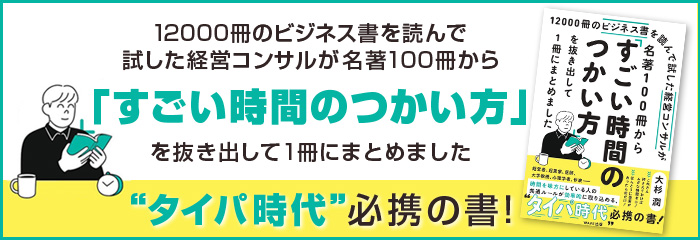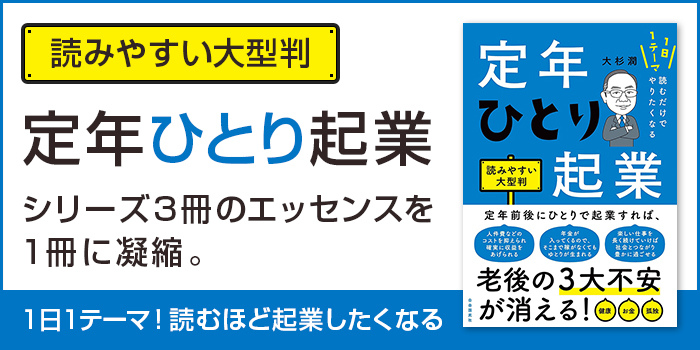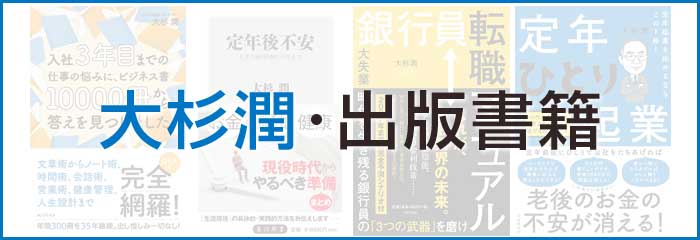『忙しい人のための美術館の歩き方』
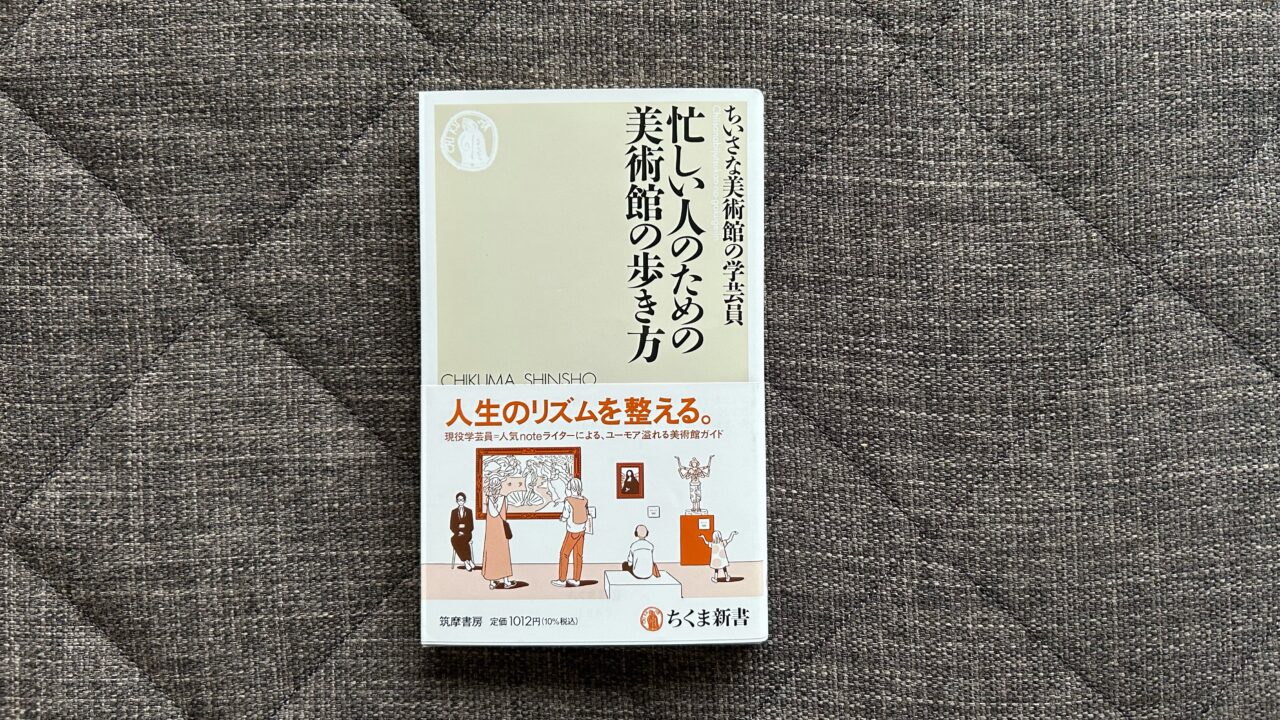
「美術館に行く意味って何ですか?」――その問いに真っ向から応えた、美術鑑賞の本質に迫る一冊があります。
本日紹介するのは、東京都生まれ、都内のとある美術館で働く現役学芸員で、複数の大学でも教鞭を執る「ちいさな美術館の学芸員」さんによるこちらの書籍です。
ちいさな美術館の学芸員『忙しい人のための美術館の歩き方』(ちくま新書)
この本は、美術館に「行きたいけど行けていない」あなたに、美術鑑賞という“至福の余白時間”を取り戻してもらうための実用的ガイドです。
この本の冒頭で著者は、「忙しいあなたにこそ、美術館で過ごす“至福の余白”が必要なのです」と語りかけ、美術館を訪れることの意味を私たちの生活に引き寄せて紹介します。
本書は以下の5部構成から成っています。
1.タイパの真逆にある美術館
2.美術鑑賞の変遷
3.美術館の新たな取り組み
4.SNS時代の美術館 鑑賞する側が主役になる
5.結局、美術館に行く意味って何?
本書の前半では、現代の忙しさに支配されたライフスタイルの中で、美術館がどれほど豊かな時間をもたらしてくれるかが語られます。主なポイントは以下の通りです。
◆ コスパ・タイパ志向の現代に逆行する“美術館の価値”
◆ 「美術=教養」とされる背景とその是非
◆ 余裕のある時代にこそ美術が求められる
◆ 忙しい人ほど必要な“鑑賞の余白”
◆ 美術館に通う人の習慣と意識の違い
本書の中盤では、美術鑑賞の歴史的な変遷と、美術館が時代とともに進化してきた軌跡が描かれます。主なポイントは次の通りです。
◆ 高度経済成長期から現代に至る美術展のヒット傾向
◆ 展覧会制度が日本に根付いた経緯
◆ SNSやデジタル化が変える鑑賞スタイル
◆ 没入型体験やオンライン鑑賞の功罪
◆ 美術館の資金難とクラウドファンディング活用の実情
本書の後半では、現代人が美術館を訪れる意義や、鑑賞体験をより深くするための実践的なノウハウが紹介されます。主なポイントは以下の通りです。
◆ 美術鑑賞とマインドフルネスの親和性
◆ スマホを置いて、余白時間に向き合う意味
◆ 鑑賞メモやアウトプットの効用
◆ 「美術を語れる人」になるためのトレーニング
◆ 美術館を“フォースプレイス”とする可能性
この本の締めくくりとして著者は、「今度の週末、美術館に行こうと決めたあなたへ」とエールを送りながら、美術館を訪れることで得られる“気づき”と“感性のリズム”を整える効用を優しく説いています。
読み終えたとき、肩の力が抜けると同時に、「今度の週末は、美術館に行ってみようかな」と心が動かされる、そんな一冊です。アートに詳しくなくても、美術館が少し遠く感じていた人にもぴったりの読書体験になるでしょう。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3792日目】