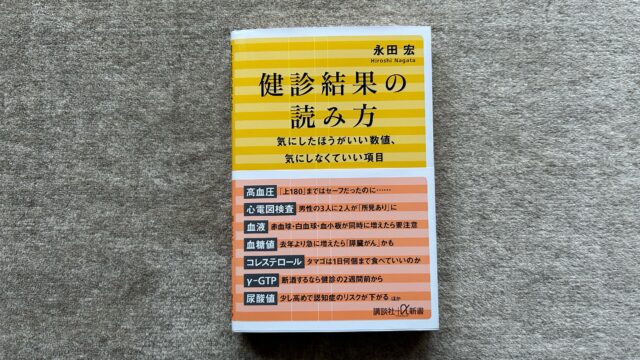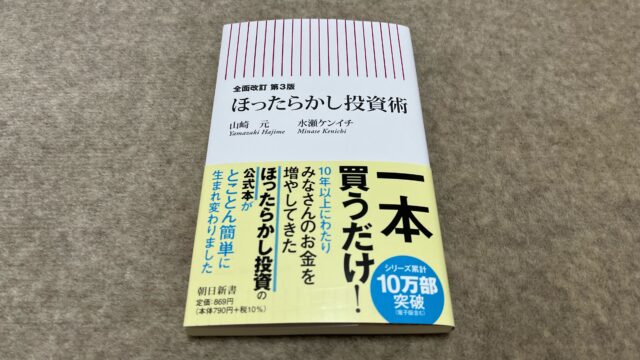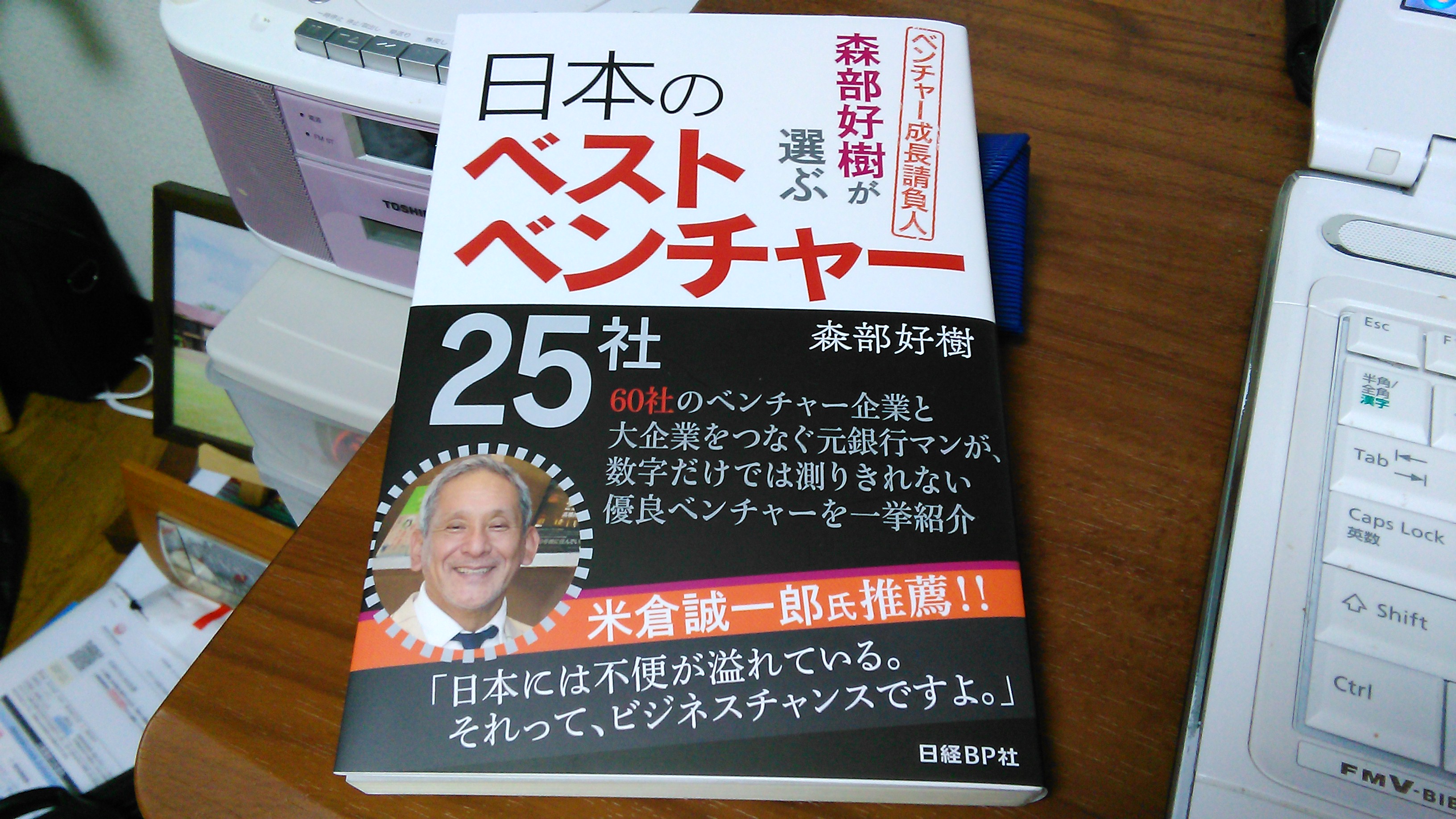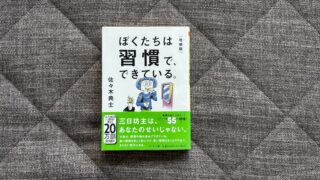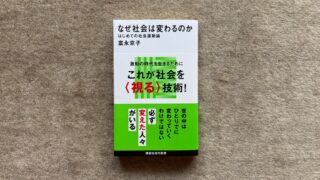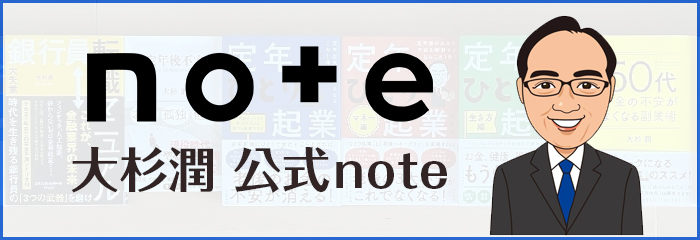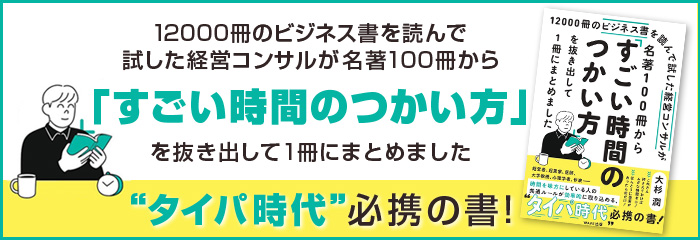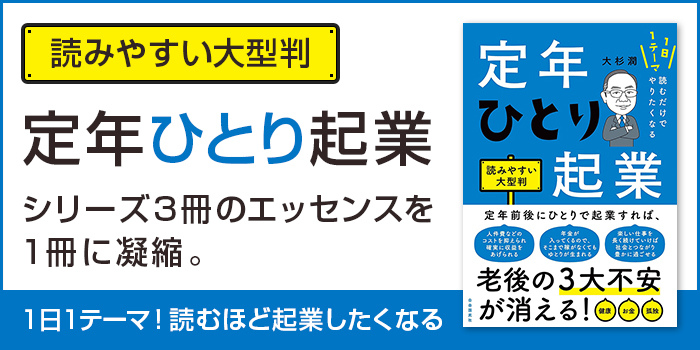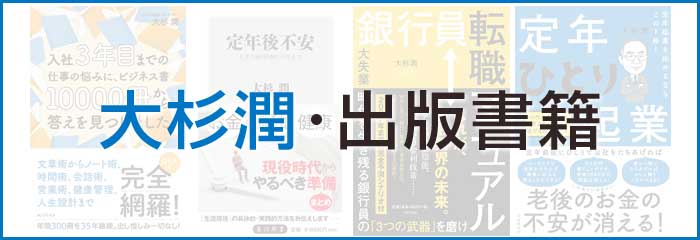『知能とは何か ヒトとAIのあいだ』
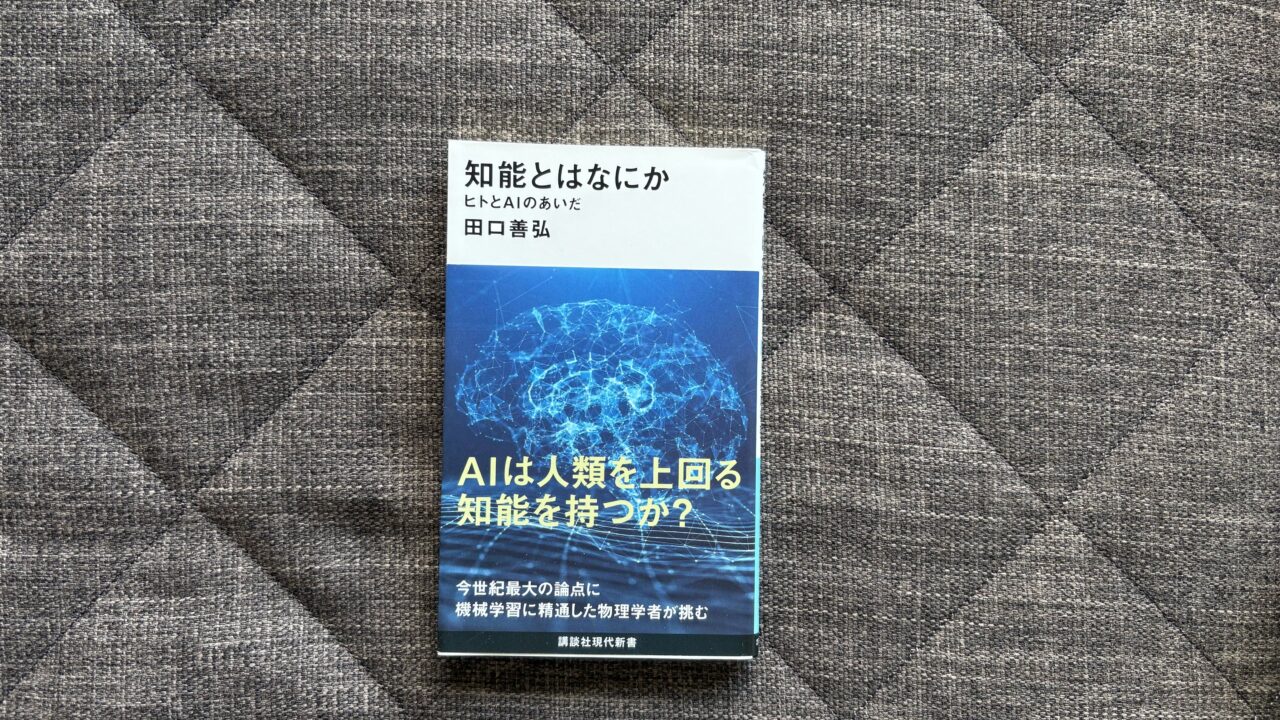
「AIは人類を上回る知能を持つのか?」――そんな今世紀最大の論点に、機械学習に精通した物理学者が挑んだ一冊があります。
本日紹介するのは、1961年東京都生まれ、1995年に執筆した『砂時計の七不思議―粉粒体の動力学』(中公新書)で第12回講談社科学出版賞を受賞、機械学習を応用したバイオインフォマティクス研究に取り組み、スタンフォード大学とエルゼビア社による「世界で最も影響力のある研究者トップ2%」に2021年度から2023年度まで4年連続選出(分野はバイオインフォマティクス)、近年はテンソル分解研究に注力している、中央大学理工学部教授の田口善弘(たぐち・よしひろ)さんが書いたこちらの書籍です。
田口善弘『知能とは何か ヒトとAIのあいだ』(講談社現代新書)
本書は、生成AIをめぐる混沌とした状況を物理学者の視点で鮮やかに読み解き、人工知能と人間の知能の本質的な違いを整理したうえで、「シンギュラリティは起きるのか」という命題に挑みます。著者は、少なくとも現在の生成AIの延長線上には、人類に匹敵する自我や意識を持つAIは誕生しないと明言します。その理由は、「知能」という言葉にひとくくりにされがちな概念の中に、実際には本質的に異なる性質が混在しているからです。
本書は以下の10部構成から成っています。
0.生成AI狂騒曲
1.過去の知能研究
2.深層学習から生成AIへ
3.脳の機能としての「知能」
4.ニューロンの集合体としての脳
5.世界のシミュレーターとしての生成AI
6.なぜ人間の脳は少ないサンプルで学習できるのか?
7.古典力学はまがい物?
8.知能研究の今後
9.非線形系非平衡多自由度系と生成AI
この本の冒頭で著者は、「私たちは『知能とは何か』という問いにすら、まだ満足に答えられていない」と指摘します。だからこそ、AIと人間の知能を同列に語る前に、それぞれの成り立ちと特性を精緻に理解する必要があると述べます。
本書の前半では、「生成AI狂騒曲」「過去の知能研究」「深層学習から生成AIへ」および「脳の機能としての『知能』」について、以下のポイントを説明しています。
◆ 生成AIは汎用性を持ち、学習の範囲を人間が制御できなくなるリスクがある
◆ 知能研究の歴史を振り返ると、人間中心的な視点と限界が浮き彫りになる
◆ 深層学習の発展が生成AIのブレイクスルーをもたらした
◆ 脳の「知能」は単なる計算能力ではなく、身体性や感覚と不可分な働きである
◆ AIと人間の知能は構造的に異なり、その違いが未来予測の鍵となる
この本の中盤では、「ニューロンの集合体としての脳」「世界のシミュレーターとしての生成AI」「なぜ人間の脳は少ないサンプルで学習できるのか?」および「古典力学はまがい物?」について考察しています。主なポイントは次の通り。
◆ 脳は無数のニューロンが相互作用する高度なネットワークである
◆ 生成AIは膨大なデータを元に世界のシミュレーションを行うが、人間の直感的理解とは異質である
◆ 人間の脳は少ない経験から一般化できる効率的な学習メカニズムを備えている
◆ 古典力学の成立や限界は、知能理解にも示唆を与える
◆ 脳とAIの比較は、物理法則や情報処理の根本的な違いを明らかにする
本書の後半では、「知能研究の今後」および「非線形系非平衡多自由度系と生成AI」について論じています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 知能研究は分野横断的アプローチが不可欠である
◆ AIの進化は計算資源やアルゴリズムの改良に依存している
◆ 非線形系や多自由度系の理解が、次世代AIの鍵を握る
◆ 自己フィードバックによるAIの知能爆発は現実的ではないと考えられる
◆ 人間とAIの知能は相互補完的に共存する未来像が現実的である
この本の締めくくりとして著者は、「AIを過大評価も過小評価もせず、正しく理解することが、未来のテクノロジーとの付き合い方を決める」と述べています。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3814日目】