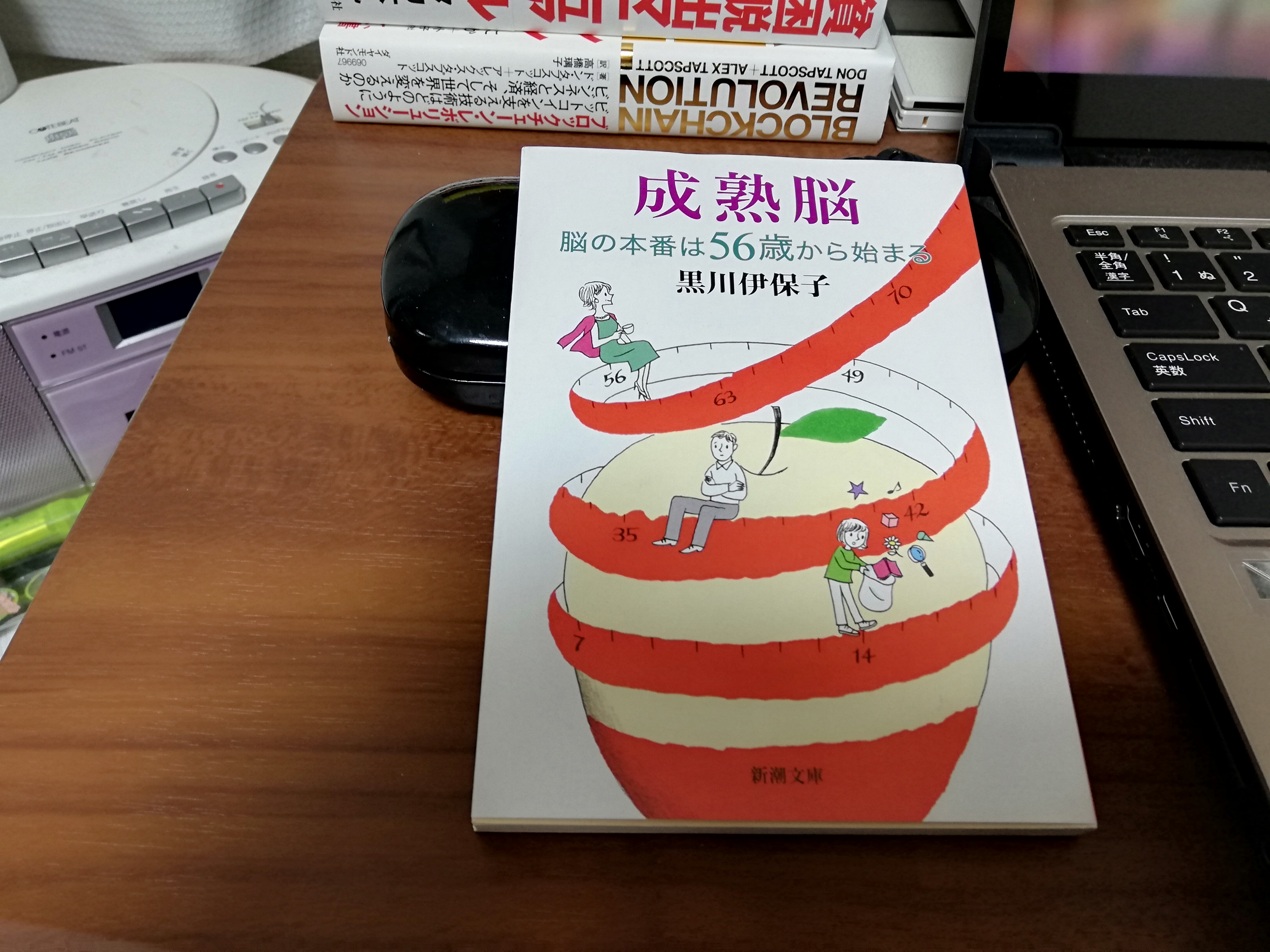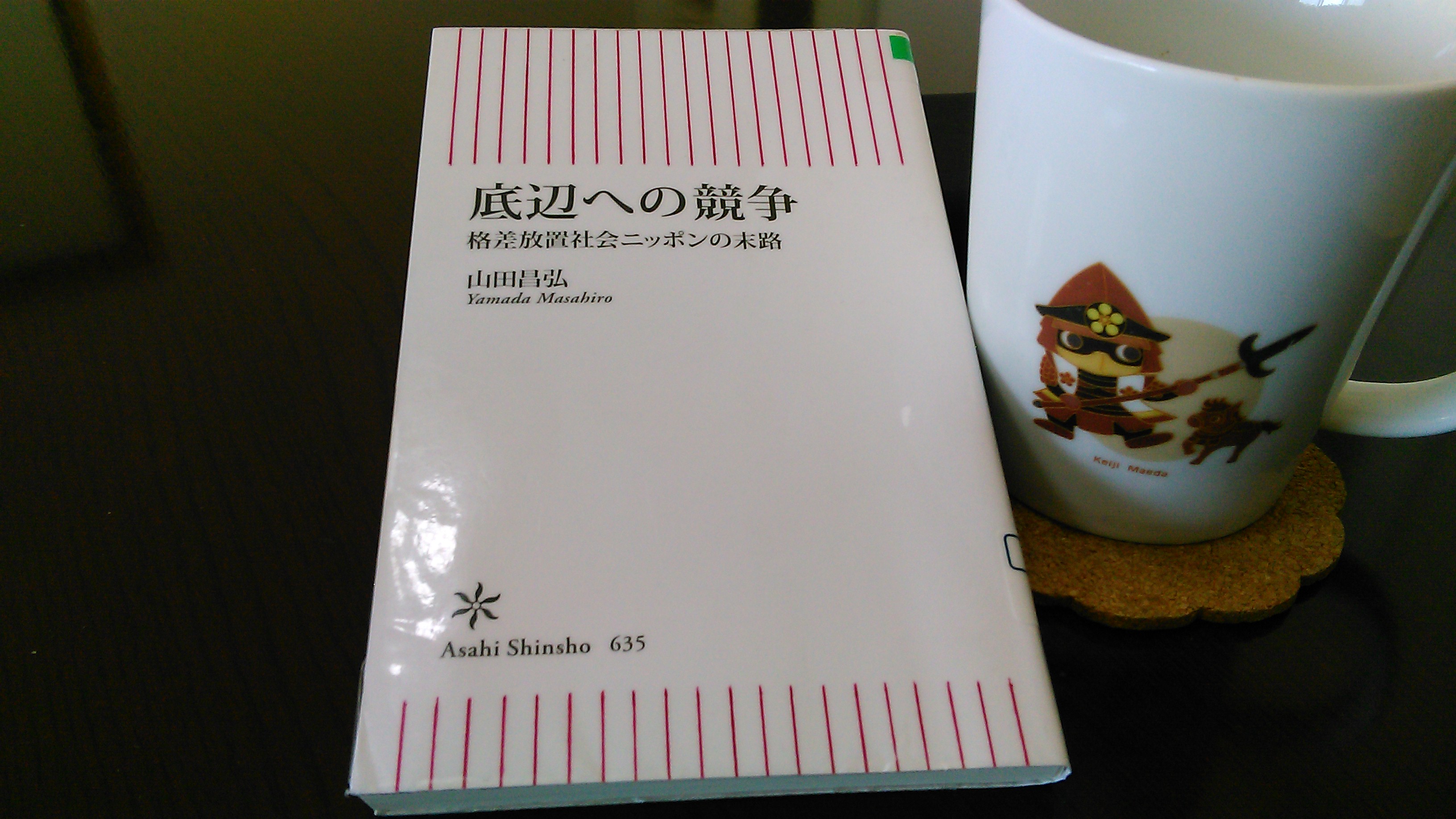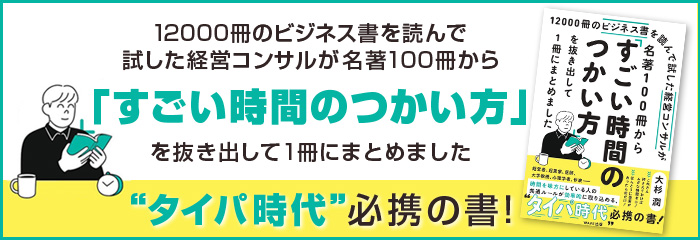『格差大国アメリカを追う日本のゆくえ』

景気回復が進んでいると言われているアメリカで、「格差拡大」が限界に達しつつあるという見方が台頭しています。アベノミクスでインフレ目標を掲げる日本がその後を追っていると警鐘を鳴らす経済アナリストがいます。
歴史、哲学、自然科学などより広い視点から経済予測を的中させている中原圭介さんのこちらの本を今日は紹介します。
中原圭介『格差大国アメリカを追う日本のゆくえ』(朝日新聞出版)
この本は、経済成長を続けるアメリカ社会における「中間層の没落」に焦点を当て、「貧富の格差」が許容限度を超えるまで拡大していることに大きな疑問を投げかけています。
そして、アベノミクスによりデフレ脱却と規制緩和・自由競争の大義により、日本もアメリカの後を追って「中間層没落」の道へ突き進むことに対して警鐘を鳴らしています。
本書の構成は以下の6部から成っています。
1.中間層が没落するアメリカ
2.格差はなぜ拡大したのか
3.経済学は何のためにあるのか
4.中間層と国家の盛衰
5.21世紀のインフレ政策は間違っている
6.世界の規範となる日本
本章の冒頭で著者は、2014年11月1日付週刊『東洋経済』の特集「分裂する大国アメリカ」を採り上げて紹介しています。
この特集の中で、所得、教育、医療などの分野で二極化が進むアメリカの実態がレポートされています。ニューヨークのマンハッタンでは9000万ドル(=108億円)以上の超高級高層マンションがキャッシュによる購入で完売する一方、そこからさほど遠くないブロンクスでは平均年収1万3000ドル(=156万円)ほどの貧困層がひしめいています。
上位5%とそれ以外の格差の拡大は今や、アメリカ社会の人々にとって許容限度を超える事態にまでなっているのではないかと著者は考察しています。
フランスの経済学者ピケティが書いた『21世紀の資本』の英語翻訳版がアメリカで出版されるやいなや、たちましベストセラーとなった現象はまさに没落する中間層の支持を受けたものと言えます。
ピケティの『21世紀の資本』は、資本主義は放置しておくとそのシステム自体に格差を拡大するメカニズムがあるため、所得再分配を行う人為的な政策が必要だとしています。
資産課税や相続税の増税などを世界各国で強調して同時に行うことを提唱しています。アメリカを中心とする新自由主義経済学者たちはこれに反し、できるだけ市場に任せるべきという主張です。
その結果、従業員よりも株主への還元(配当増額や自社株買いによる株式償却)を優先する企業経営になっていて、経営者や株主といった富裕層に富が集中する傾向が強まっています。
とくに著者は、ROE(株主資本利益率)の向上を至上命題として、業績が悪くなっていないうちから減益が予想されるだけで、従業員の首切りを断行して不採算部門から撤退し、自社株買いにより株価を上げることのみに注力する大企業経営者の経営姿勢に疑問を呈しています。
本書の最後で著者は、「日本の失われた20年」はほんとうに失われた期間だったのか、という問題意識を投げかけています。「デフレ脱却と経済成長率」を犠牲にしながら日本の雇用と平等を守った期間、とも考えられると言います。
アメリカこそ失われた40年ではないか、日本はその後を追うべきではない、というのが中原さんの結論です。矛盾が拡大するアメリカで資本主義を揺るがすような大きなクラッシュが起こるかどうか、その答えは間もなく出る気がしています。
皆さんも本書を参考にぜひ、アメリカ経済や日本のゆくえについて考えてみてほしいと思います。
では、今日もハッピーな1日を!