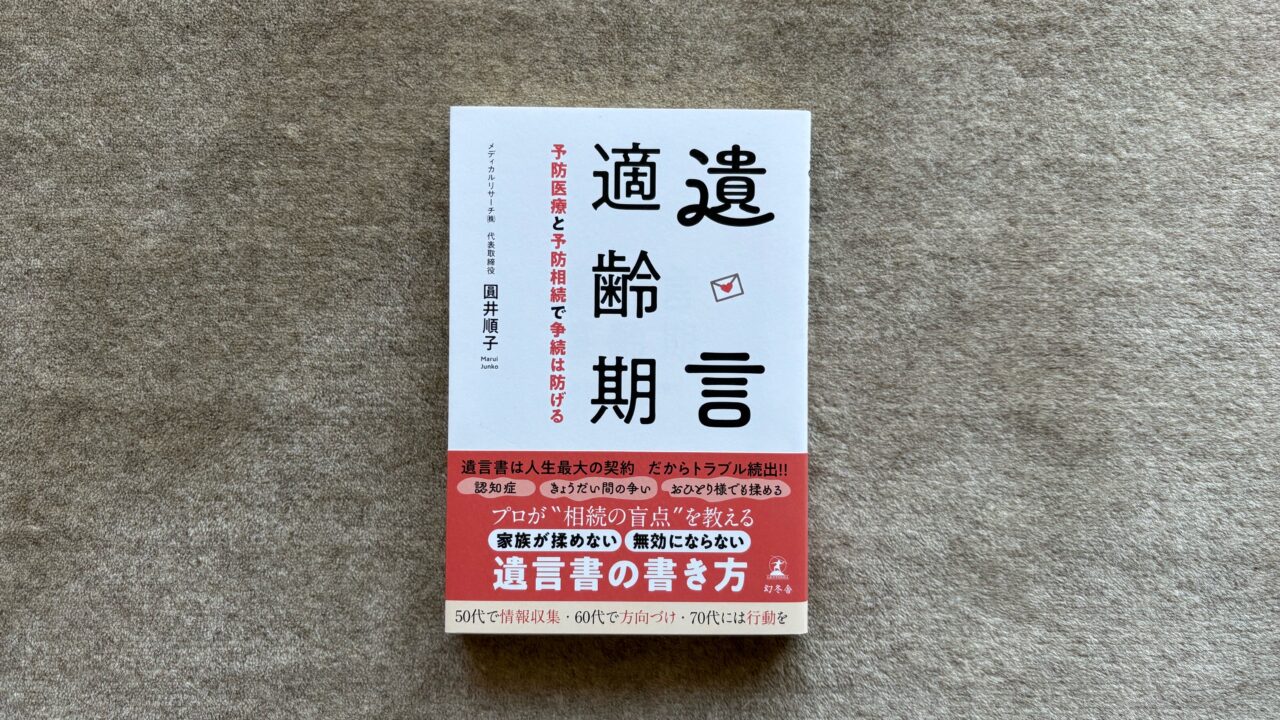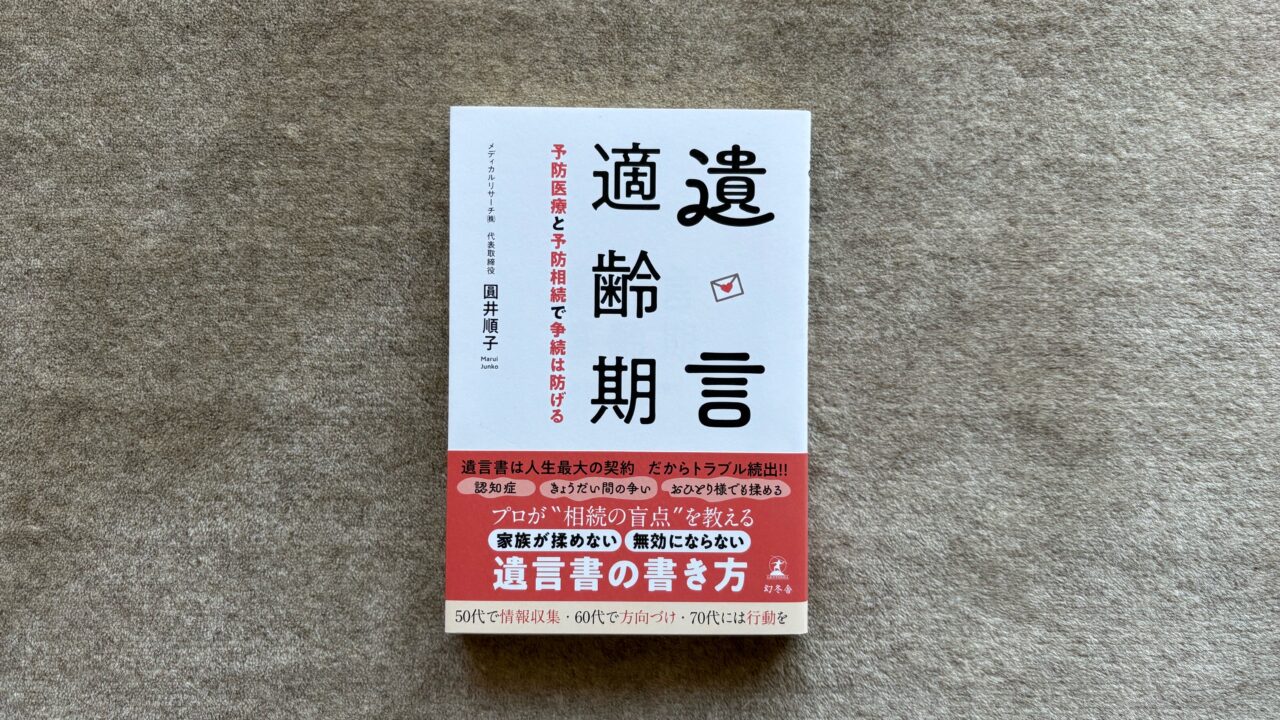「遺言書は、家族への最後のラブレターである」――そんな温かくも核心を突くメッセージから始まり、相続の “争い” を未然に防ぐための実践知を伝える一冊があります。
本日紹介するのは、兵庫県生まれ。短期大学卒業後に一般企業へ就職するも、看護師になる夢を捨てきれず25歳で看護専門学校に入学。看護師免許取得後は、医師と経営者の橋渡し役として病院立ち上げや医療経営に携わり、2016年にメディカルリサーチ株式会社代表取締役に就任。さらに2022年には、認知症予防と未病ケアのためのサプリを展開する株式会社BodyVoiceを設立し、「医療×予防×相続」という新たな視点で高齢社会の課題解決に取り組む圓井順子(まるい・じゅんこ)さんが書いたこちらの書籍です。
圓井順子『遺言書適齢期 予防医療と予防相続で争続は防げる』(幻冬舎)
この本は、「遺言書は死の直前に書くもの」という誤解を解き、心身の健康が保たれているうちに “予防相続” を行うことの重要性を説いた実践書です。
認知症、兄弟間のトラブル、「おひとり様相続」など、現代特有の相続リスクを専門的な立場から解説しながら、医療と法律の両面から「争続(そうぞく)」を防ぐ具体策を紹介しています。
本書は以下の6部構成から成っています。
1.遺言書は家族への最後のラブレター
2.【子ども編】親の相続対策を考える
3.認知症と遺言書
4.人生の棚卸しがうまくできる人は相続で揉めない
5.生活習慣病対策で認知症は遠ざけられる
6.コレカラのこと
本書の前半では、「遺言書は家族への最後のラブレター」および「【子ども編】親の相続対策を考える」について解説しています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 遺言書は “財産分配の書類” ではなく、“想いを伝える手紙” である
◆ 子ども世代が親の相続をタブー視せず、早期に対話することが大切
◆ 「親の意思」を尊重することで、兄弟間の争いは大幅に減る
◆ 遺言書の有効・無効を左右するのは「意思能力」の有無
◆ 公正証書遺言と自筆証書遺言、それぞれの長所と注意点を理解する
この本の中盤では、「認知症と遺言書」および「人生の棚卸しがうまくできる人は相続で揉めない」を中心に、“心の準備と情報整理” の重要性が語られます。主なポイントは次の通りです。
◆ 認知症になると遺言書が「無効」と判断されるリスクが高まる
◆ 加齢による“物忘れ”と“認知症”の違いを家族全員が理解すべき
◆ 「人生の棚卸し」を行うことで、自分の価値観と財産の整理ができる
◆ 「エンディングノート」は未来への“心の遺産”になる
◆ 相続の最大の敵は「準備不足」と「先送り」である
本書の後半では、「生活習慣病対策で認知症は遠ざけられる」および「コレカラのこと」というテーマのもと、医療的な視点からの予防相続と “幸せな最期の迎え方” が示されています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 認知症予防は“体の健康管理”と“心の安定”から始まる
◆ 睡眠・食事・運動の改善が「判断力の維持」に直結する
◆ 相続は“お金の話”ではなく、“人間関係の再構築”である
◆ 「誰に何を託すか」を明確にすることで、家族が救われる
◆ 「予防医療×予防相続」が、これからの人生設計の新常識になる
本書の魅力は、看護師出身の著者ならではの “医療現場のリアル” と、“法的トラブル現場のリアル” の両方を踏まえた実践的なアドバイスにあります。
遺言書というと「終活の最終段階」と思われがちですが、本書は「まだ元気なうちにこそ書く」ことの意味を、医学的根拠をもってわかりやすく解説しています。
家族を守り、自分の想いを残す――。
その第一歩は、健康診断と同じように「遺言書の予防」から始まります。
まさに、“争わない相続時代” を生きるための新しい教科書です。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3897日目】