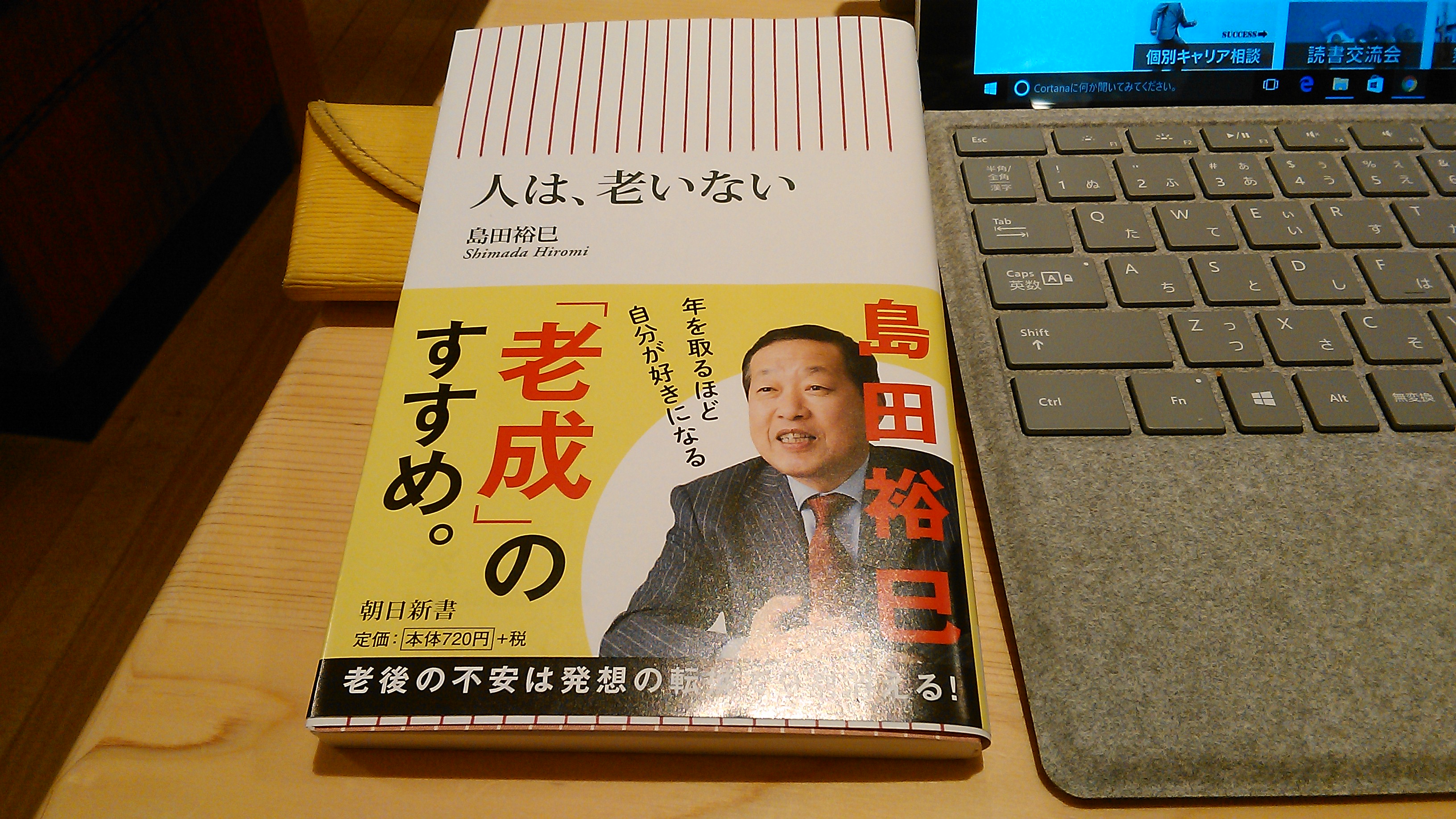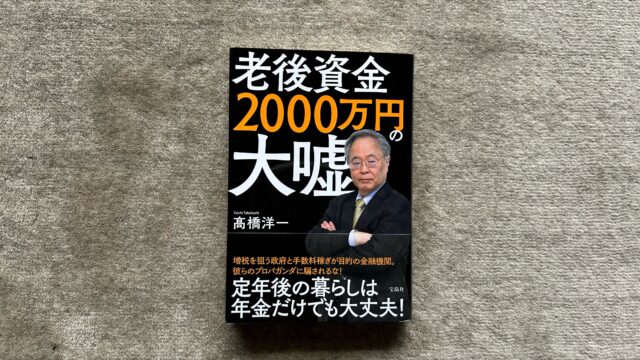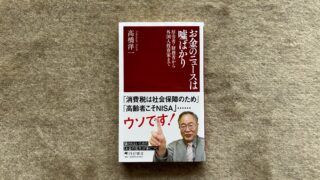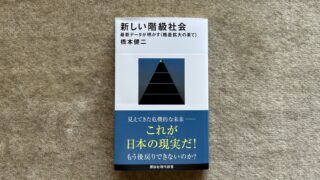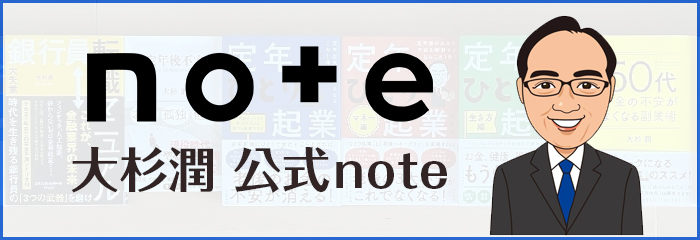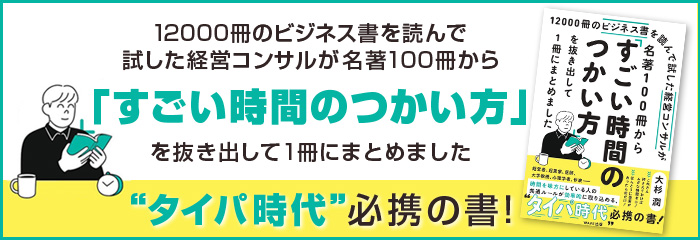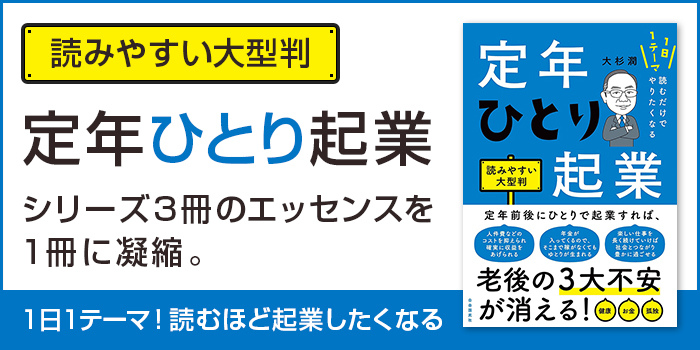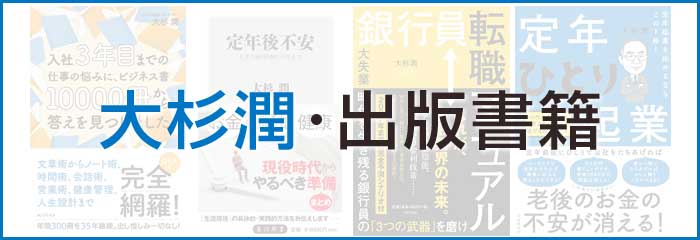『2030―2040年 医療の真実ー下町病院長だから見える医療の末路』
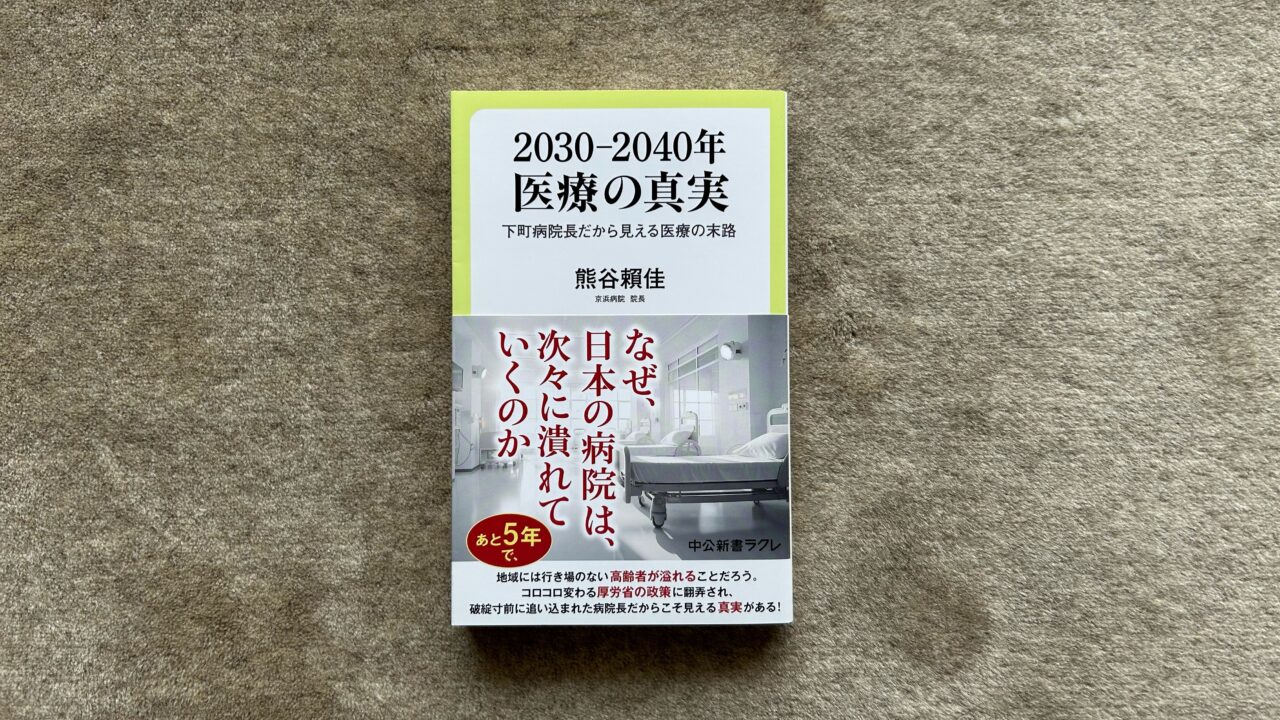
「あと5年で高齢者の行き場がなくなる――」そんな衝撃の未来図から、日本の医療・介護制度の “崩壊” を予見する書籍があります。
本日紹介するのは、1977年慶應義塾大学医学部卒業後、東京大学脳神経外科入局、東京大学の関連病院などで臨床研究に携わったのち、1992年より東京都・下町にある中規模病院の院長を務め、認知症ケアや地域医療において現場からの提言を続けてきた熊谷賴佳さんによるこちらの書籍です。
熊谷賴佳『2030―2040年 医療の真実 ─ 下町病院長だから見える医療の末路』(中公新書ラクレ)
この本は、「地域医療の最前線に立つ中小病院が、どれほどの困難と制度の矛盾に直面しているか」を赤裸々に描き、日本の医療と介護が迎える “危機的未来” を提示する一冊です。
本書は以下の6部構成から成っています。
1.日本の医療・介護崩壊のリアル
2.2040年 医療の地獄絵
3.なぜ日本の病院は次々に潰れるのか
4.医療崩壊に導く5つの罪
5.海外に日本の未来が見える
6.2040年 日本の医療沈没を防ぐ処方箋
本書の前半では、「医療崩壊」の現状と、その背景にある政策の迷走について、次のようなポイントが語られます。
◆ 高齢者医療を担ってきた中小病院が次々に破綻している
◆ 厚労省の政策変更により診療報酬が圧縮され、経営は限界
◆ 自宅に戻れない高齢者が病院や施設に“滞留”している
◆ 介護・医療スタッフの確保も難しく、地方では機能不全
◆ 2025年を過ぎると“行き場のない高齢者”が街にあふれる
本書の中盤では、なぜ病院が潰れていくのか、そしてその制度的原因と “5つの罪” が明かされます。
◆ 医療財政を支配する財務省と厚労省の“都合の良い改革”
◆ 病院淘汰の背後にある「数値目標」と「統合化政策」
◆ 医師の偏在や過重労働、後継者不足が深刻化している
◆ 患者ファーストではなく“制度ファースト”の制度設計
◆ 医療を支える人材に報いる構造が欠落している
本書の後半では、海外事例を交えて未来の医療制度のあり方を提示し、「医療沈没」を避けるための処方箋が語られます。主なポイントは以下の通りです。
◆ スウェーデンやドイツの制度改革に学ぶ“選択と集中”
◆ 日本でも地域医療の“連携強化”が不可欠
◆ テクノロジーの活用で業務負担を軽減せよ
◆ 患者・家族への医療リテラシー教育が鍵になる
◆ “最後のチャンス”は今。2040年の地獄を避けるには行動が必要
この本の締めくくりとして著者は、「医療制度とは“制度設計者の都合”ではなく、“患者のため”にあるべきだ」と強く訴えています。
読み終えたとき、「このままでは自分や家族の未来が危ない」と感じる、警鐘と希望が同居する一冊です。あなたも本書を手に取り、“医療の未来” に目を向けてみませんか?
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3785日目】