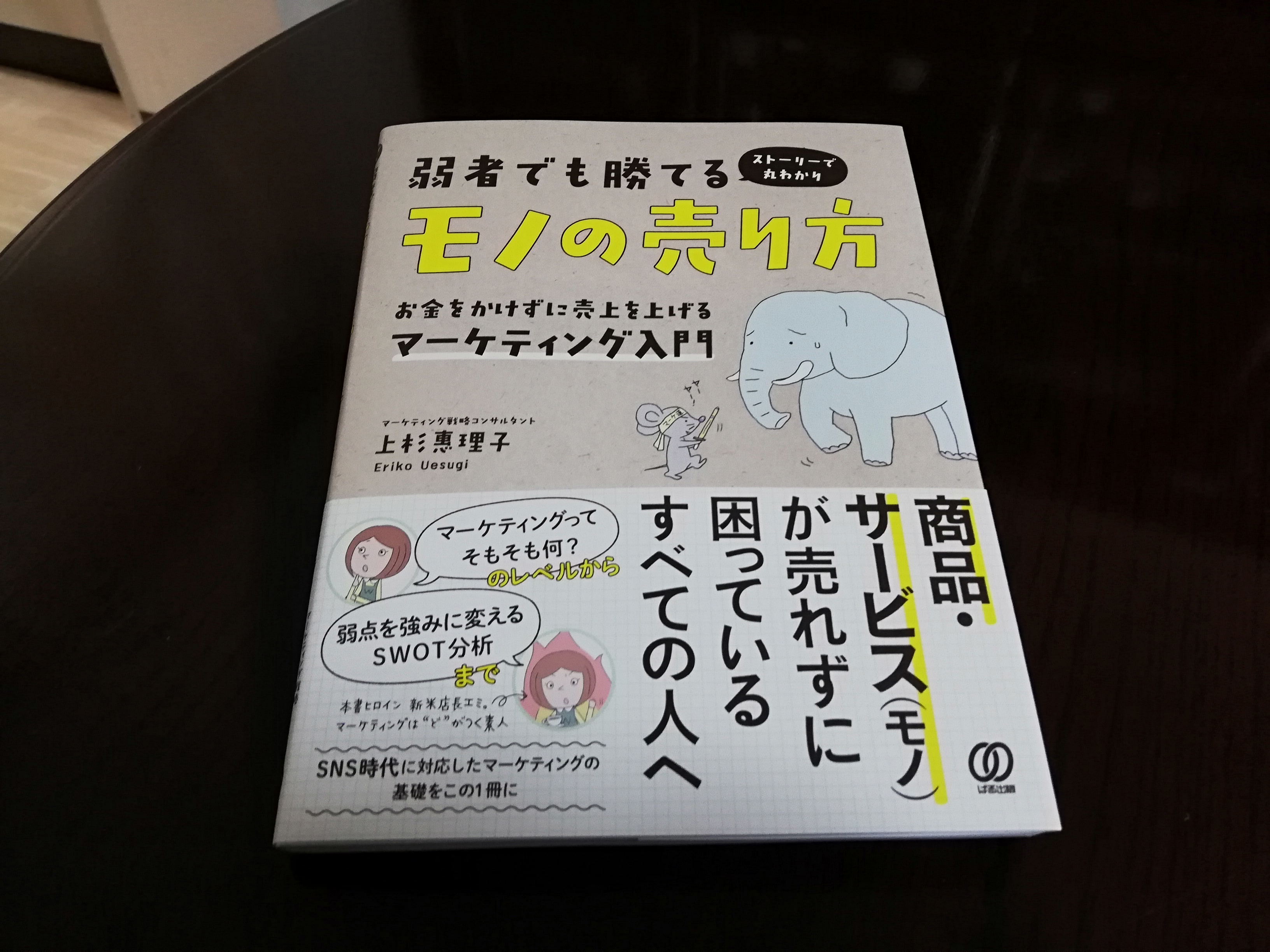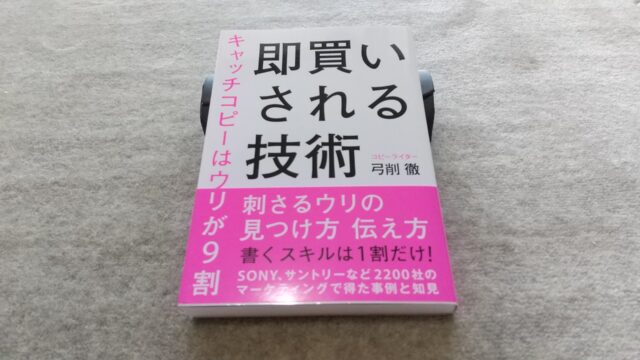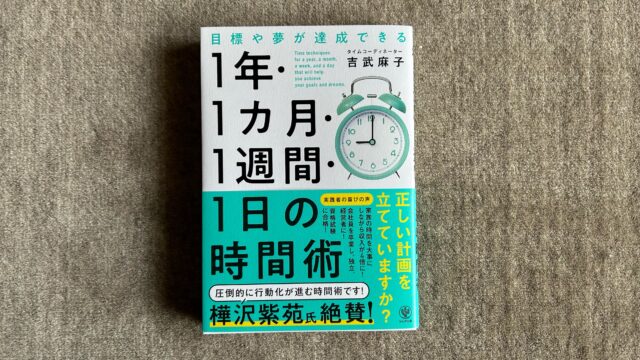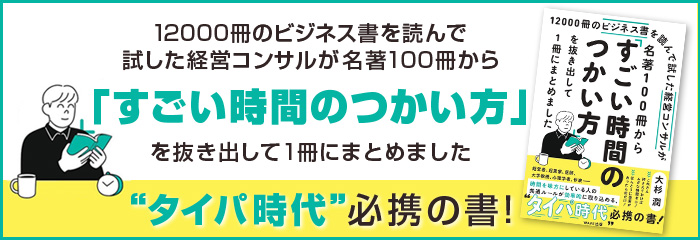本の申し子 「立花隆」が読んだ本

読書家の有名人は数多くいますが、その中でも3本の指に入るのではないかと思うのが、立花隆さんです。一説によると、書庫のためのビルを借りて(通称 「ネコビル」)、数万冊の蔵書をストックしている、ということで、実はビルにも蔵書が収まり切らずに周辺にさらに書棚スペースを借りているという。
ということで、本日は立花隆さんの読書歴が分かるこの本を紹介します。
立花隆 『ぼくの血となり肉となった五〇〇冊そして血にも肉にもならなかった一〇〇冊』 (文藝春秋)
この本は、立花隆さんが 「週刊文春」 に連載していた 『私の読書日記』 の第3弾で、2001年3月15日号から2006年11月2日号までを収録しています。
この読書日記自体も、とても参考になる立花さんの読書歴が分かる記録ですが、この本で特筆すべきは、本論に匹敵するくらいのボリュームがある序論の方です。
ここには、立花さんが著述業(いわゆる 「もの書き」)として、仕事をするために読んできた書籍の変遷が書かれている。立花さんによれば、いいものを書くためには、IO比(インプットとアウトプットの比率)を100対1くらいに保つ必要がある、ということです。
要するに立花さんは1冊本を書くために最低、その百倍の100冊は本を読んできている。立花さんは、この時点ですでに100冊の本を書いていたので、その百倍の1万冊くらいの本は読んでいる、と言っています。
私がこれまでに33年間かけて読んだ総冊数とこの時点で同じ冊数です。立花さんは、その後も猛烈な勢いで読書をされているので、ネコビルとその周辺書棚の蔵書は数万冊に達しているといいます。
立花さんの読書に対する渇望は群を抜いていて、東大仏文科を卒業して文藝春秋に入社したものの、「本ばかり読んではいられない」 という生活環境に置かれたときの「精神的飢餓感」に耐えられなかったということです。
そこで、学士入学で東大哲学科に入学する。面接した教授は、せっかく文芸春秋といういい会社に就職したのだから考え直すよう説得されたということだが、立花さんはすでに退職してしまっていた、といいます。
その後はアルバイトをしながら1食百円で済ませるメニューなどをノートに書いて根津のアパートで本とフトン以外、何もない生活を続けます。木造のアパートは本の重みで床が抜ける寸前になってマンションに移り、そこは鉄筋コンクリートだったが居住部分の造りが木造で床が抜けてしまったそうです。
そういう生活を続けて、「立花隆」というペンネームでもの書きを始めたのが28歳ということで、まさに筋金入りの「本の申し子」と言ってよいでしょう。
その後、1974年に「田中角栄研究」を書いたことにより、立花隆さんは一躍、時の人になる。ここで、「青春漂流時代」も終わりを告げた、と言っています。
この本の長い序論は、前半が立花さんの20代後半から30代前半に焦点をあてて、その間に出会った何冊かの「大きな影響を与えた書物」とその出会いについて詳しく書かれています。
序論の後半は、人生のさまざまな時期に出会った、さまざまな面白い書物について、アトランダムに語っている。この部分は、蔵書を収納している 「ネコビル」 の中で、マイクを付けて書棚の前を歩きながら、目の前に並ぶ本の思い出をしゃべりまくるという、異色の作り方で構成されています。
本の申し子、立花隆さんを形成した青春漂流時代と、その後の人生で出会った本とのストーリーが赤裸々に語られ、知的好奇心が掻き立てられる内容になっています。
この本を読めば、本というのはここまで人生の大きな部分を占めるようになるのか、という驚きも得られます。ここまでの人がいるのだからと、本にのめり込んでしまう自分に安心する面も私はありました。
この本の後半部分は2007年1月現在、今から8年前の時点を基準に書かれています。比較的新しい、当時の新刊本が採り上げられていて興味深いです。
当時はリーマンショックの直前で、その後世界はまた新たなステージに入っている気がしますが、2015年という現在の状況と似た部分があるように感じます。まもなく世界経済が大きな構造変化を迎える直前、という意味で。
紹介されている本は、「500冊と100冊」 というタイトルをはるかに超える数にのぼりますが、具体的な書名などは読んでのお楽しみとさせていただきます。
究極の読書家である立花隆さんを知る最適な書として、この本を推薦したいと思います。
では、今日もハッピーな1日を!