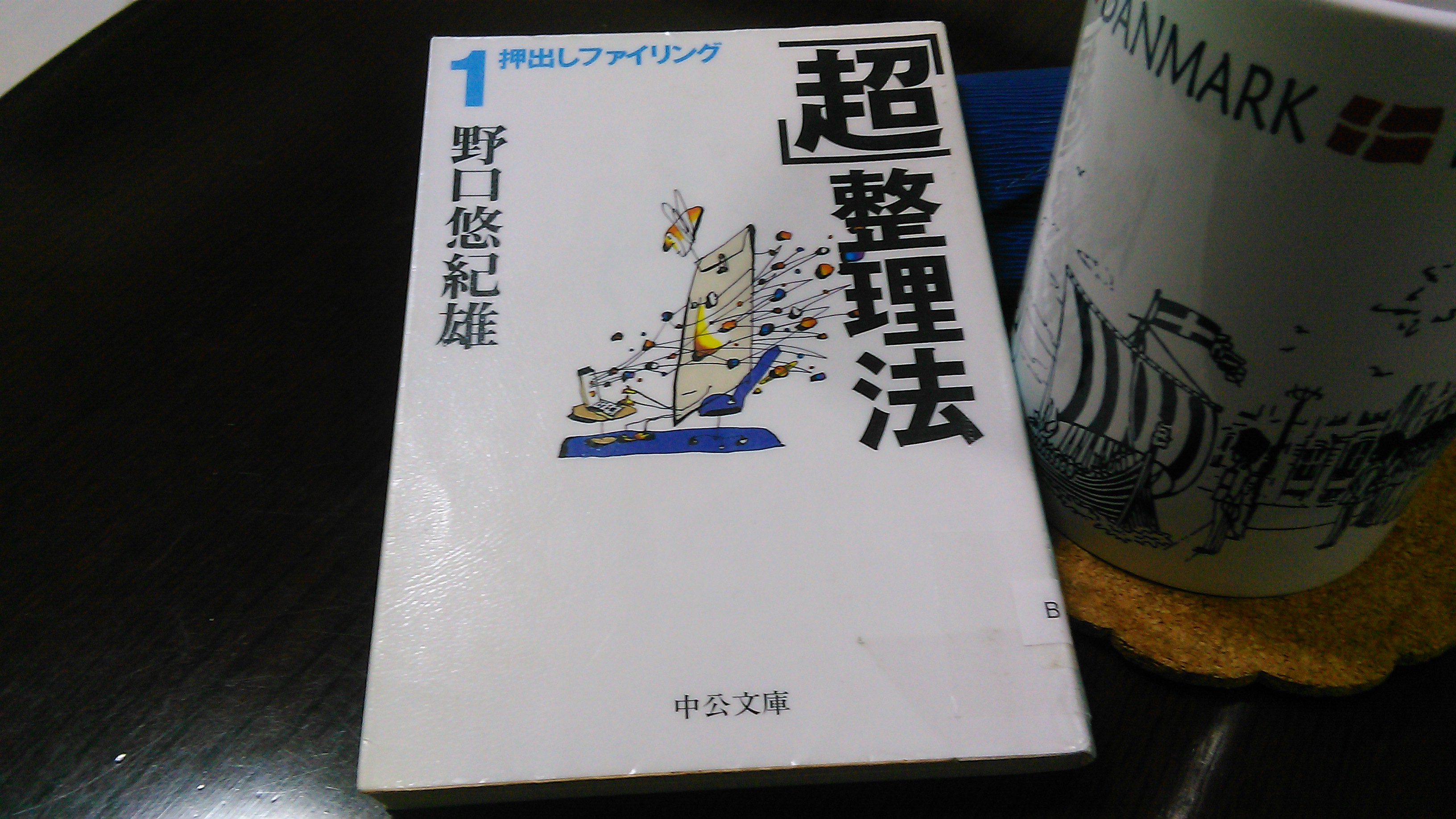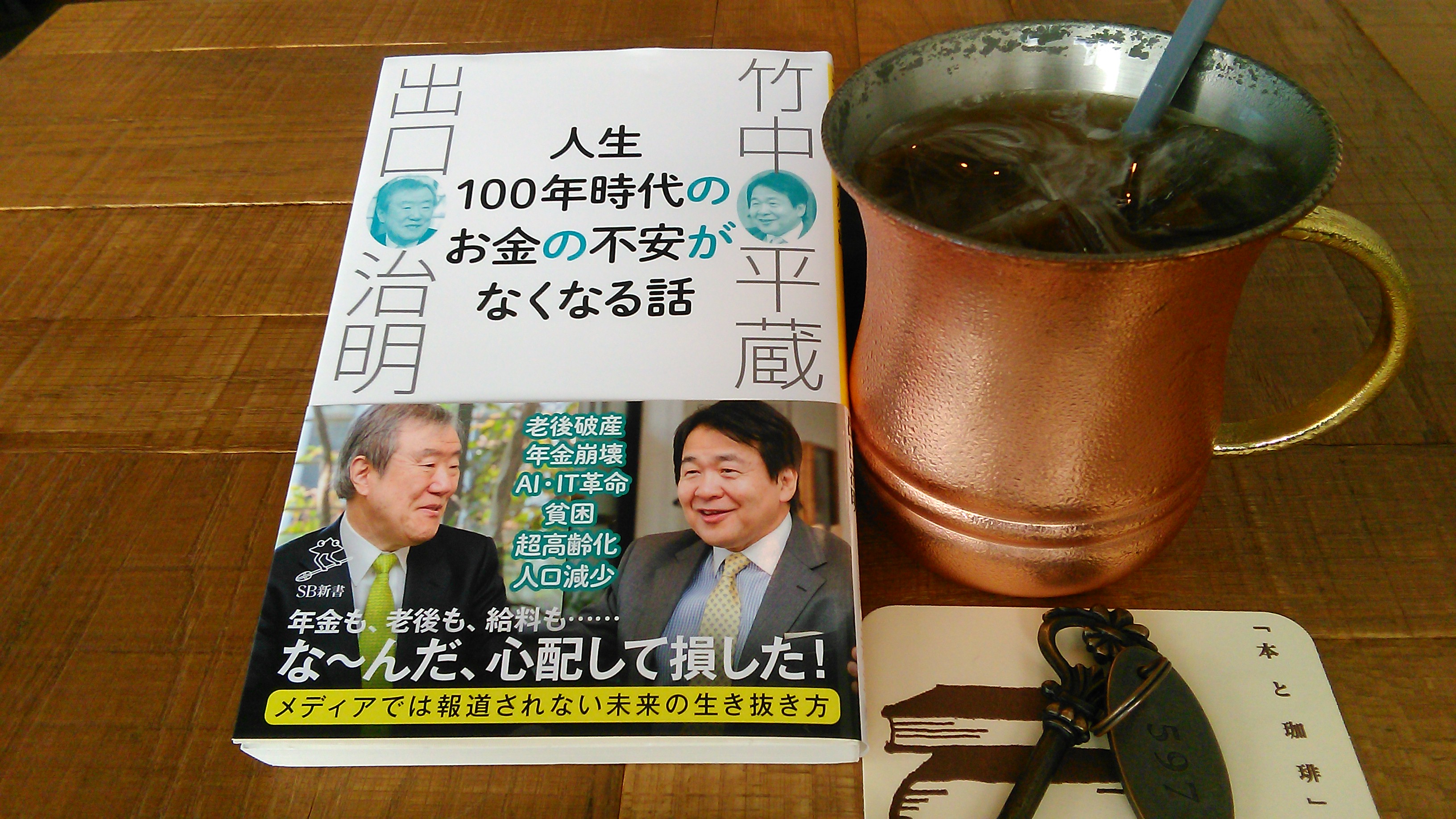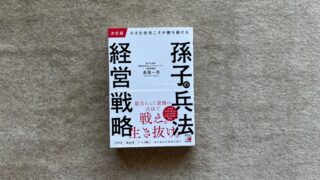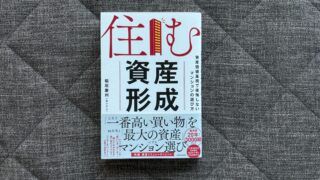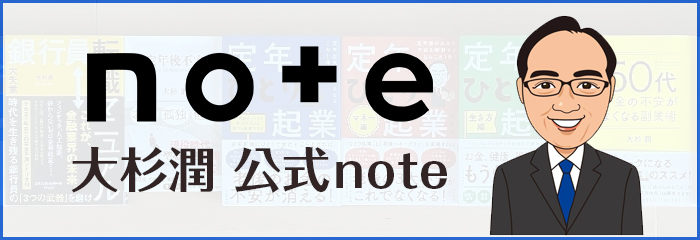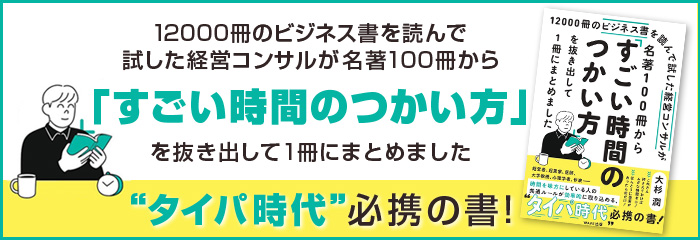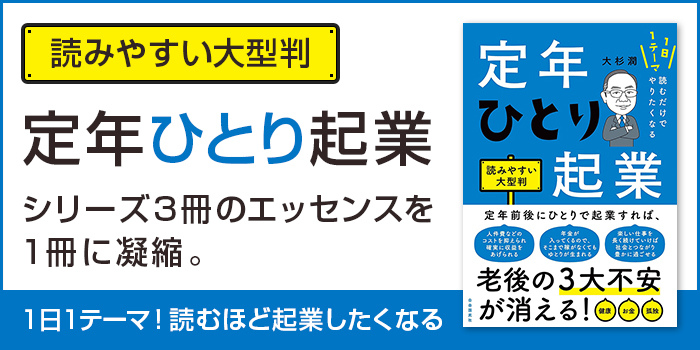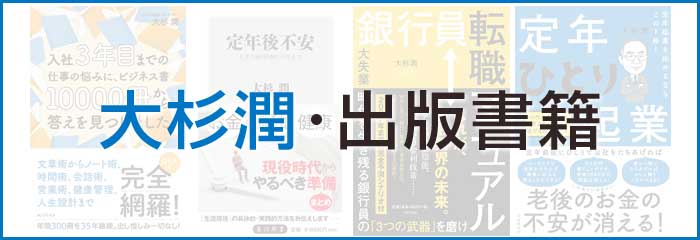『Newsweek 日本版 2025年7月22日号:AIの6原則』

「AIにできること、できないことを峻別して活用すれば、人間の知的生産は格段に向上する」ー そんなメッセージが込められた特集記事があります。
本日紹介するのは、急速に進化・普及するAIの限界と可能性を検証し、仕事や学習の生産性向上に不可欠な「AIの6原則」を提示した、こちらの雑誌特集です。
『Newsweek 日本版 2025年7月22日号:AIの6原則』(CEメディアハウス)
この特集では、ChatGPTをはじめとする生成系AIがビジネス・教育・創作の現場にどのような影響を与えているのかを多面的に検証し、私たちがAIとどう向き合うべきかを提言しています。
この特集記事の構成は以下の5部構成から成っています。
1.テクノロジー:日本人が知っておくべきAIの限界と新たな可能性
2.創造性:チャットGPTが個性的な作家になれない理由
3.LLM:AIは「言葉の意味」にお手上げ
4.教育:知識の値段は急降下、大学の未来はどこに?
5.新研究:それでも人工知能の言語理解能力は改善中
本書の前半では、加速度的に普及する人工知能の実力は「人類の夢」にはほど遠く、以下の6つの教訓が紹介されています。
◆ 制御するのは常に人間でなければならない
◆ 自動化ではなく「AIとの協働」を目指せ
◆ AIが得意とするタスクを選ぶ
◆ AIは答えではなく可能性を生み出すために使う
◆ 人間の課題を解決する
◆ 創造的パートナーシップを築く
この本の中盤では、「チャットGPTが個性的な作家になれない理由」および「AIは『言葉の意味』にお手上げについて説明しています。主なポイントは次の通り。
◆ 作家はソフトウェア開発者によるLLMの使い方から学ぶべき
◆ 良質なプロンプトを与えることが重要
◆ AIに「創造性」は要らない
◆ AIに必要なのは、人間に近い感覚で物事の意味を理解すること
本書の後半では、「知識の値段は急降下、大学の未来はどこに?」および「それでも人工知能の言語理解能力は改善中」について、AIの限界と最新の進化を深掘りし、教育や社会制度へのインパクトを考察しています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 知識の希少性は薄れ、その供給が飛躍的に増えて価格は下がった
◆ 未来はAIとの共存にあり
◆ 教育現場におけるAI活用と「知識の価値」の再定義
◆ 言語理解力が向上しつつあるAIの「現在地」
この本の締めくくりとして、AIはまだ万能ではないが、正しく使えば、人間の知性を拡張する最強のパートナーになる、と述べられています。
AI時代を生きる私たちにとって、もはや「AIとの共存」は選択ではなく前提です。だからこそ、AIの限界を知り、人間にしかできない知的活動に集中する戦略が、これからの時代のリテラシーとなるのではないでしょうか。
AIに仕事を奪われる不安を抱くより、「AIを使って成果を10倍にする発想」を持てば、可能性は一気に広がります。ぜひ本特集を通じて、あなた自身の「AI活用ルール」を見つけてみてください。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3797日目】