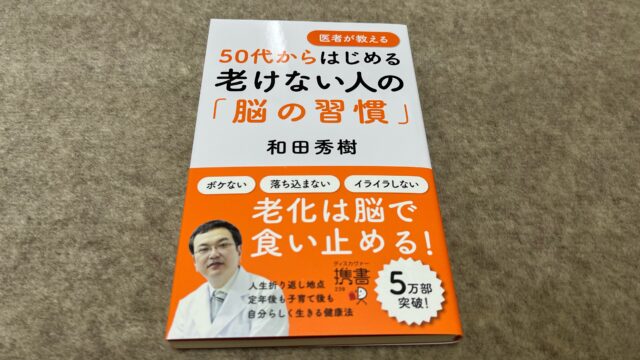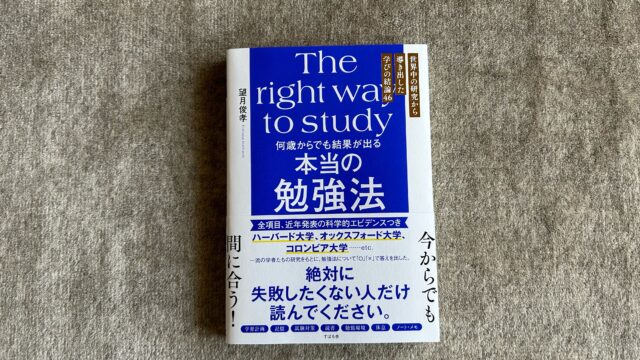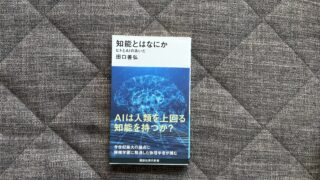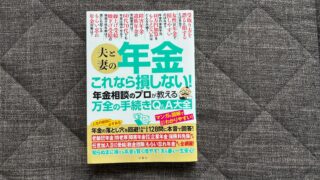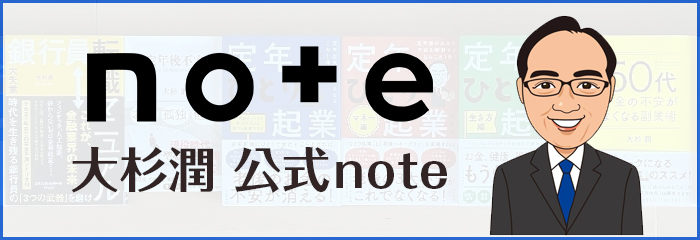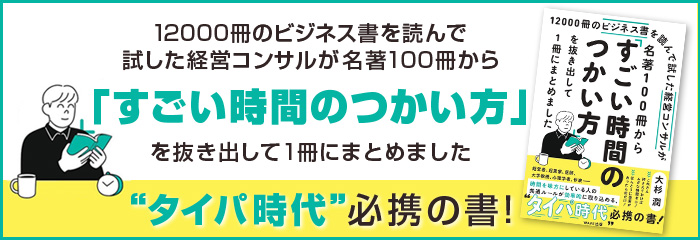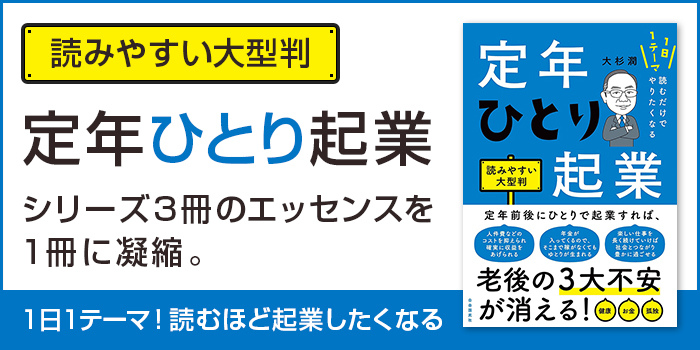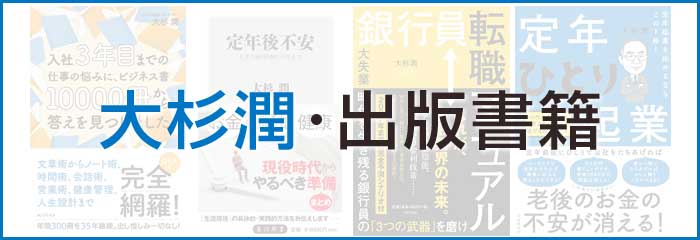『なぜ社会は変わるのか はじめての社会運動論』
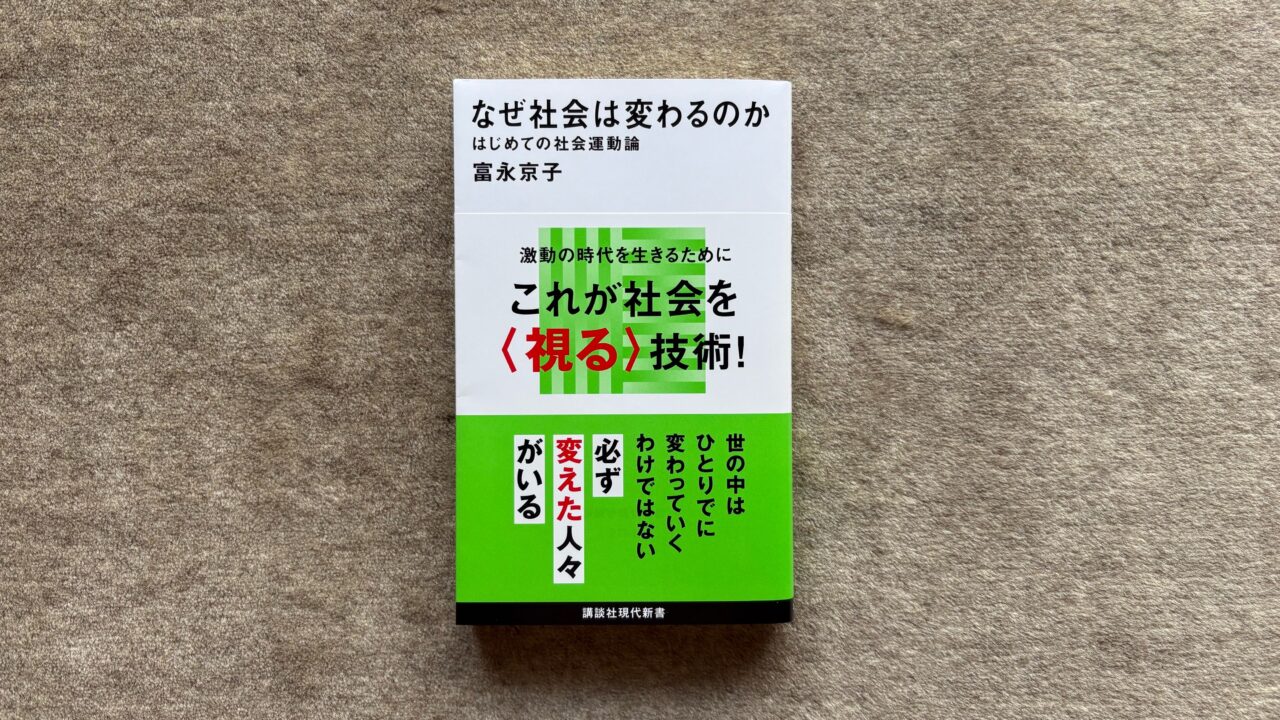
「社会はひとりでに変わっていくわけではない。そこには必ず“変えた”人たちがいる」――そんな力強いメッセージから始まる一冊があります。
本日紹介するのは、1986年生まれ、東京大学大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了後、日本学術振興会特別研究員(PD)を経て2015年より、立命館大学産業社会学部准教授の富永京子(とみなが・きょうこ)さんが書いたこちらの書籍です。
富永京子『なぜ社会は変わるのか はじめての社会運動論』(講談社現代新書)
本書は、日本初となる社会運動論の入門書であり、デモ、ストライキ、不買運動など、社会運動がどのように生まれ、発展し、社会を変えていくのかを体系的に解説します。怒りや不満といった感情だけでは運動は持続せず、資源、組織、政治的機会、フレーム(伝え方)など、複数の要素が複雑に絡み合って社会変革が進むプロセスを、最新の理論と豊富な事例で明らかにしています。
本書は以下の10部構成から成っています。
1.社会運動とはなにか
2.集合行動論
3.フリーライダー問題から資源動員論へ
4.政治過程論/動員構造論
5.政治的機会構造論
6.フレーム分析
7.新しい社会運動論
8.社会運動と文化論
9.2000年代の社会運動論
10.社会は社会運動であふれている
この本の冒頭で著者は、「社会を変えるのは、自然な流れや時代の必然ではなく、行動を起こした人たちである」と語ります。そして、社会運動は単なる突発的な集団行動ではなく、理論的な背景と戦略的な枠組みを持つことを強調します。
本書の前半では、「社会運動とはなにか」「集合行動論」「フリーライダー問題から資源動員論へ」および「政治過程論/動員構造論」について、以下のポイントを説明しています。
◆ 社会運動は社会構造の変化を目指す集団的行動である
◆ 怒りや不満は契機になるが、それだけでは持続しない
◆ 成功する運動には資金、人材、情報といった資源が不可欠である
◆ 既存のつながりやネットワークが動員の基盤となる
◆ 政治側の動向や「成功しそう」と思える見通しが重要な要因となる
この本の中盤では、「政治的機会構造論」「フレーム分析」「新しい社会運動論」および「社会運動と文化論」について考察しています。主なポイントは次の通り。
◆ 政治の「聞く耳」の度合いを測ることが運動戦略に直結する
◆ フレーム(伝え方)は運動の受け止められ方を左右する
◆ マイノリティが私的領域を通じて発信する新しい運動の形が注目される
◆ 資源や政治機会だけでなく、文化的背景が運動の成否を左右する
◆ 社会運動は時代や文脈に応じて進化していく
本書の後半では、「2000年代の社会運動論」および「社会は社会運動であふれている」について論じています。主なポイントは以下の通りです。
◆ MTT(Movement Theory and Theory)と経験的研究が統合されつつある
◆ 2000年代以降の社会運動は多様化し、オンライン空間との融合が進んだ
◆ 小規模でローカルな運動も社会変化の契機となる
◆ 運動の成果は政策だけでなく社会の価値観や文化にも表れる
◆ 社会は常に多様な社会運動によって動かされている
この本の締めくくりとして著者は、「社会を変える力は、特別な人や大規模な団体だけでなく、日常の中で行動を起こすすべての人に宿っている」と述べています。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3815日目】