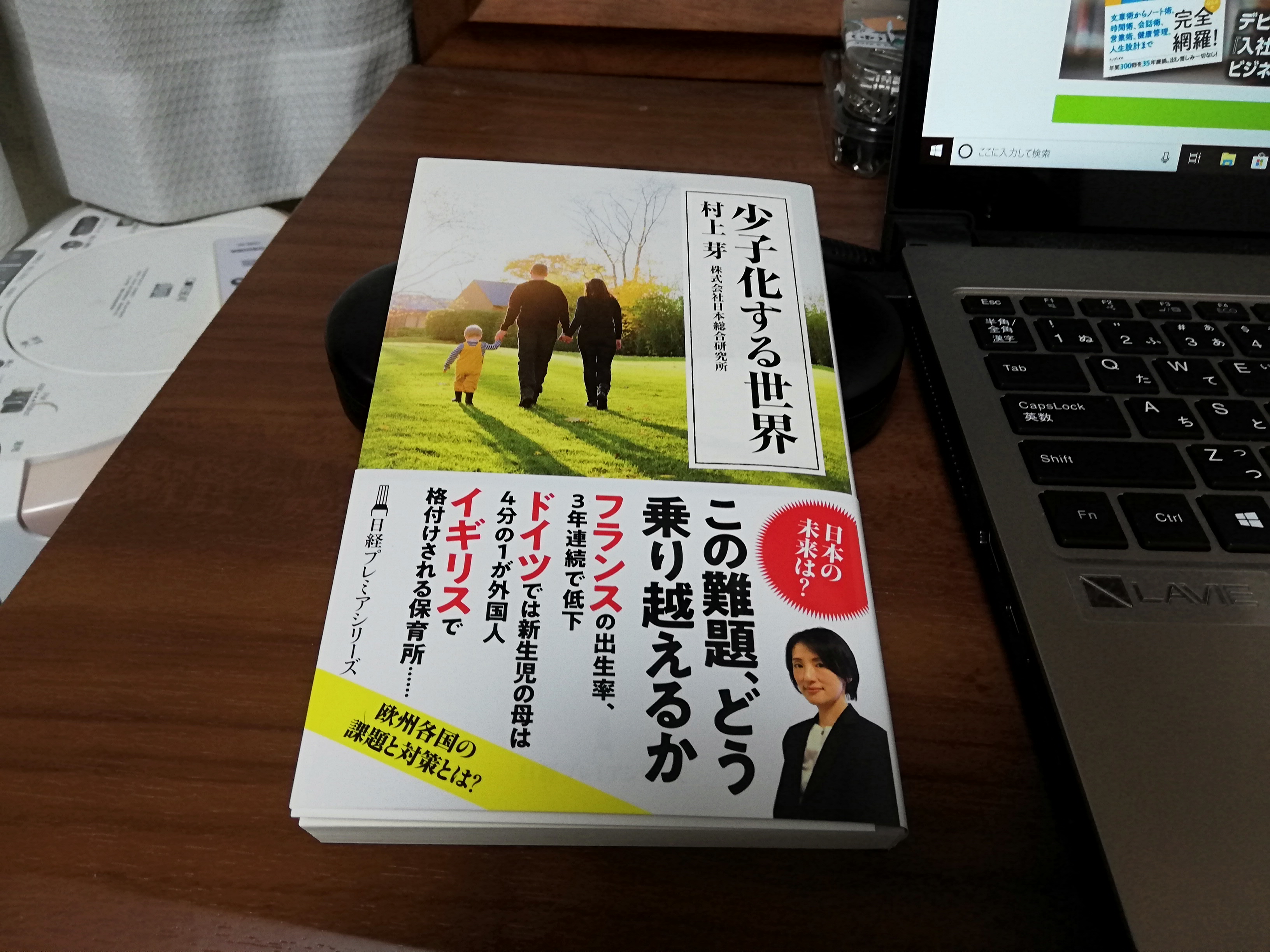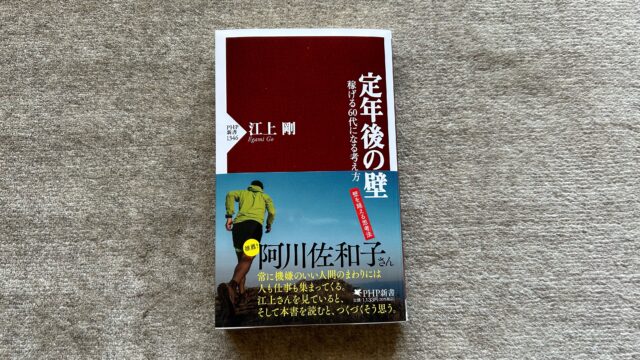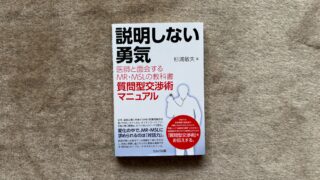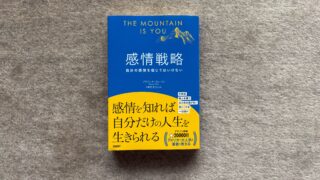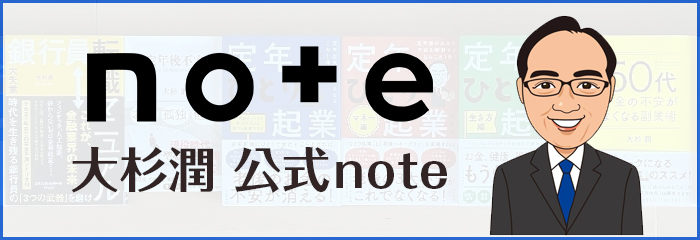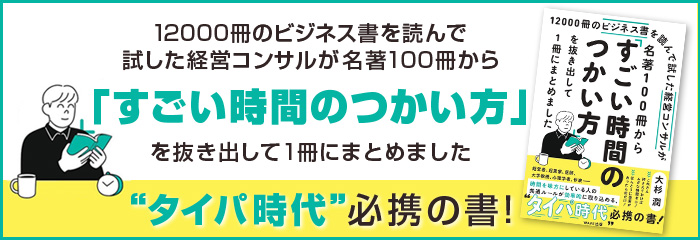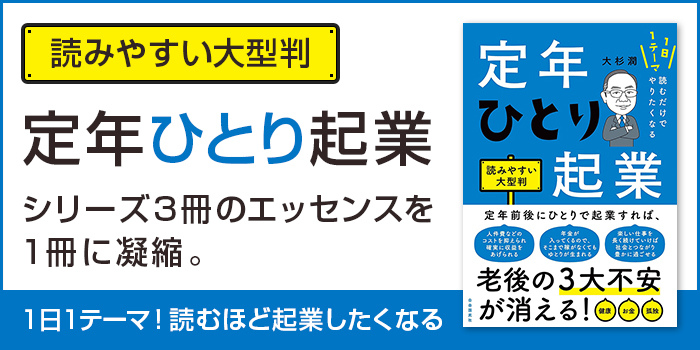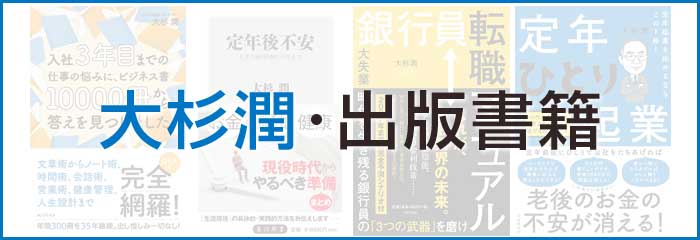『なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法 』
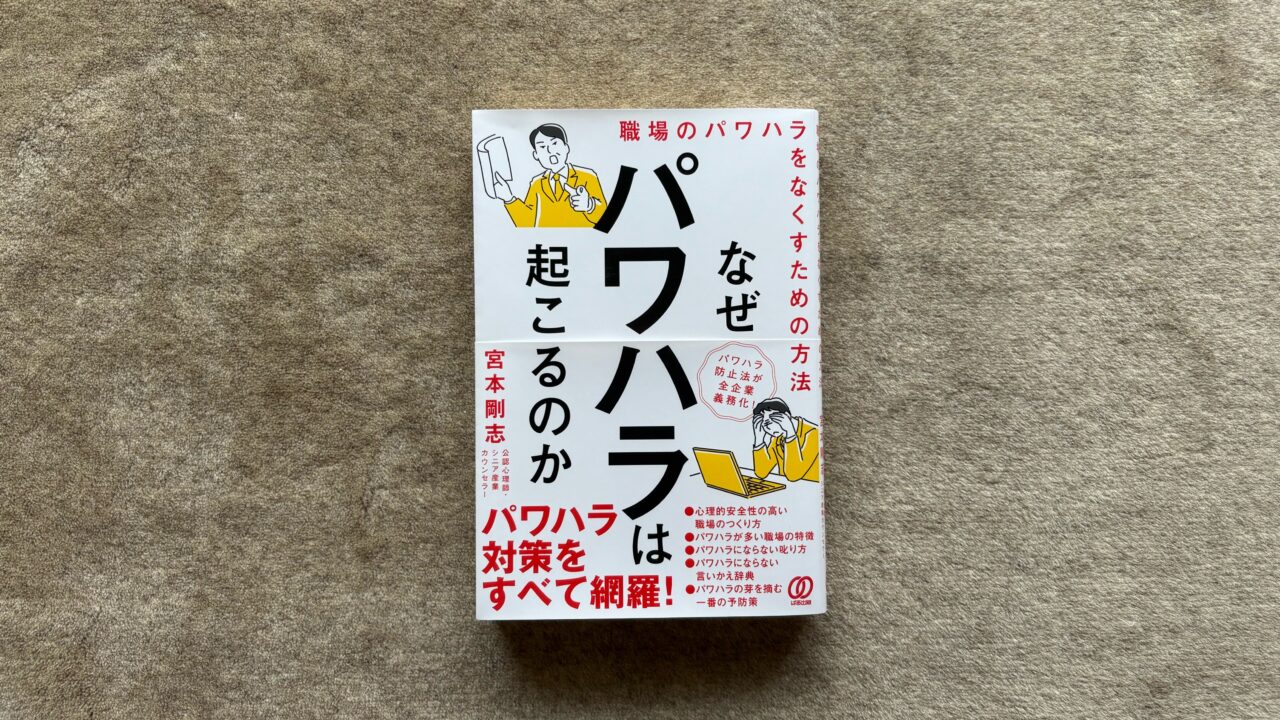
「パワハラは、誰か一人の性格や能力の問題ではなく、組織文化や暗黙のルールが温床となって生まれる」――そんな厳しい現実を突きつける一冊があります。
本日紹介するのは、管理職として部下との関わりに悩んだ経験をきっかけにハラスメントを学び始め、心理学に基づく研修やハラスメント被害者・加害者の面談、さらに企業研修を年間200回、カウンセリングを年間400人に実施。現在は株式会社メンタル・リンク代表取締役社長・公認心理師として、企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務め、NHK『所さん!事件ですよ』やTBS『THE TIME,』など多数のメディアにも出演。著書に『「ハラスメント」の解剖図鑑』『こんなの理不尽!怒る上司のトリセツ』『「怒り」とうまくつき合う──アンガーマネジメント』がある宮本剛志(みやもと・つよし)さんが書いたこちらの書籍です。
宮本剛志『なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法』(ぱる出版)
この本は、加害者・被害者・第三者・組織、すべての視点からパワハラをなくす方法を網羅的に解説しています。
本書は以下の6部構成でから成っています。
1.パワハラってなに?
2.なぜパワハラは起きるのか─無意識の土壌を探る
3.この場面、セーフ? アウト?─リアルケース集
4.パワハラにならない上手な叱り方
5.その一言を変えるだけで、空気は変わる─パワハラにならない言いかえ辞典
6.パワハラのない職場のつくり方
この本の冒頭で著者は、パワハラは単純に「性格が悪いから」「能力がないから」起きるのではなく、組織に潜むさまざまな要因が絡み合い、無意識のうちに温床が作られてしまうと指摘しています。
本書の前半では、「パワハラってなに?」および「なぜパワハラは起きるのか──無意識の土壌を探る」について、パワハラの6つのタイプや見極めの3ポイント、加害者になりやすい特徴などを解説しています。主なポイントは以下の通りです。
◆ パワハラには6つのタイプが存在する
◆ 「3つのポイント」でパワハラかどうかを判断できる
◆ 無自覚な加害者は知識不足・自己理解不足・一定の会話パターンに陥っている
◆ 「人間関係」が最大のストレス要因である
◆ 組織文化や認知バイアスがパワハラの温床になる
この本の中盤では、「この場面、セーフ? アウト?」および「パワハラにならない上手な叱り方」について、リアルケース集や感情をコントロールした叱り方を示しています。主なポイントは次の通りです。
◆ グレーなケースでも3要素で検証し判断できる
◆ 公衆の面前で叱ることはパワハラにつながりやすい
◆ 「叱る」と「怒る」の違いを明確にする
◆ 叱る目的は「行動変容」であり、人格攻撃ではない
◆ イライラ感情の仕組みを理解し、コントロールする
本書の後半では、「言いかえ辞典」および「パワハラのない職場のつくり方」について、すぐに使える実践的な工夫や心理的安全性を高める方法が紹介されています。主なポイントは以下の通りです。
◆ 「なんでできないの?」を「どうすればできる?」に言いかえる
◆ ネガティブな言葉をポジティブに転換する習慣を持つ
◆ 犯人探しではなく、職場全体の改善に注力する
◆ 心理的安全性の誤解をなくし、建設的な対話を重ねる
◆ 日常的な声かけや行動共有がパワハラ防止につながる
この本の締めくくりとして著者は、「パワハラのない職場は、誰もが安心して能力を発揮できる場所であり、それは組織の成果にも直結する」と述べています。
パワハラ防止法が全企業に義務づけられた今、本書は経営者や管理職はもちろん、働くすべての人にとって必携の実用書といえるでしょう。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3862日目】