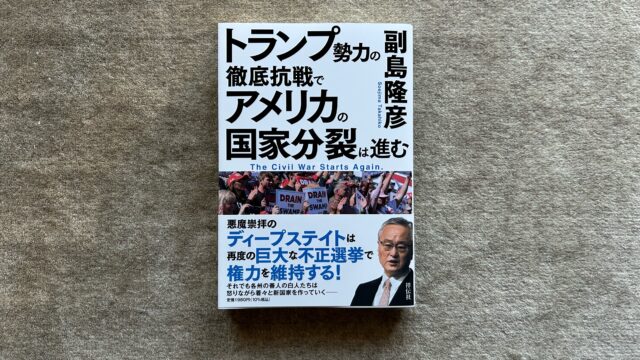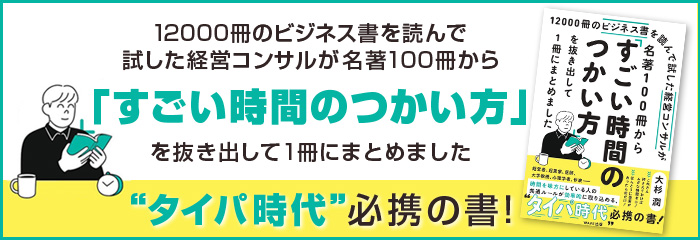渡辺淳一『孤舟』(集英社文庫)

渡辺淳一氏は『失楽園』をはじめとする売れっ子作家であり、医師の立場から男女の心の機微を描くことで定評がある。それだけに、地味な内容の本書を薦める人は少ない。
そうした定評と異なり本書を採り上げた理由は、テーマが今後の少子高齢化社会において、欠くべからざる重要な面を捉えているからだ。とくに順調なビジネスマン人生を送った人々には切実だ。
定年退職後の孤独を描いた作品として、本書のリアリティは格別だ。自由な時間に胸ふくらませていた主人公は、定年退職により大きく変化した人間関係を現実と受け止められない。
子どもは飛び立ち、妻との関係は大きく変化し、家族という基盤がいかに脆いものかを思い知らされる。多くの定年退職後の家庭に起きる状況だ。
かつての職場の同僚や後輩も、現役ではなくなった主人公には関心が急速に薄れていく。目の前の課題に精いっぱいで、それどころではないのだ。これも多くの退職者が味わう日常だろう。
突然の孤独感に襲われた主人公は、心の隙間を埋めるために、思いもかけなかった行動に出る。非日常とも思える行動も、追い詰められ、プライドを取り戻したい退職者には必然なのだろう。
会社生活が残り少なくなったベテラン社員や会社幹部であっても、なかなか定年退職後の自らの姿はイメージできない。そして退職日を境に、自らを取り巻く環境は激変してしまう。
現役時代には考えもしなかった孤独感に突如、襲われるようになるのだ。 「毎日が日曜日」(城山三郎の小説の題名)は、毎日が孤独と同義語だ。
小説作品としては地味だが、本書はこれから多くの団塊の世代のビジネスマン退職者に発生するであろう社会問題を先取りしているという意味で、とても興味深い。
小説は、自分で体験できないことを前もって追体験できることが醍醐味だ。定年退職を控えた多くのビジネスマンや定年退職後の孤独な元ビジネスマンに本書を薦めたい。
予め心の準備や、あまりにカッコ悪い主人公に接して、少しは気が楽になるかもしれない。何より、現代の社会問題として、多くの示唆を得るに違いない。