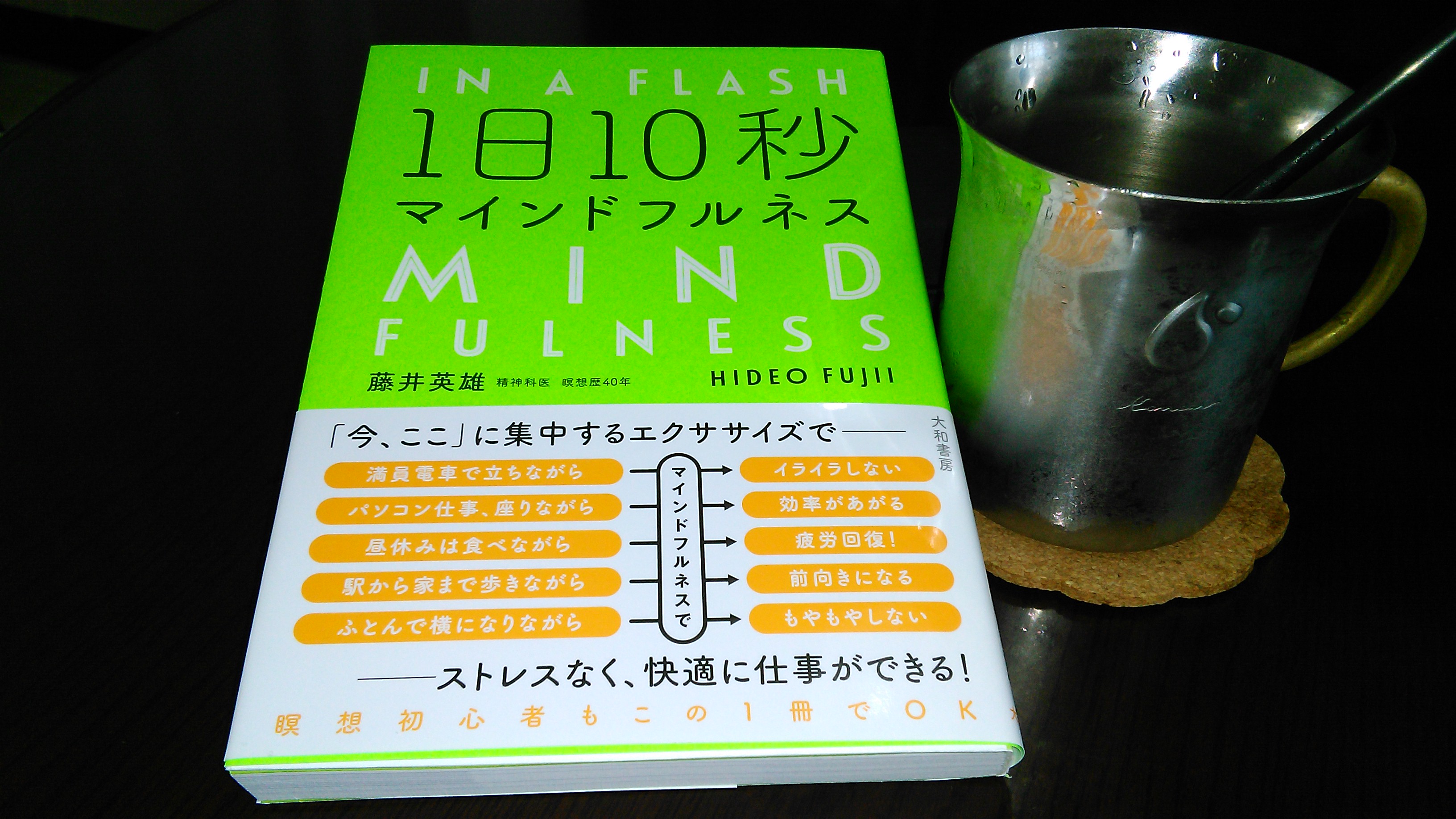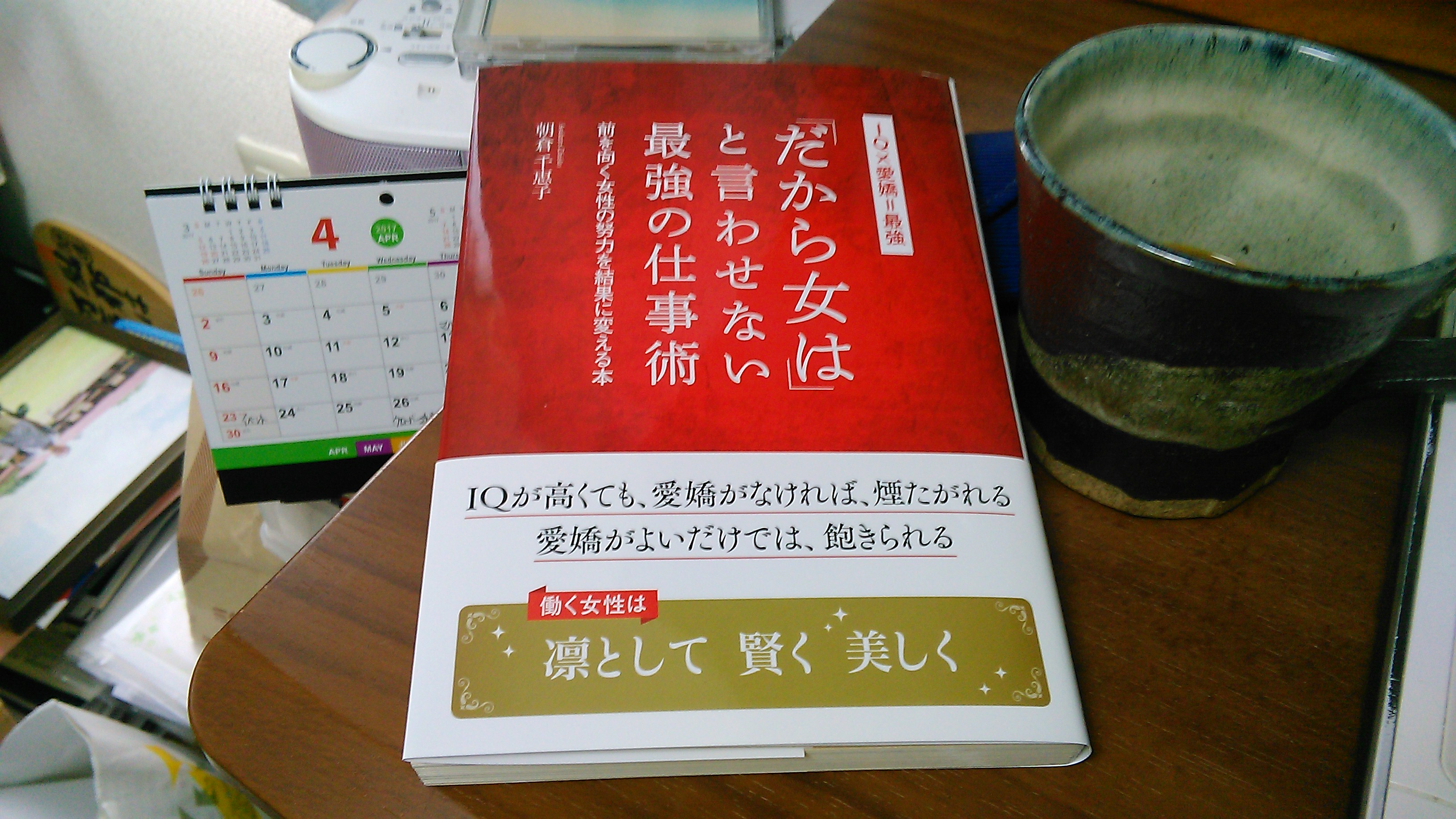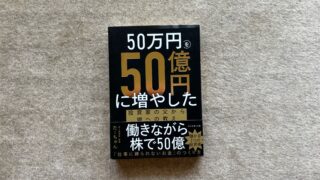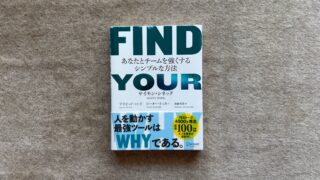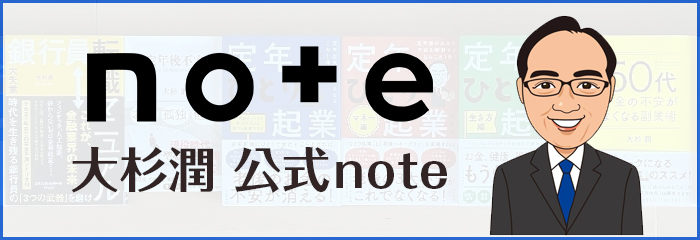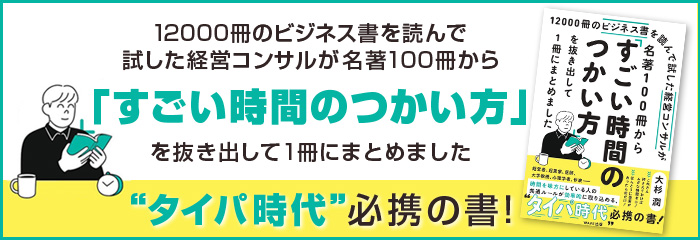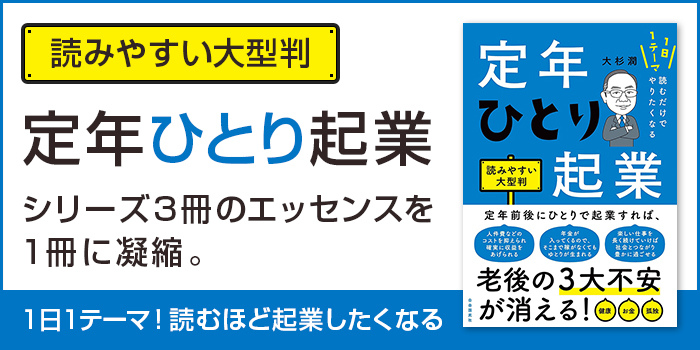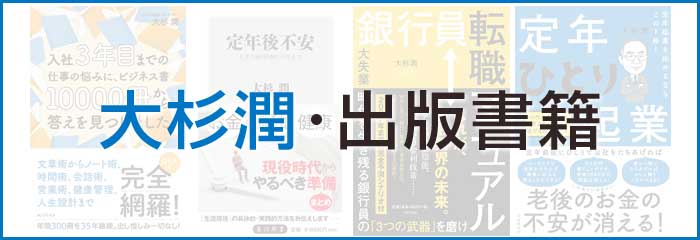『世界のビジネスエリートが身につけている コーヒーの教養』
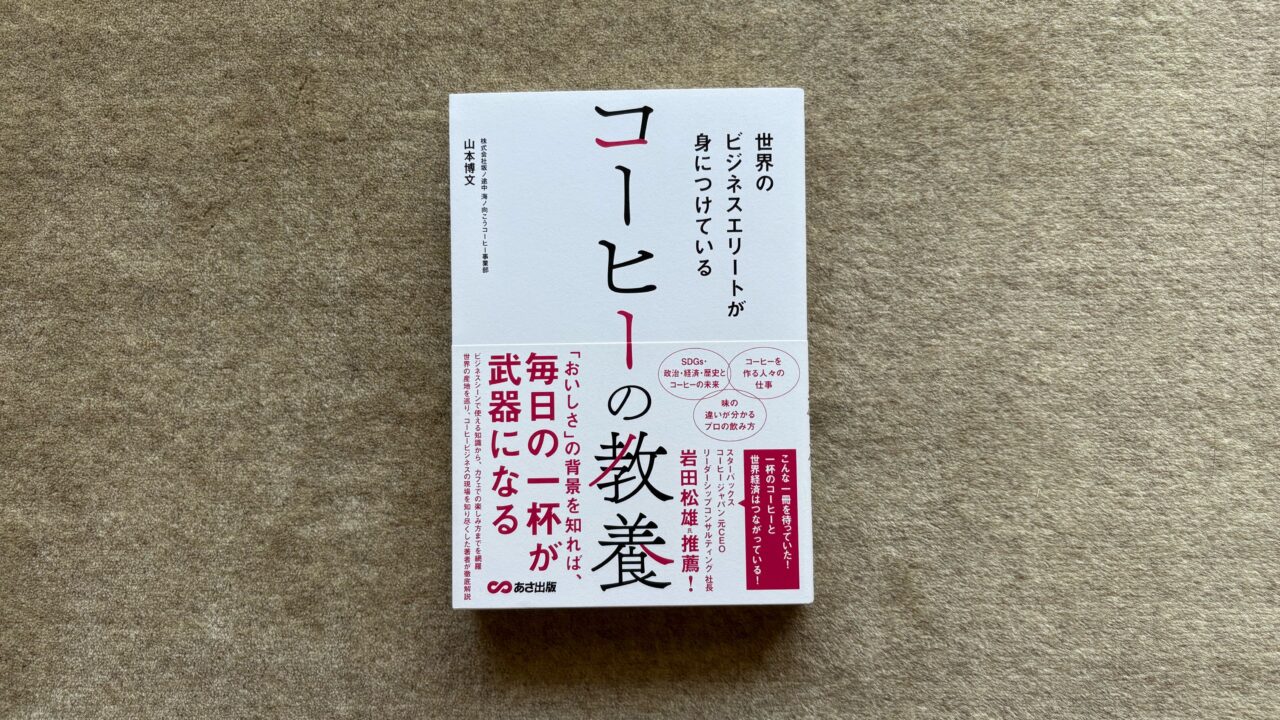
「いま飲んでいる一杯が、美味しいのはなぜだろう?」――そんな問いから始まる、コーヒーを通じて世界とつながる “教養の一冊” があります。
本日紹介するのは、2013年から2年間、フィリピンのベンゲット州国立大学に留学し、アグロフォレストリー研究所でコーヒー栽培について研究、現地NGO「コーディリエラ・グリーン・ネットワーク(CGN)」と協力し、農家への栽培指導や植林活動を行って、帰国後はコーヒー生産技術の専門家としてアジアを中心に世界各地のコーヒー産地を巡り、持続可能な生産支援や環境保全活動に取り組む第一線のビジネスパーソン、株式会社坂ノ途中「海ノ向こうコーヒー」事業部の事業開発責任者として、コーヒー生豆の輸入から現地農家支援までを行う山本博文さんが、日常の一杯を豊かにする知識と視点を詰め込んだこちらの書籍です。
山本博文『世界のビジネスエリートが身につけている コーヒーの教養』(あさ出版)
この本は、単なる趣味や嗜好品としてのコーヒーではなく、“語れる教養” として、そして地球規模でつながる社会問題として捉えなおす視座を与えてくれる本です。
本書は、以下の3部構成から成り立っています。
1.コーヒーで世界を広げる
2.一杯のコーヒーを深く知る
3.日常のコーヒーをもっと楽しむ
この本の冒頭で著者は、「ヨーロッパのコーヒーハウスで商人や知識人が議論を交わしていたように、現代でも一杯のコーヒーは、ビジネスの文脈や社会背景と深く結びついている」と述べています。
本書の前半では、「世界で活躍するビジネスパーソンにコーヒーが選ばれる理由」「意外と知らない、コーヒーの基礎知識」および「産地ごとの味わいに学ぶ、コーヒーと政治経済の関係」について、以下のポイントを説明しています。
◆ コーヒーは“嗜好品”でありながら、“経済指標”でもある
◆ 産地の政治・経済情勢が、そのまま味わいや価格に反映される
◆ フィリピンやミャンマーなど新興国の動向がコーヒー業界を左右する
◆ 歴史を学ぶことで、コーヒーに対する敬意と理解が深まる
◆ ビジネスの現場でも、コーヒーを語れる人は一目置かれる存在になれる
この本の中盤では、「コーヒーの味の違いを楽しむプロの飲み方」および「サプライチェーンから見る、コーヒーの味の作り方」など、実践的な知識が展開されています。主なポイントは以下の通りです。
◆ カッピングは、五感でコーヒーを理解する“味の言語”である
◆ 収穫、精製、輸送、焙煎、抽出のすべてが味に影響する
◆ フェアトレードや環境配慮も、“美味しさ”の本質に関わっている
◆ 「誰が、どこで、どう育てたか」が、コーヒーの個性を決める
◆ “味の裏側”を知ると、いつもの一杯がドラマに変わる
本書の後半では、「淹れ方、選び方、歴史~いつものコーヒーが違って見える、知識と楽しみ方」および「コーヒーの未来を作る仕事」が提示されます。主なポイントは以下の通りです。
◆ コーヒーメニューの背景にある文化的意味を理解する
◆ 抽出器具や温度、豆の選び方次第で味が劇的に変化する
◆ 日本の喫茶文化は世界的にもユニークで奥深い
◆ 生産地の気候変動や森林破壊が、将来のコーヒーを脅かしている
◆ 一杯の選択が、世界の農家と環境を支えるアクションになる
この本の締めくくりとして著者は、「日常にあるコーヒーが、世界を知るきっかけになり、会話を生み出し、行動を変える――そんな未来を信じてこの本を書きました」と語っています。
ビジネス、文化、サステナビリティすべてが詰まった “知的な一杯” 、コーヒーを愛するすべての人に届けたい、味わい深い一冊に仕上がっています。
ビジネス書の紹介・活用法を配信しているYouTubeチャンネル『大杉潤のYouTubeビジネススクール』の「紹介動画」はこちらです。ぜひ、チャンネル登録をしてみてください。
https://www.youtube.com/channel/UCIwJA0CZFgYK1BXrJ7fuKMQ
では、今日もハッピーな1日を!【3810日目】